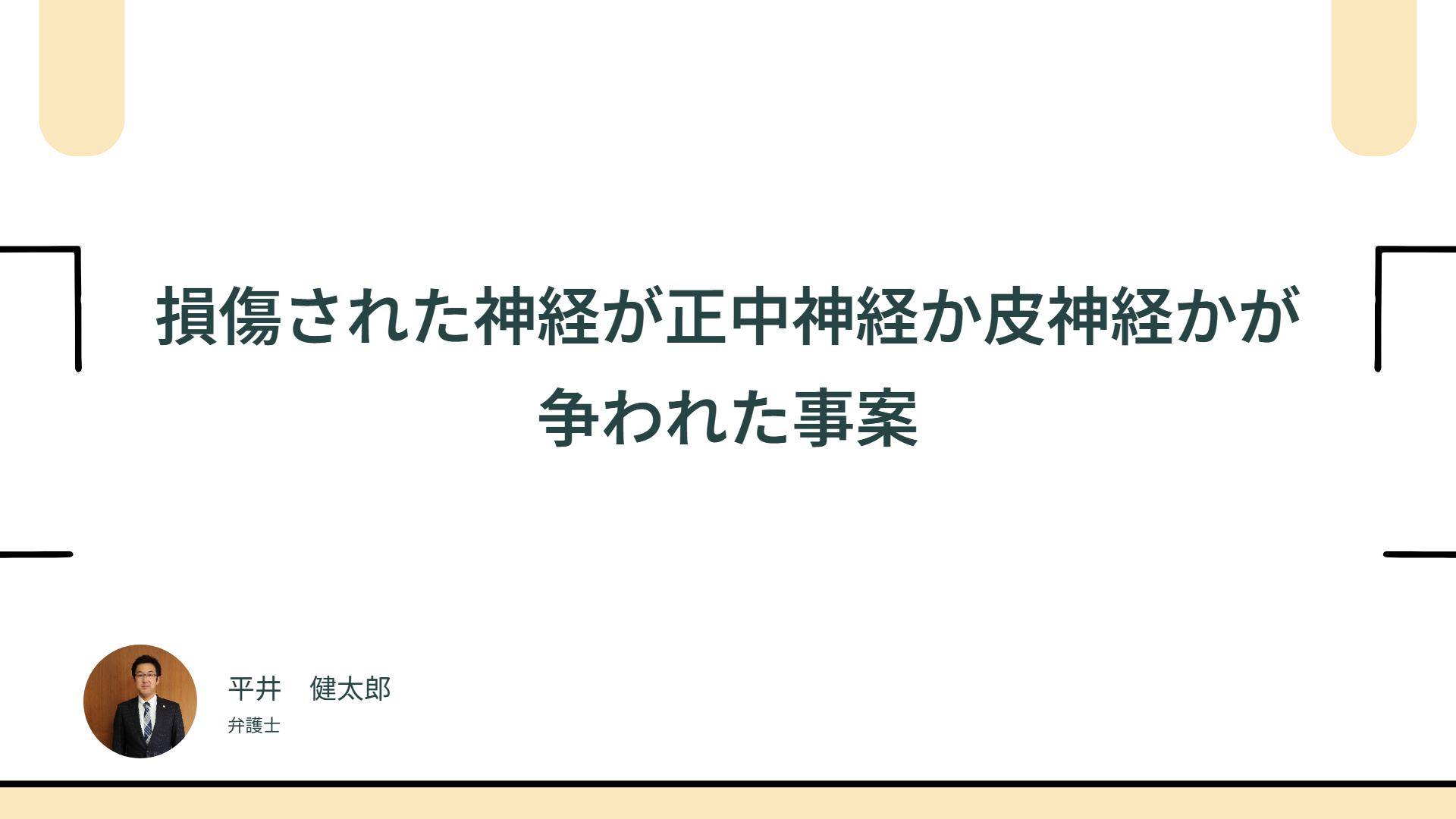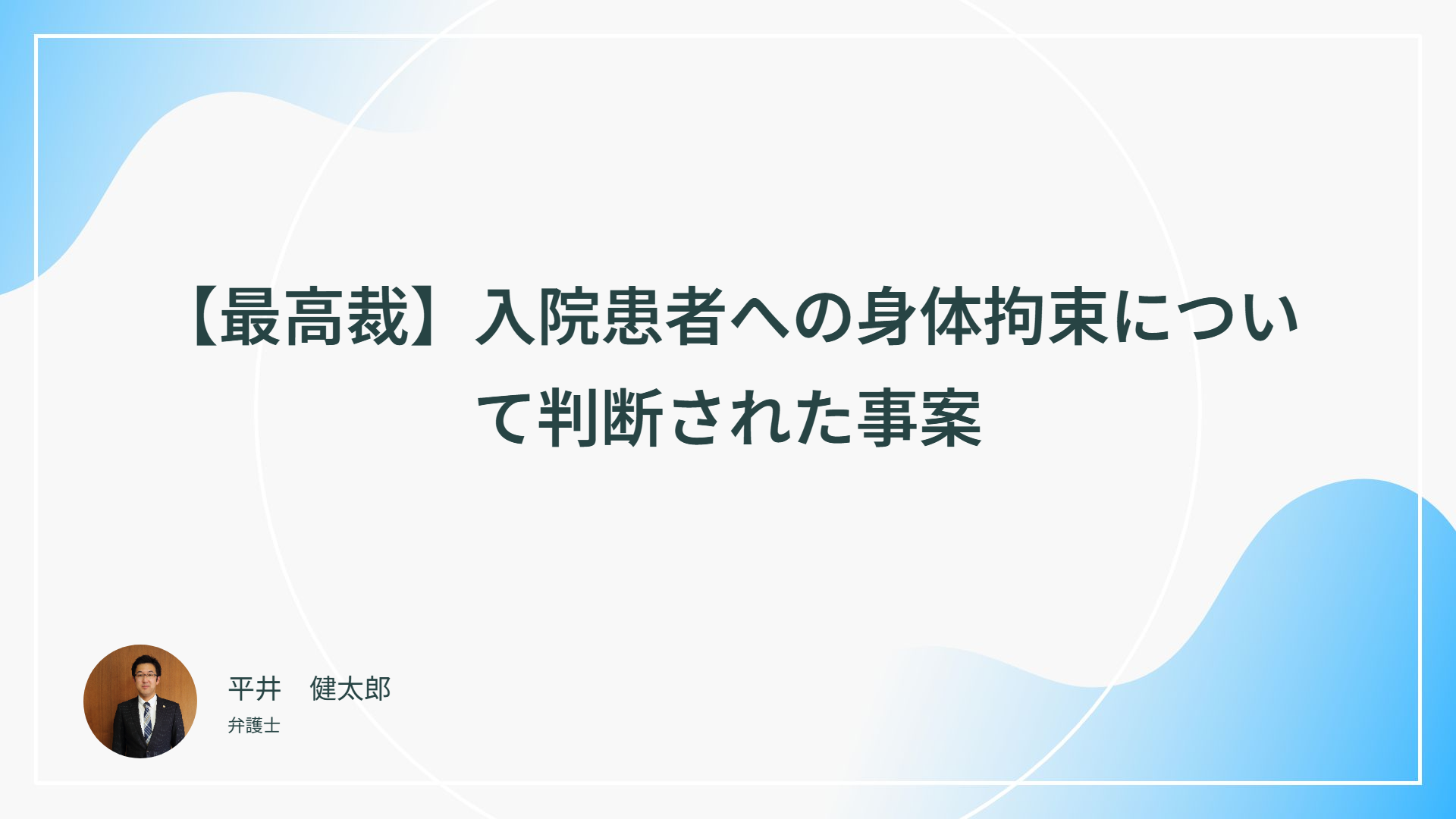帝王切開等の実施の検討することなく、状況を正確に把握せず陣痛促進薬による分娩を続行する判断をした事案
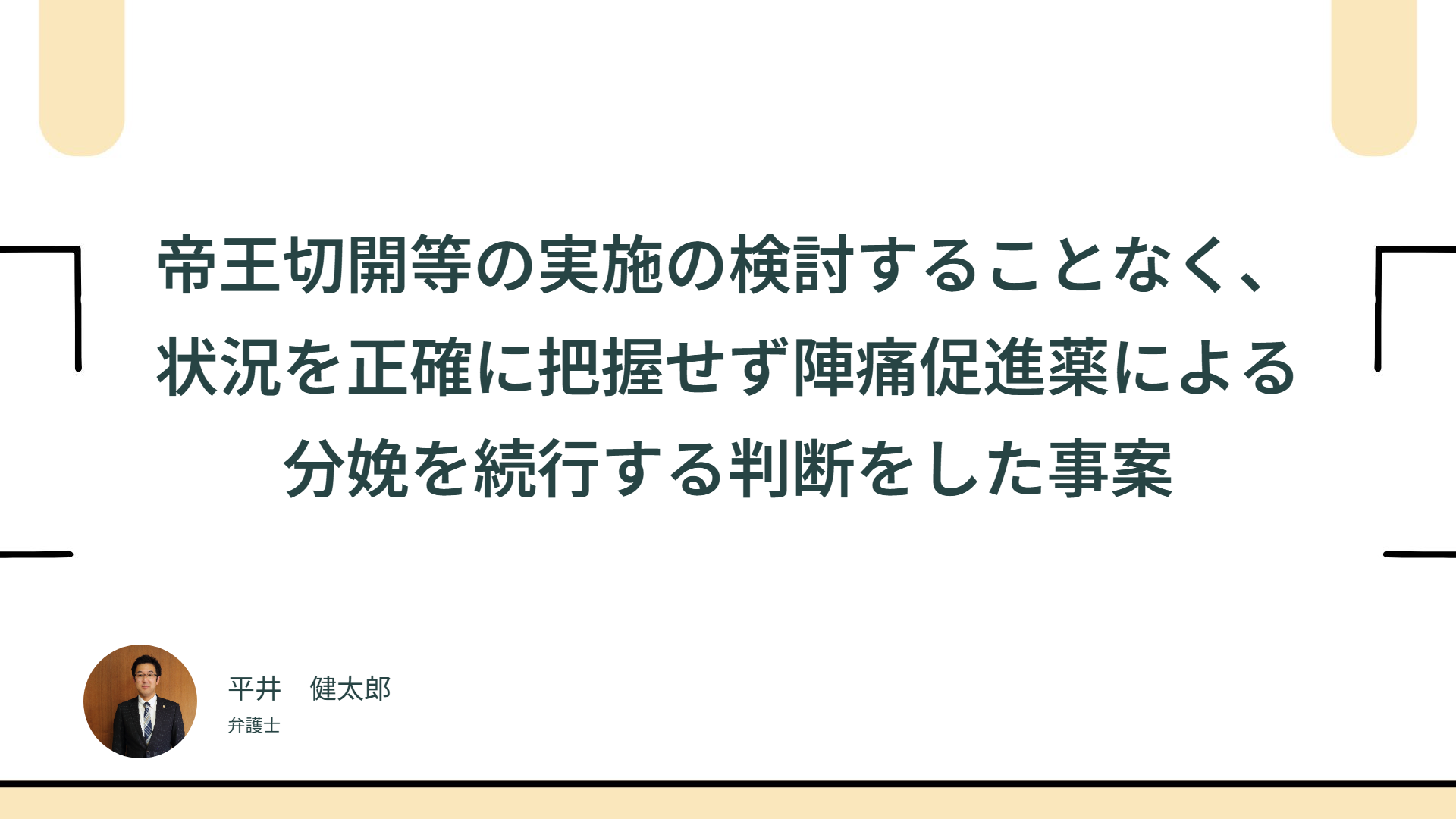
重症新生児仮死の状態で出生して重度の後遺障害を負った場合に、医師にクリステレル胎児圧出法又は帝王切開術を実施すべきか検討し、準備に着手し、実行すべき注意義務があるのにこれに違反したとされ、原因分析報告書の内容も評価され因果関係も認められた事案
(高知地裁平成28年12月9日、判時2332号71頁)
【争点】
- 監視の強化,保存的処置の施行及び原因検索を適切に行う義務を怠った過失
- 急速遂娩の準備及び実行をすべき義務を怠った過失
- 相当因果関係
- 原告X1の損害
- 原告X2及び原告X3の損害
【判旨+メモ】
胎児心拍数陣痛図に基づき、時間経過に沿って胎児に低酸素状態を評価し、どの時点で、「低酸素状態を原因とする脳性麻痺などの後遺障害が生じる」可能性を予見できたかが判断されている。
遅発一過性徐脈がある場合には,胎児が低酸素状態にあることが,基線細変動が減少している場合には,胎児の状態が悪化していることがそれぞれ推測されるところ,上記のとおり,原告X1の遅発一過性徐脈は一時的なものではなく,午後3時40分頃には高度遅発一過性徐脈が発生し,午後3時50分頃から,基線細変動の減少を伴う高度遅発一過性徐脈が複数回にわたり発生するようになっていたのであるから,Fにおいては,遅くとも午後4時40分頃に分娩室に入室した頃には,原告X1が低酸素状態にあり,その状態が悪化していることを認識することができたというべきである。そして,原告X1がその後直ちに娩出されるような状況にはなかったことからすれば,陣痛促進薬による経腟分娩をそのまま続行した場合には,上記の低酸素状態が更に増悪し,ひいては原告X1に低酸素状態を原因とする脳性麻痺などの後遺障害が生じることがあり得ることを予見することができたものというべきである。
ガイドラインに沿っていないことが直ちに過失とはならないとの反論は病院から出されることがあり、本件でも規範性がないとの反論がなされているが、ガイドラインの作成経緯も踏まえ判断が示されている。
代理人としては、ガイドライン違反が直ちに過失と判断されるとは限らないことに注意する必要があり、ガイドライン以外の立証も準備する必要がある。
ところで,被告は,本件ガイドラインについて,規範性を有するようなものではないと主張する。証拠(甲B1,B7,乙B1)によれば,本件ガイドラインの胎児心拍数波形に基づく対応について,「エビデンスが乏しい中での推奨であることを考慮して幅をもたせてあるのが特徴である。」との記載がある事実が認められるものの,本件ガイドラインには,●●●年時点での日本産科婦人科学会及び日本産婦人科医会でコンセンサスが得られた医学的知見が示されている事実も認められ,本件ガイドラインの胎児心拍数波形に基づく対応については,平成20年6月に公表された本件指針の推奨内容を踏襲したものであることからすれば(前記前提事実(3)),基線細変動の減少を伴う高度遅発一過性徐脈が生じている場合には,胎児が低酸素状態にあることが推測され,母体や胎児の置かれた状況如何によっては,その低酸素状態を原因とする脳性麻痺などの後遺障害の発生を回避するために執るべき措置として,急速遂娩を行うことを検討すべき義務が発生することはあり得るものというべきである。
本件では、産科医療補償制度原因分析委員会の回答書が証拠として提出されており、回答書においても基準からの逸脱と判断されている。
裁判において、原因分析報告書なども有力な証拠となり得るが、それだけで結論が出るとは考えず、文献や論文、意見書による立証も併せて準備することが重要である。
産科医療補償制度原因分析委員会の回答書(甲B4)においても,午後3時40分以降の胎児心拍数陣痛図は軽度から中等度の異常波形を示しており,分娩方法の見直しを行わず,陣痛促進薬の投与を継続し,経過観察したことは基準から逸脱していると判断されていることからすれば,Fには,遅くとも,午後4時40分過ぎの時点で,クリステレル又は帝王切開の実施すべきかを検討し,いずれかの準備に着手し,これを実行すべき注意義務があったというべきである。
因果関係についても認められているが、以下の3段階の立証が必要になる。
①後遺障害が分娩中に低酸素状態となり増悪化していったことによって生じたこと
②ある時点までに低酸素状態を解消できれば後遺障害は負わなかったこと
③病院の過失がなければ上記ある時点までに帝王切開等を行い低酸素状態を解消できたこと
過失が認められれば自動的に因果関係も認められるという関係にはなく、結果が発生した医学的機序から証明し、時間要素も意識して過失を構成し立証する必要がある。
前記前提事実(3)のとおり,脳に十分な酸素が供給されなくなると,脳に障害を来し,脳性麻痺となることがあり,上記(1)のとおり,原告X1は脳性麻痺と診断されていること,上記(1)アの事実に加え,別紙7のとおり,原告X1の心拍数の異常の程度が時間の経過につれて大きくなっていき,出生から1分後のアプガースコアは1点で,出生から5分後のアプガースコアは3点であったこと,胎児血のpH値が7より小さいと,母体の中で低酸素状態であった可能性があるところ(前記前提事実(3)),臍帯血のpH値は6.80であったこと(乙A1の17),産科医療補償制度の原因分析報告書(甲B1)においても,胎児の予備能を超えた子宮収縮の負荷が胎児の低酸素状態を引き起こし,これが持続し,徐々に悪化したことによって酸血症に至ったと考えられるとされていることからすれば,本件後遺障害は,分娩中に低酸素状態となり,これが増悪化していったことによって生じたものと推認することができる。
もっとも,別紙7のとおり,午後5時10分頃~午後6時頃は,原告X1の基線細変動は減少しているものの,消失しておらず,胎児心拍数も120~150拍/分台であった。そうすると,その頃は,本件後遺障害を負うような危機的な低酸素状態にあったとまではいえず,遅くとも午後6時頃までに原告X1の低酸素状態を解消することができれば,原告X1は本件後遺障害を負わなかったものと推認される。そして,Fが,午後4時40分頃にクリステレル又は帝王切開の準備に着手していれば,被告病院の急速遂娩を行う体制からすれば,遅くとも午後5時35分頃の時点で,原告X1の低酸素状態を解消することができたことになる。したがって,Fが午後4時40分頃の時点で,クリステレル又は帝王切開の実施の準備に着手していれば,原告X1が本件後遺障害を負わなかったものと推認されるから,Fの過失と原告X1に生じた本件後遺障害との間には相当因果関係がある。