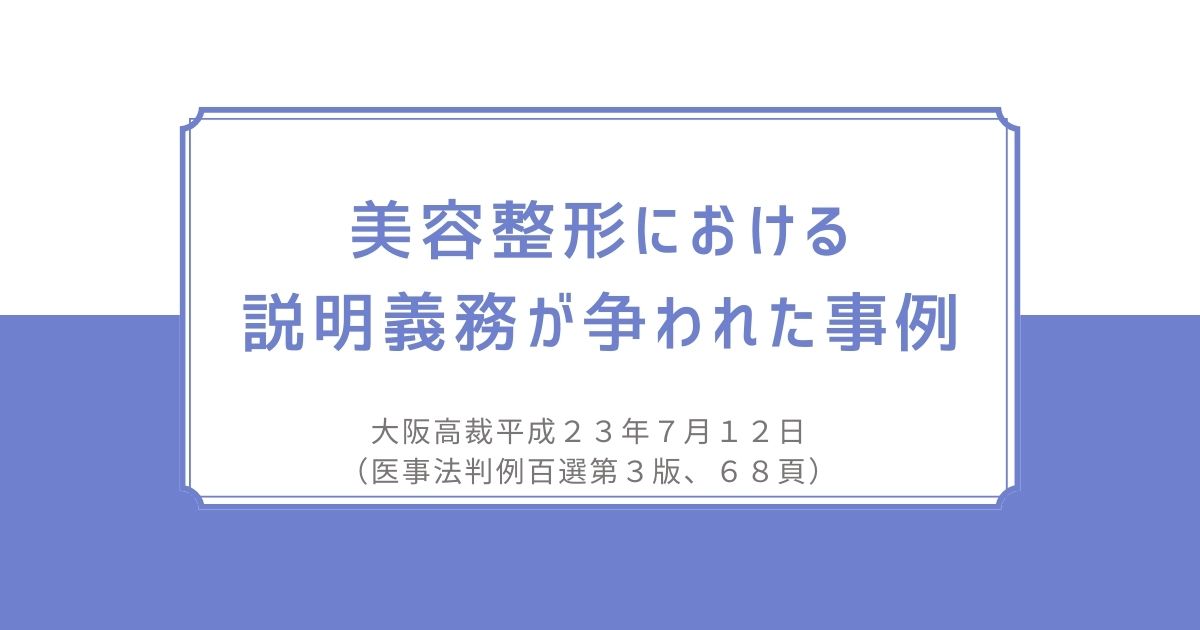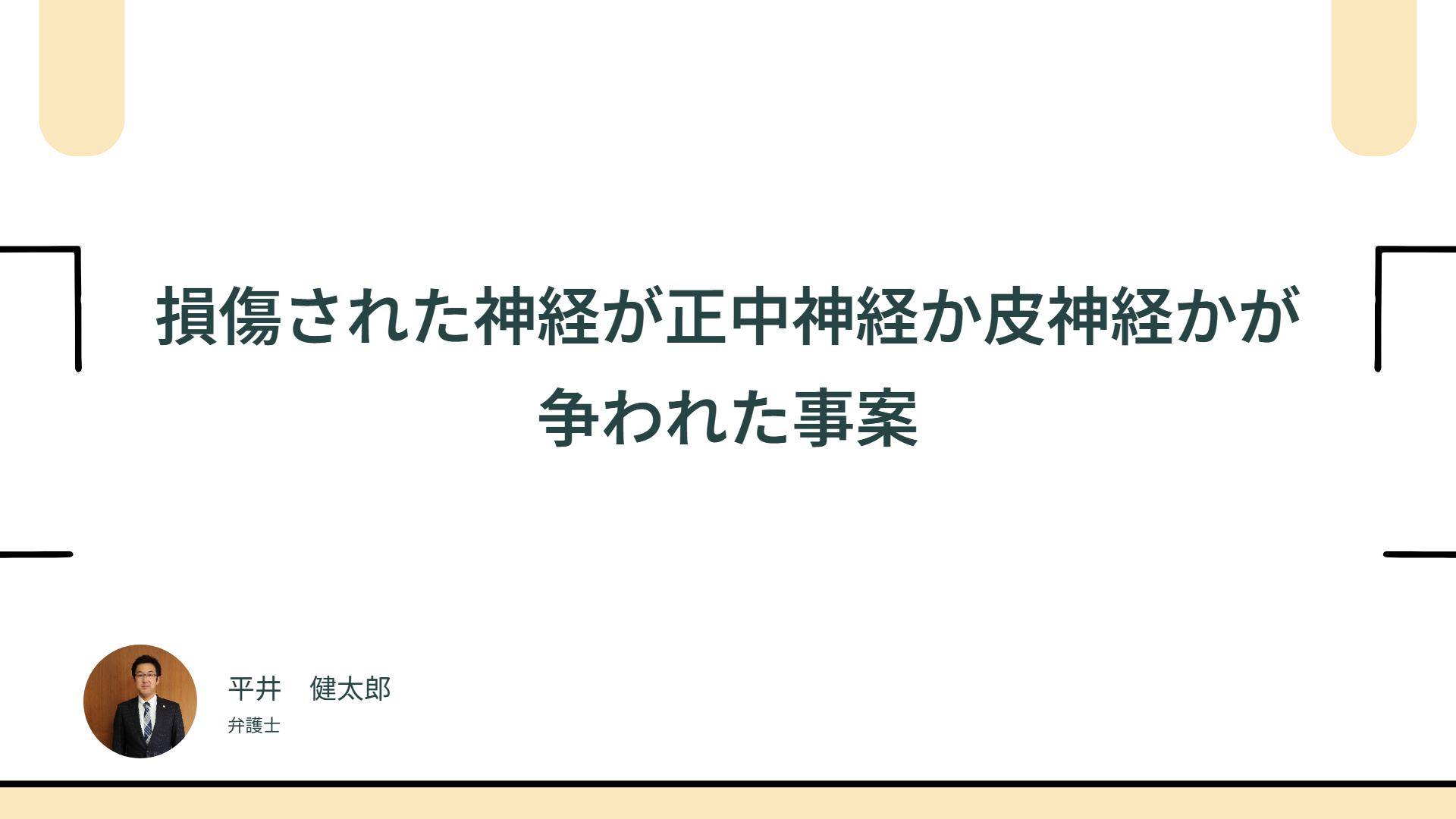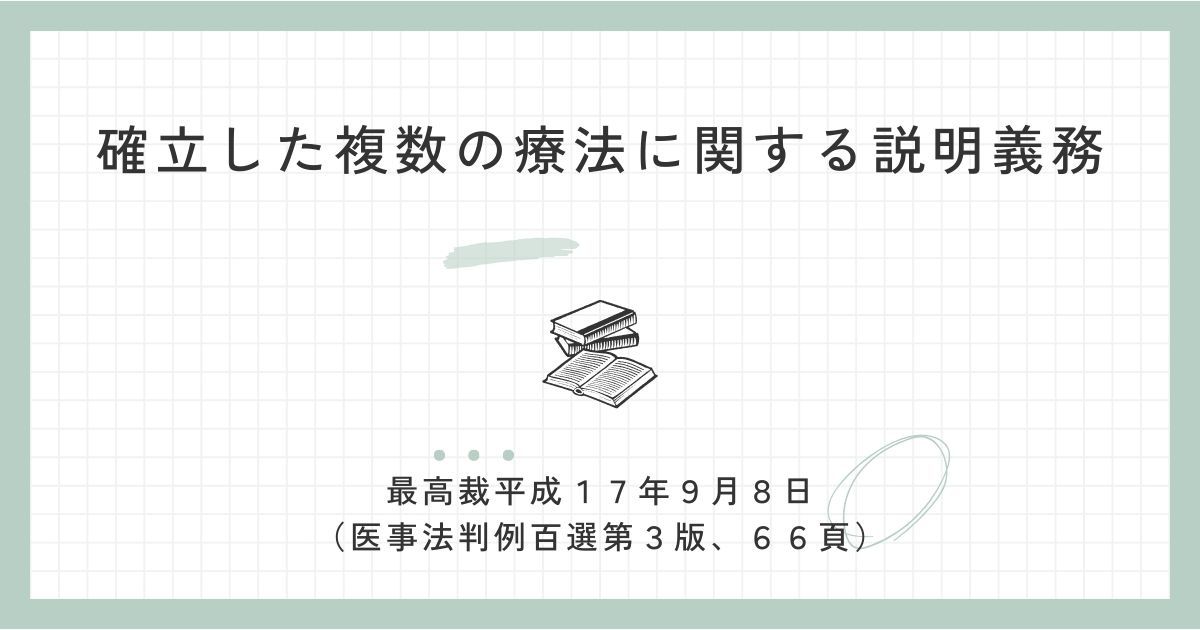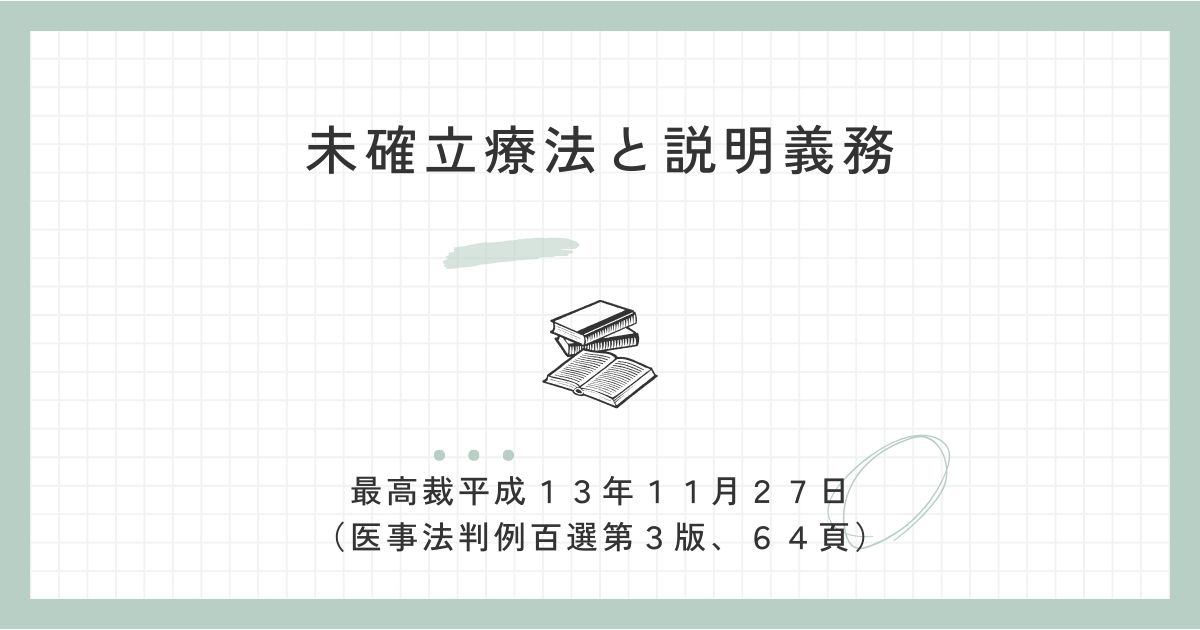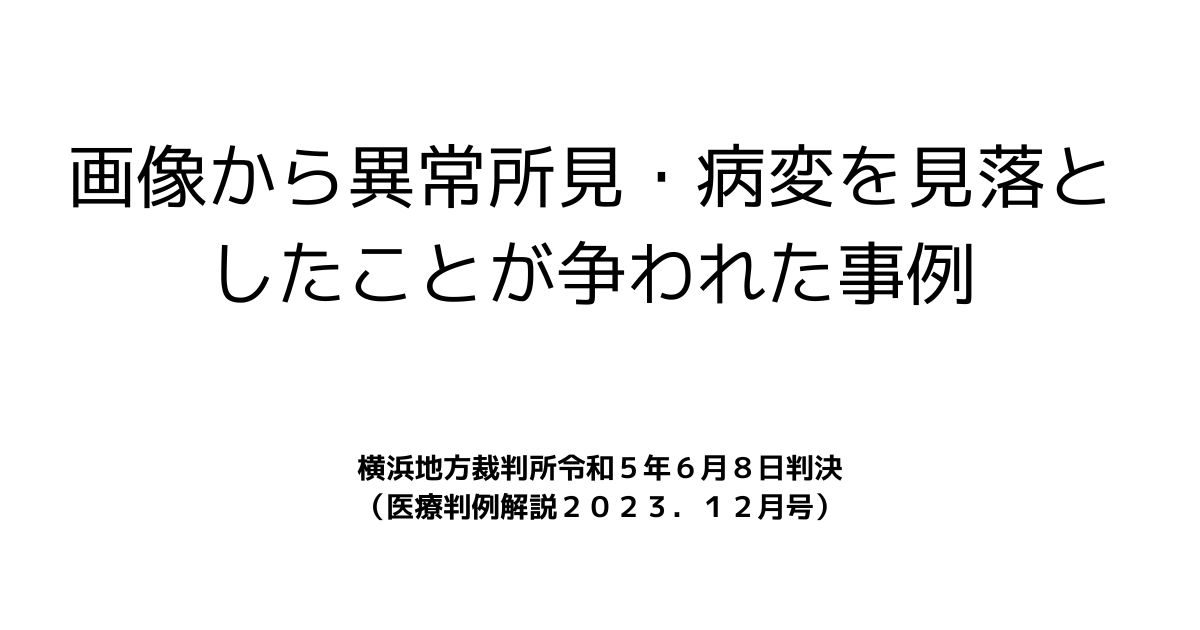静脈穿刺で強い痛みを訴えたのに中止せず神経を損傷したらどうなるか?
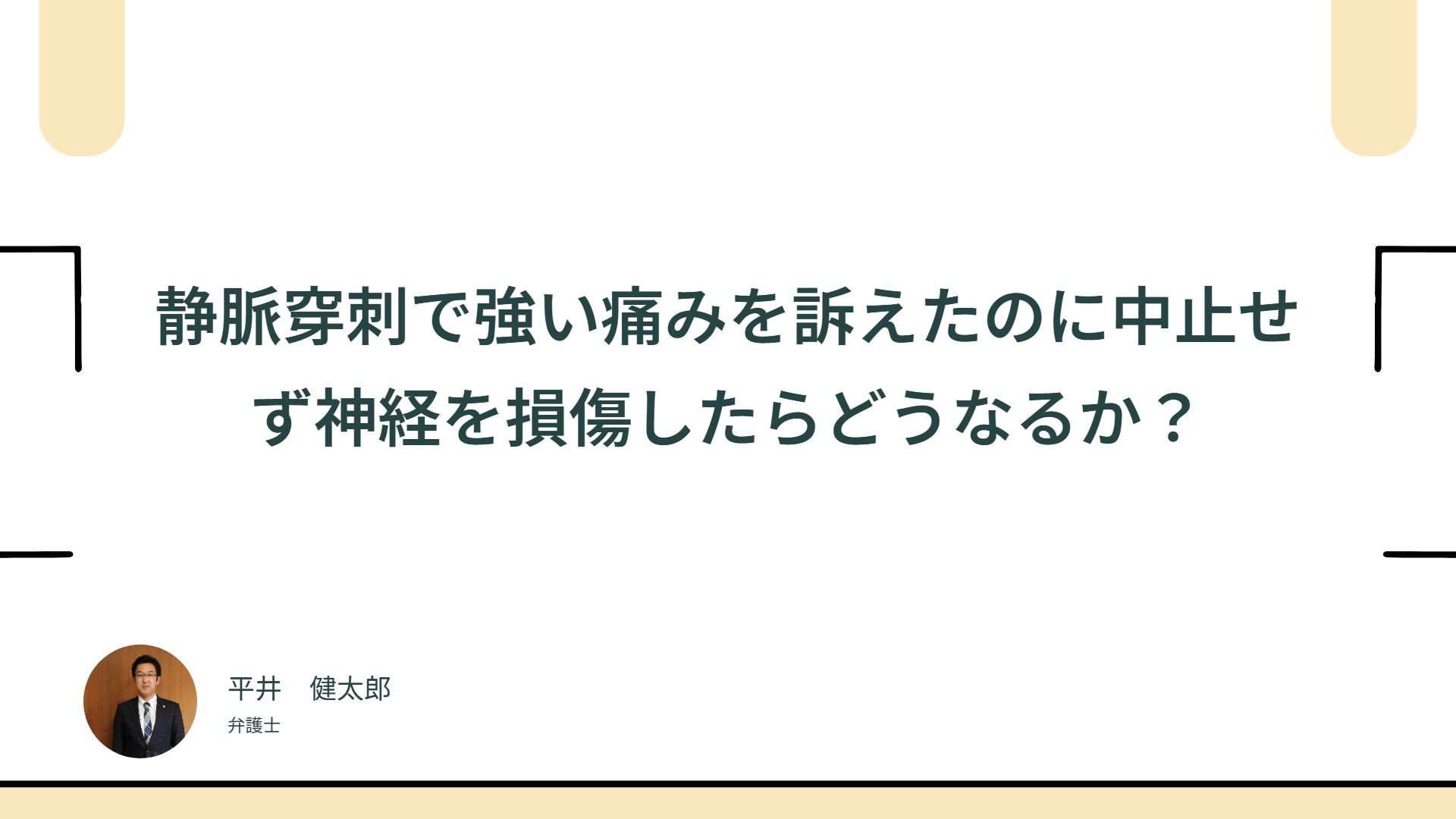
誤った静脈穿刺手技により右前腕の神経を損傷して後遺障害が生じたとして損害賠償を求め、主に後遺障害等級等が争われた(秋田地裁令和元年10月23日、医療判例解説87号39頁)
【争点】
- 後遺障害の程度(等級)について
- 入通院慰謝料の額
- 原告の基礎収入額について
- 休業損害について
- 後遺障害逸失利益等の算定について
【判旨+メモ】
被告は,本件穿刺をした研修医に,原告が痛みを訴えているにもかかわらず直ちに穿刺手技を中止しなかった過失があったこと,本件穿刺により原告が右前腕部尺骨神経損傷の傷害を負ったこと,被告が使用者責任を負うことを認めている。
本件では、病院側が過失を認めていたため、争点は損害論だけであった。
判決文によると、過失の内容は「原告が痛みを訴えているにもかかわらず直ちに穿刺手技を中止しなかった過失」である。
事実として「その際,初期研修医が静脈確保のため原告の右前腕尺側中ほどを穿刺した。穿刺された際,原告は強い痛みを訴えたが,当該初期研修医は手技を中止せず,原告が痛みを訴えた後も数秒間穿刺を続け,静脈を探った。原告がより激しい痛みを覚え,皮下血腫が増大したため,当該初期研修医は手技を中止した」と認められ、これが過失と評価されているので、強い痛みを訴えたにもかかわらず穿刺手技を中止しなかった場合には過失と評価され得るということだろう。
本件穿刺により,原告が右尺骨神経損傷の傷害を負ったこと(以下「本件受傷」という。)については当事者間に争いがないところ,この点は,本件穿刺直後から原告の右上肢の尺骨神経支配領域に痛みやしびれ,知覚鈍麻がみられ(認定事実(2)ア,イ),そのような症状は平成29年4月6日の診察時にも続いていたことが認められる(乙2)ことに照らし,医学的見地からも合理性があるということができる。
(中略)
これらの事実と尺骨神経損傷についての上記の医学的知見等に照らせば,右肩関節及び右肘関節の可動域制限については,医学的にみて,本来,安静が必要な状況下での右上肢の使用に起因するものであったり,心因性のものであったり,あるいはその両方によるものである可能性が高いというべきである。もとより,原告に右肩関節及び右肘関節の上記可動域制限が生ずることになった最初のきっかけが本件受傷にあること(事実的因果関係の存在)自体は否定されるものではないが,上記右肩関節及び右肘関節の可動域制限と本件穿刺との間に相当因果関係があると認めるのは困難である。したがって,本件受傷により,原告に右肩関節及び右肘関節に機能障害が残ったという原告の主張は,採用することができない。
この他にも右手関節及び右手指について検討を加え、原告のこういしょうがいは、手関節に頑固な神経症状を残すものとして後遺障害等級12級と判断されている(患者側は併合6級になると主張していた)。
労働能力喪失期間について,被告は,受傷から5年程度であると主張するが,本件受傷から3年近く経過している現時点において頑固な神経症状が残存していることに照らし,5年程度で労働能力を回復するとはにわかに認められず,ほかに労働能力喪失期間を短縮すべき特段の事情も認められないから,症状固定(平成31年)から67歳(令和16年)までの15年間の労働能力喪失を認めるのが相当である。
後遺障害が残っている場合でも労働能力喪失期間が争われることがある。被告が主張する5年になれば、10年分の労働能力喪失が認められない結果となるため、患者側からすると賠償額が低額になる。
本件では、裁判をしている現時点の症状を踏まえ、あと2年で回復するとは考えられないことから、労働能力喪失期間の短縮を認めなかった(患者側の主張のまま認められた)。