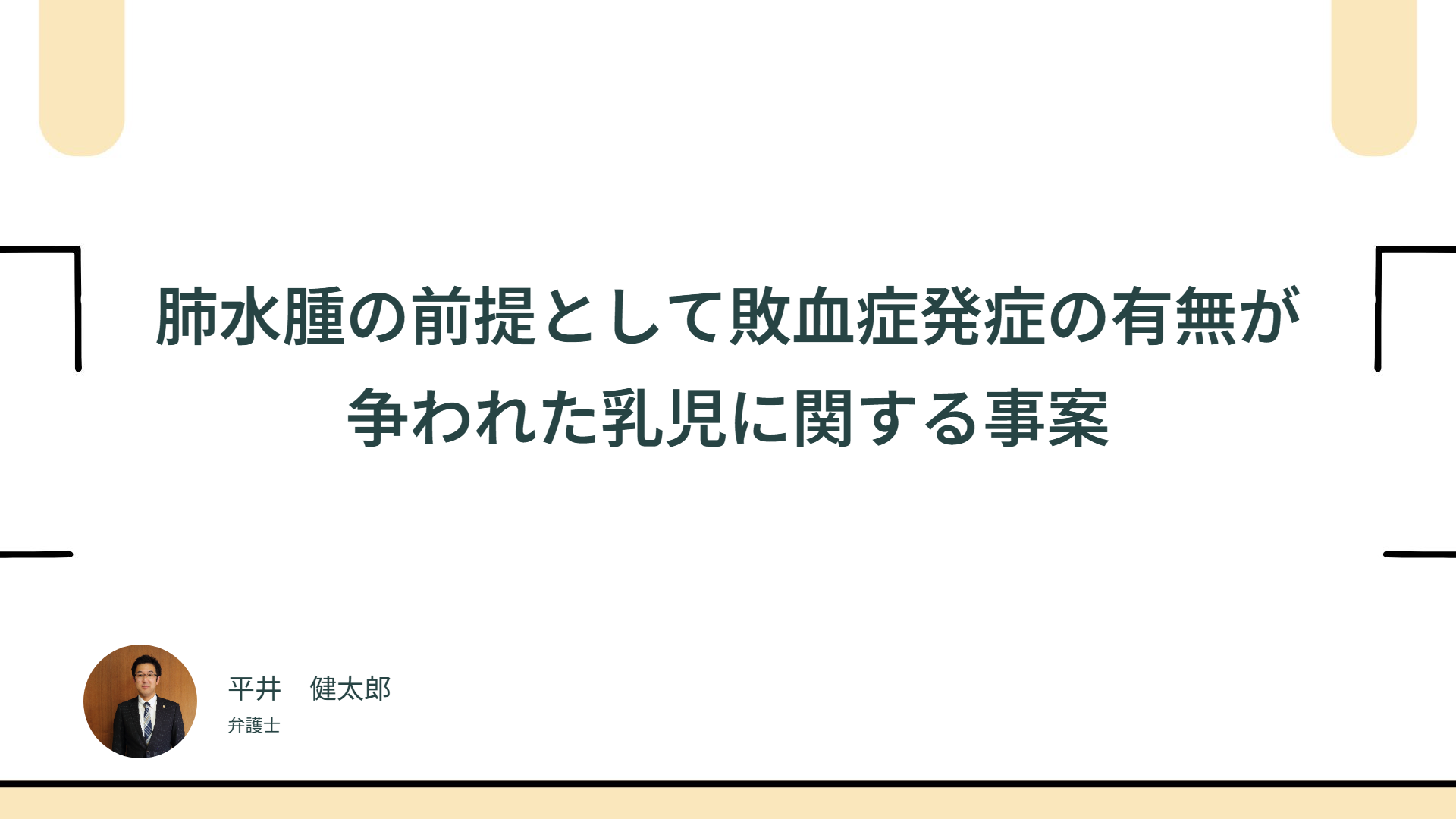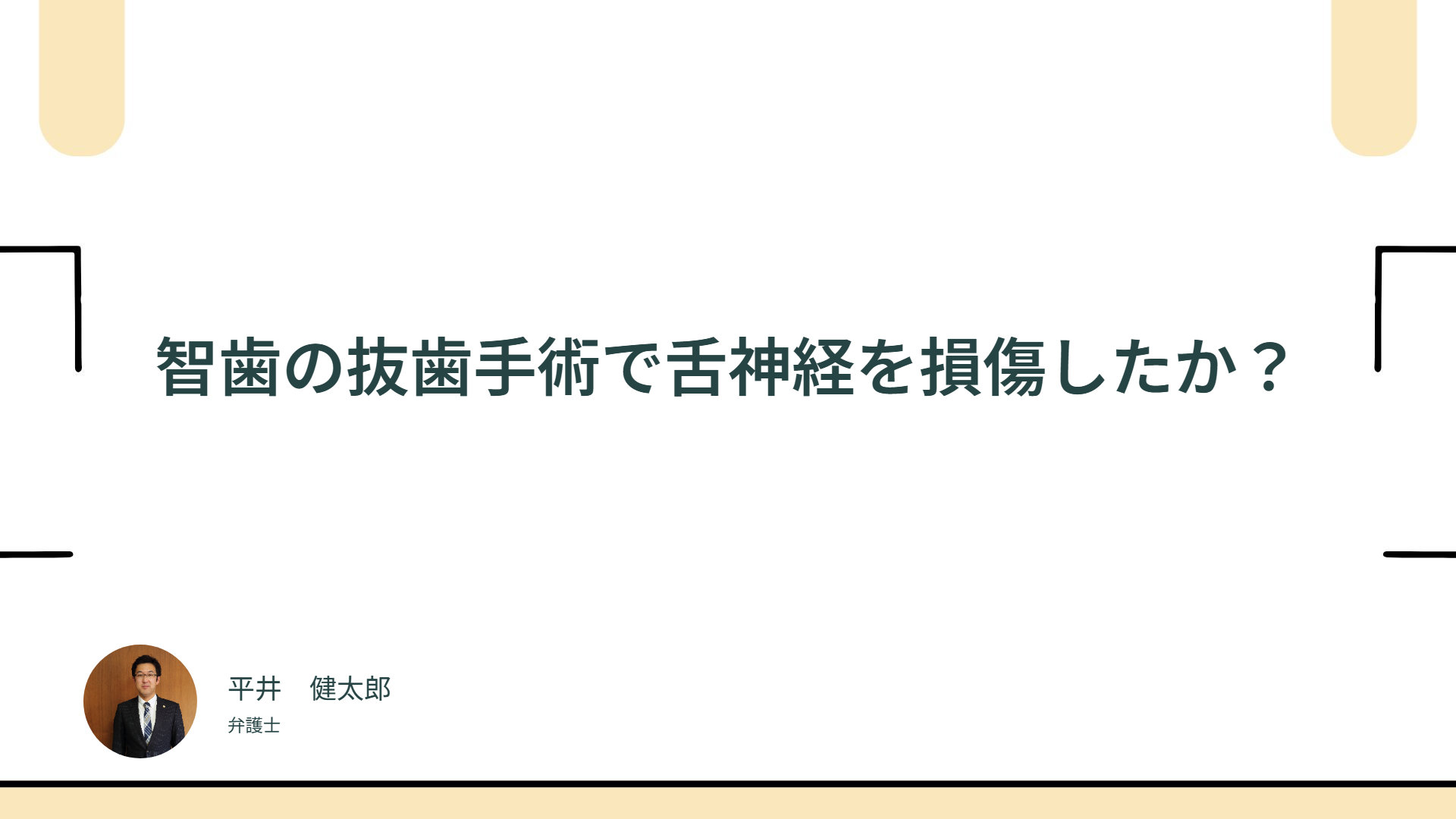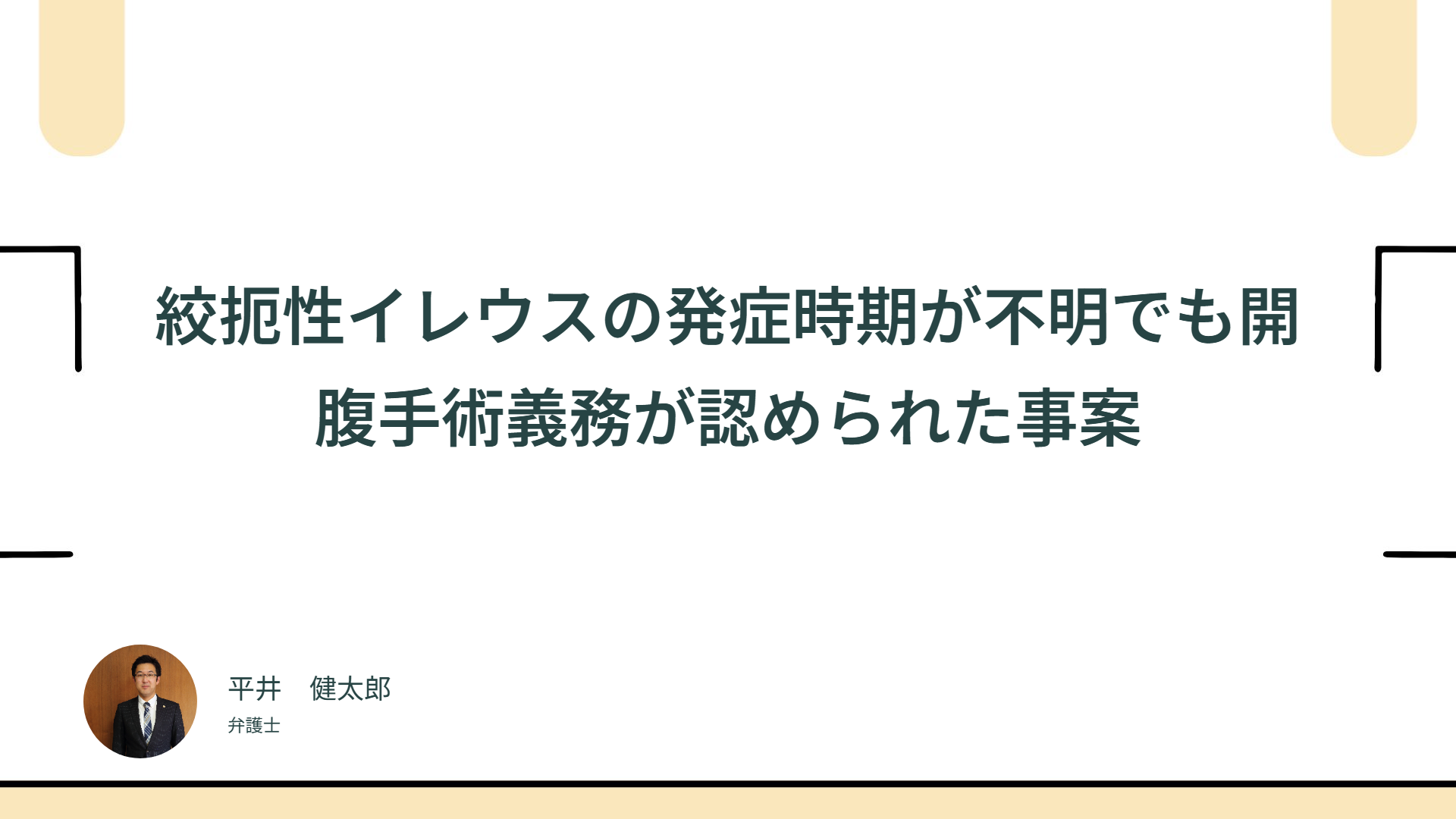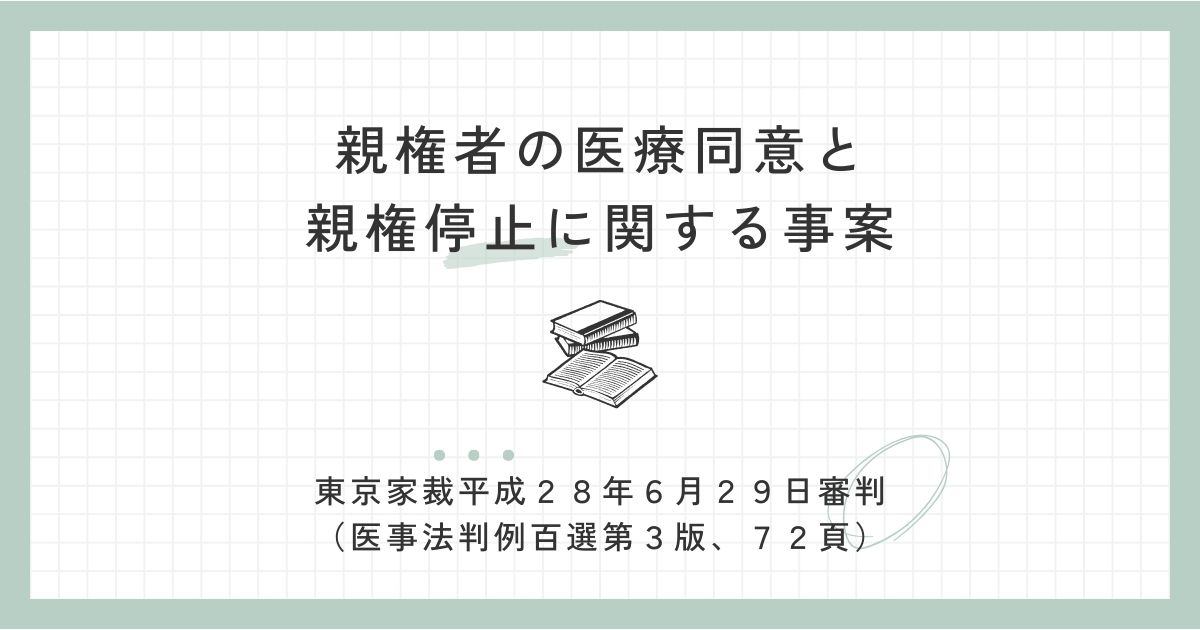過度な吸引行為と後遺障害との間に相当程度の可能性が認められた事案
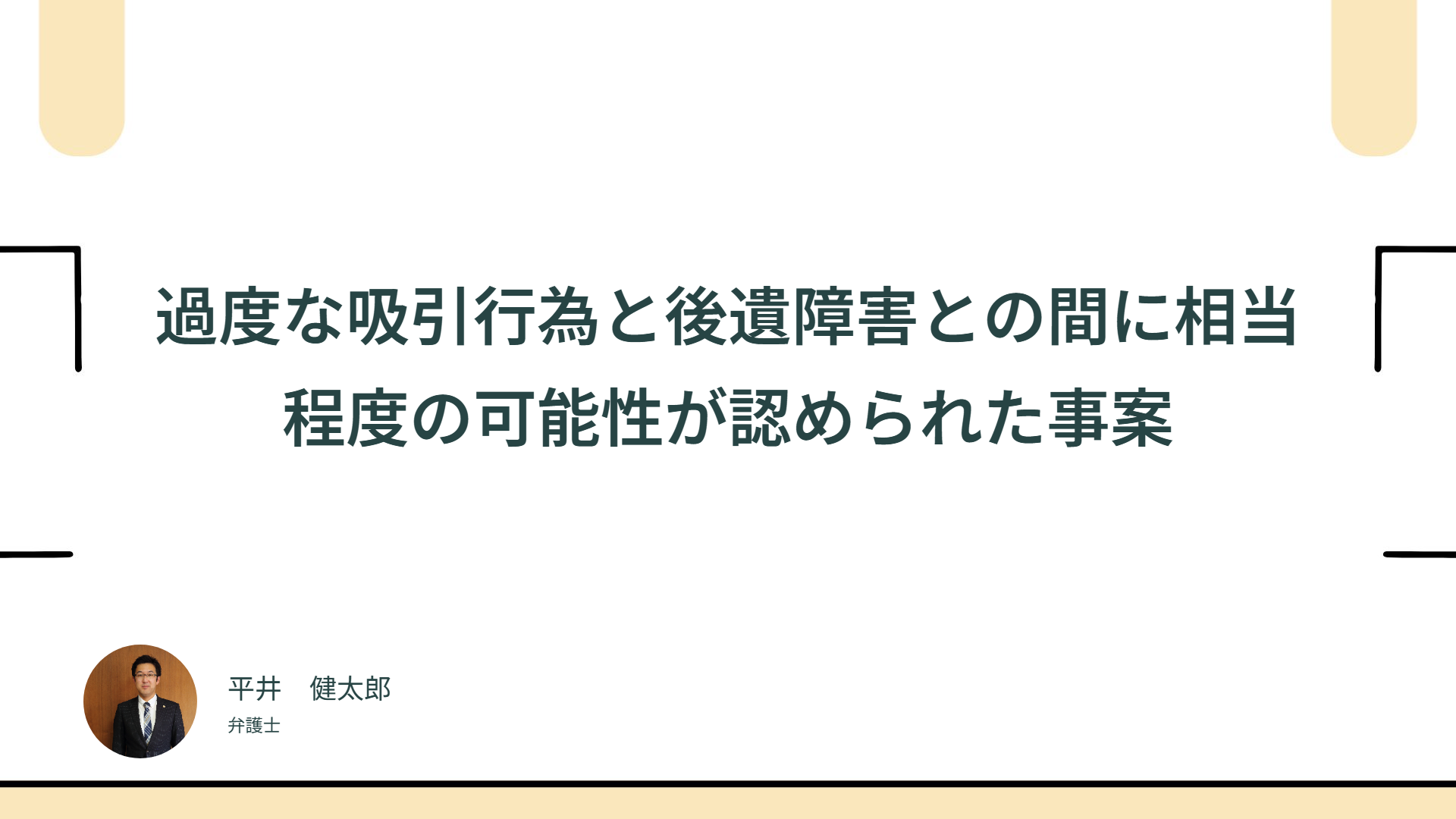
過度な吸引分娩の手技について過失が認めらたが、脳性麻痺との関係で高度の蓋然性は認められず、相当程度の可能性が認められた事案
(大阪高裁令和2年3月26日判決、原審大阪地裁平成30年2月13日判決)
【争点】
- 実施された吸引分娩の時間及び回数
- 適応のない吸引分娩を実施した注意義務違反があったか
- 過度に吸引分娩を実施した注意義務違反があったか
- 本件分娩における吸引により脳性麻痺が生じたか
【判旨+メモ】
高裁の判決では、主に①と④について判断が詳しく示されており、過失については争点③の過度に吸引分娩を実施した注意義務違反が認められている。
争点④本件分娩における吸引により脳性麻痺が生じたかについては、以下のように結論が示されている。
以上の諸事情を総合すると,一般に,脳性麻痺には多くの要因の関与があり,満産期の児の脳性麻痺で低酸素虚血が原因となるものは10%より低いとの文献もあること,産科医療補償制度における脳性麻痺の原因分析の中で,原因不明ないし特定困難とされたものが相当数を占める一方で,帽状腱膜下血腫が原因とされたものの件数は極めて少ないこと,Aの帽状腱膜下血腫が重度であると認めるに足りる証拠はなく,直接診断に当たった医師が仮死と血腫は並列に発症したと考えるのが妥当であるとの意見を述べたこと,出生前のPVLという概念があり,AにはPVLに向かう異常所見があったことなどの事情からすれば,Aの脳性麻痺が先天性の疾患等の他原因による可能性は大いにあるといわざるを得ない。したがって,帽状腱膜下血腫が脳性麻痺を生じさせた高度の蓋然性があるとは認められない
他方,産科医療補償制度において帽状腱膜下血腫による出血性ショックにより脳性麻痺を起こしたと分析された事例はあり,Aの帽状腱膜下血腫につき広範囲な血腫が認められ,輸血が実施されている。そして,何より,前記1で認定したとおり,本件分娩において○月○日22時30分頃から23時10分頃までの間に3回,同月○日0時30分から0時54分までに少なくとも10回の吸引行為が行われ,同時間帯に少なくとも7から8回の吸引行為(滑脱),すなわち,滑脱を含め,少なくとも2時間半近い長時間に20から21回という多数回の吸引行為がされており,前記3で判断したとおり,これは,平成23年ガイドラインを大きく逸脱して新生児合併症のリスクを上昇させる危険性の高いものであった。これらを踏まえると,帽状腱膜下血腫により脳性麻痺が生じたという可能性が相当程度あることは否定することができない。
本判決は、「脳性麻痺が先天性の疾患等の他原因による可能性は大いにあるといわざるを得ない」ことを理由に、高度の蓋然性を認めなかった。
他方、「平成23年ガイドラインを大きく逸脱」していることに重きを置いて、当該逸脱が「新生児合併症のリスクを上昇させる危険性の高い」行為であったことを指摘していることから、過失の程度も考慮して、「帽状腱膜下血腫により脳性麻痺が生じたという可能性が相当程度あることは否定することができない」としたのではないかと思われる。
そうすると、ガイドライン逸脱の程度が小さければ、その分リスク上昇の程度も低くなると考えられるため、それが因果関係の判断に影響すると思われる。