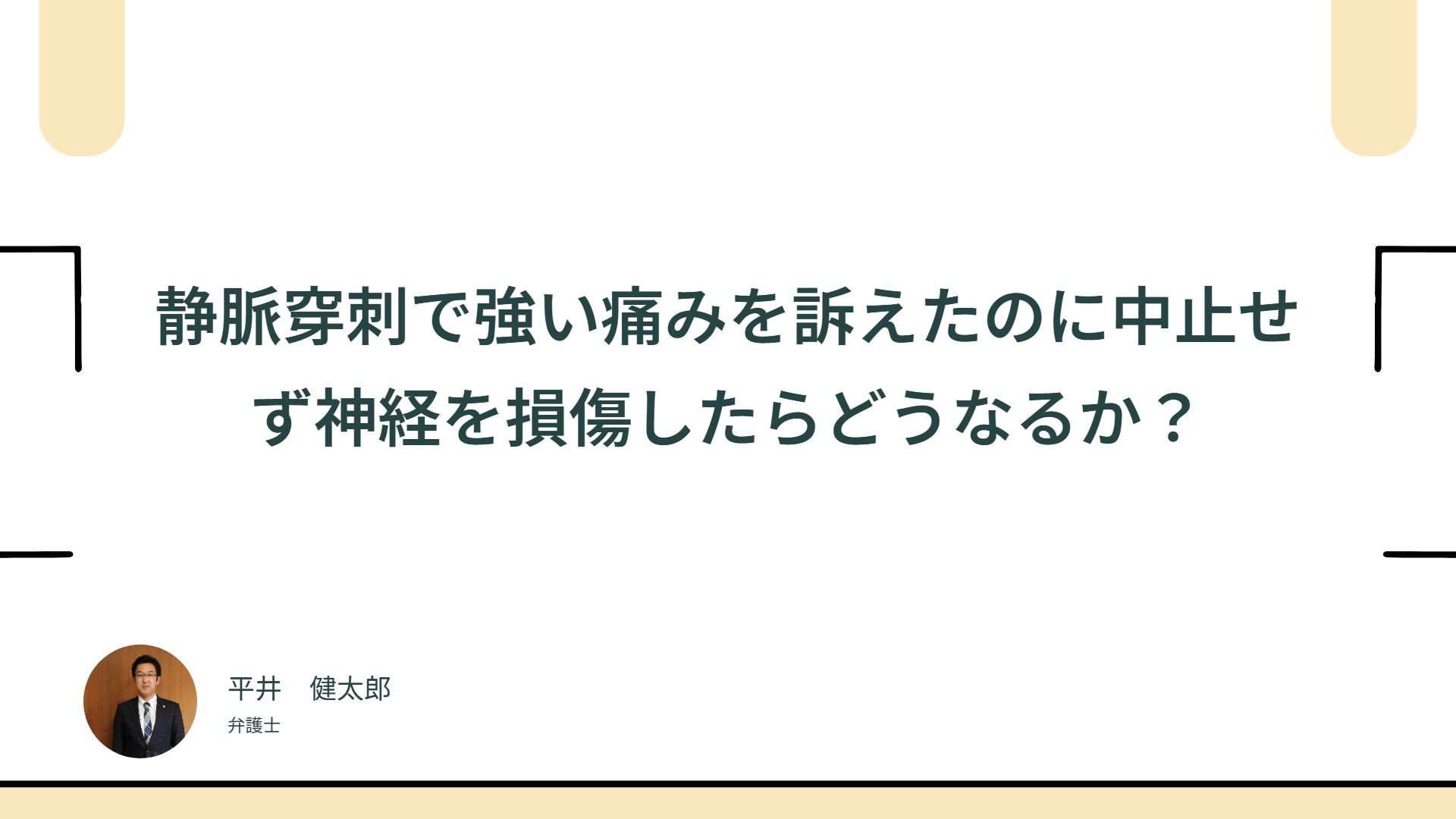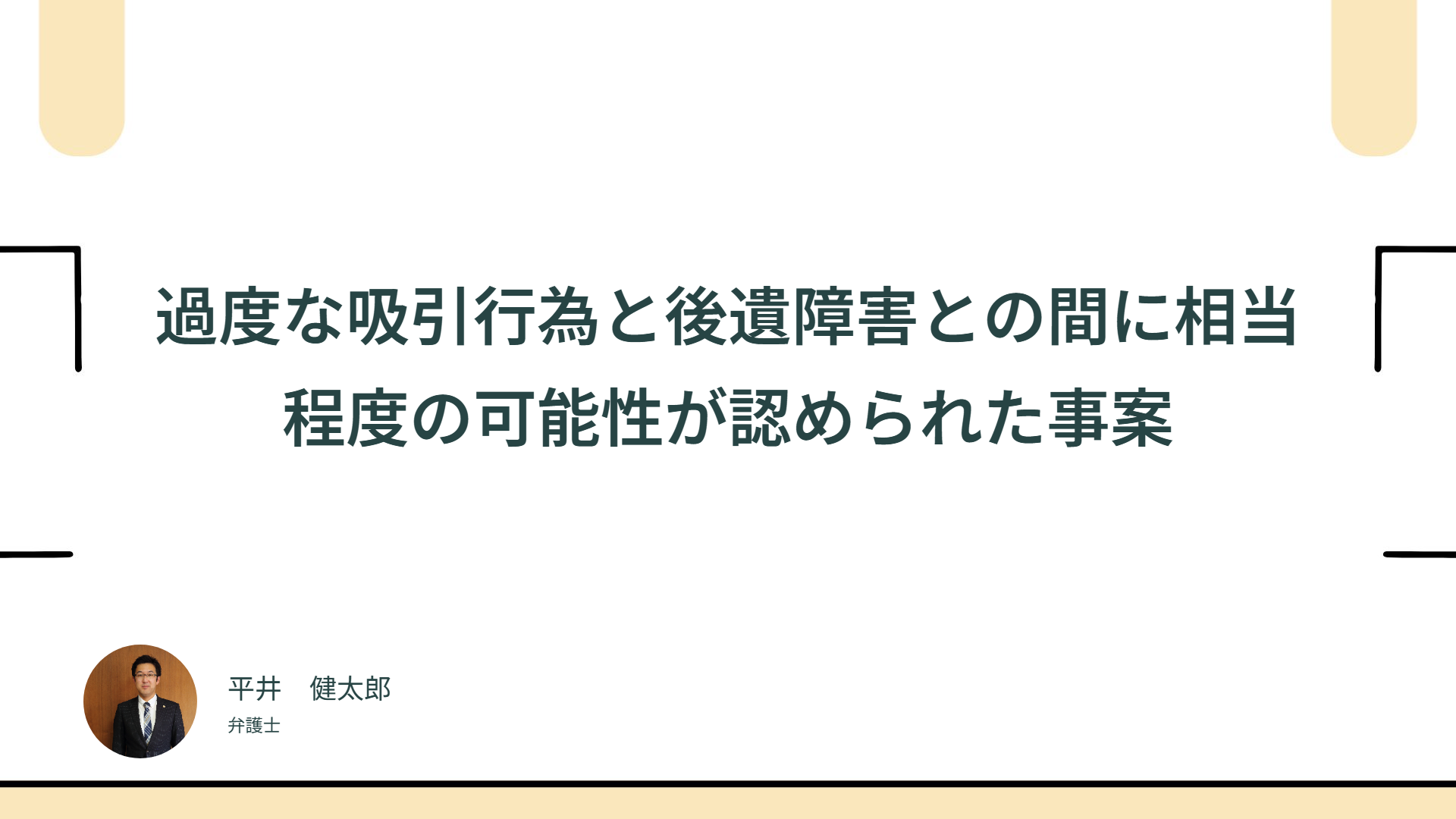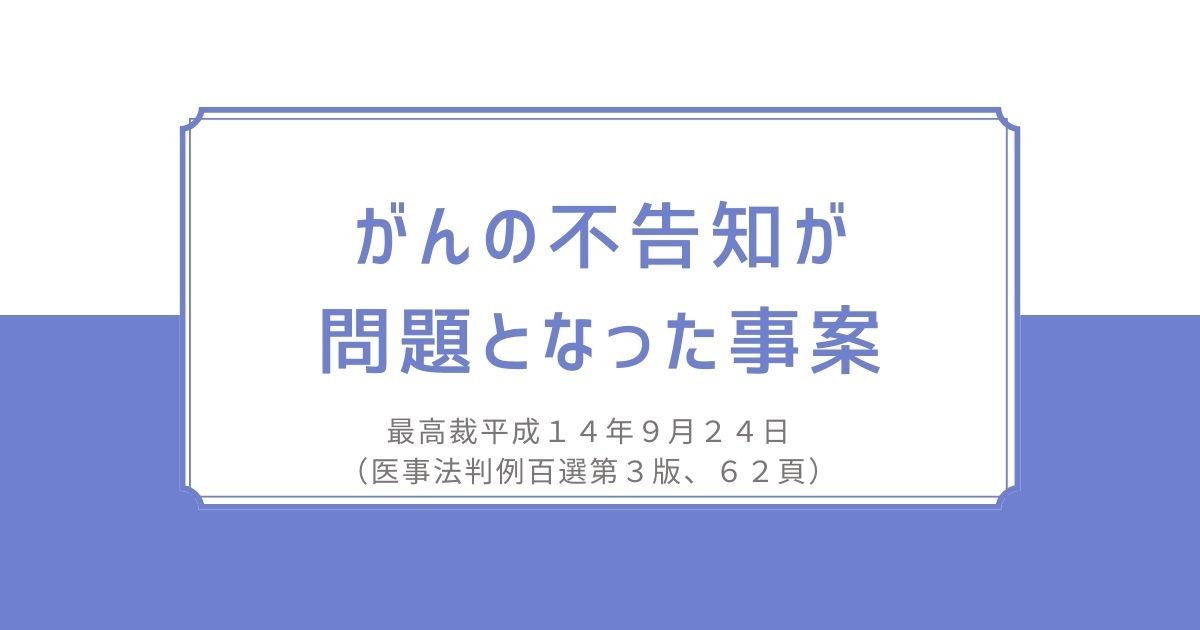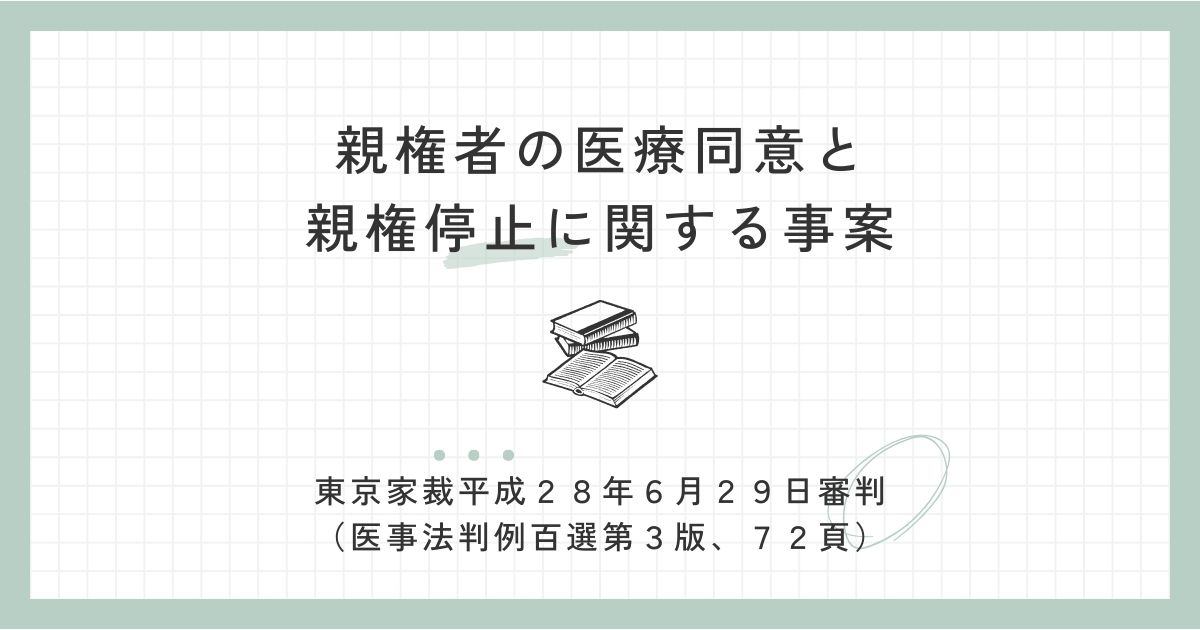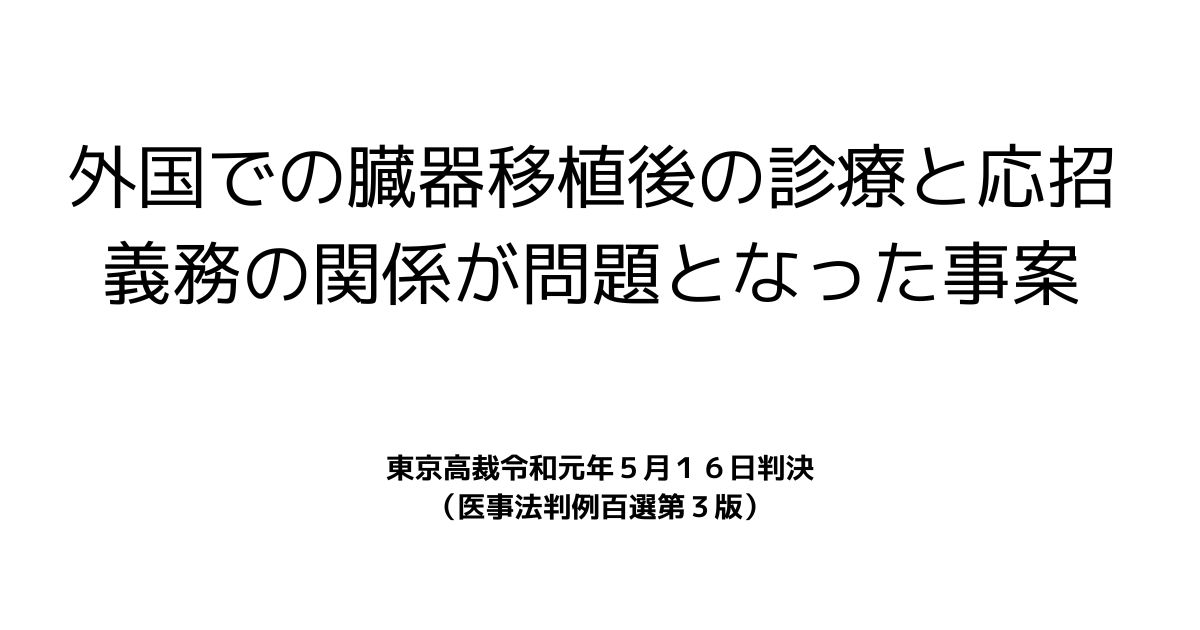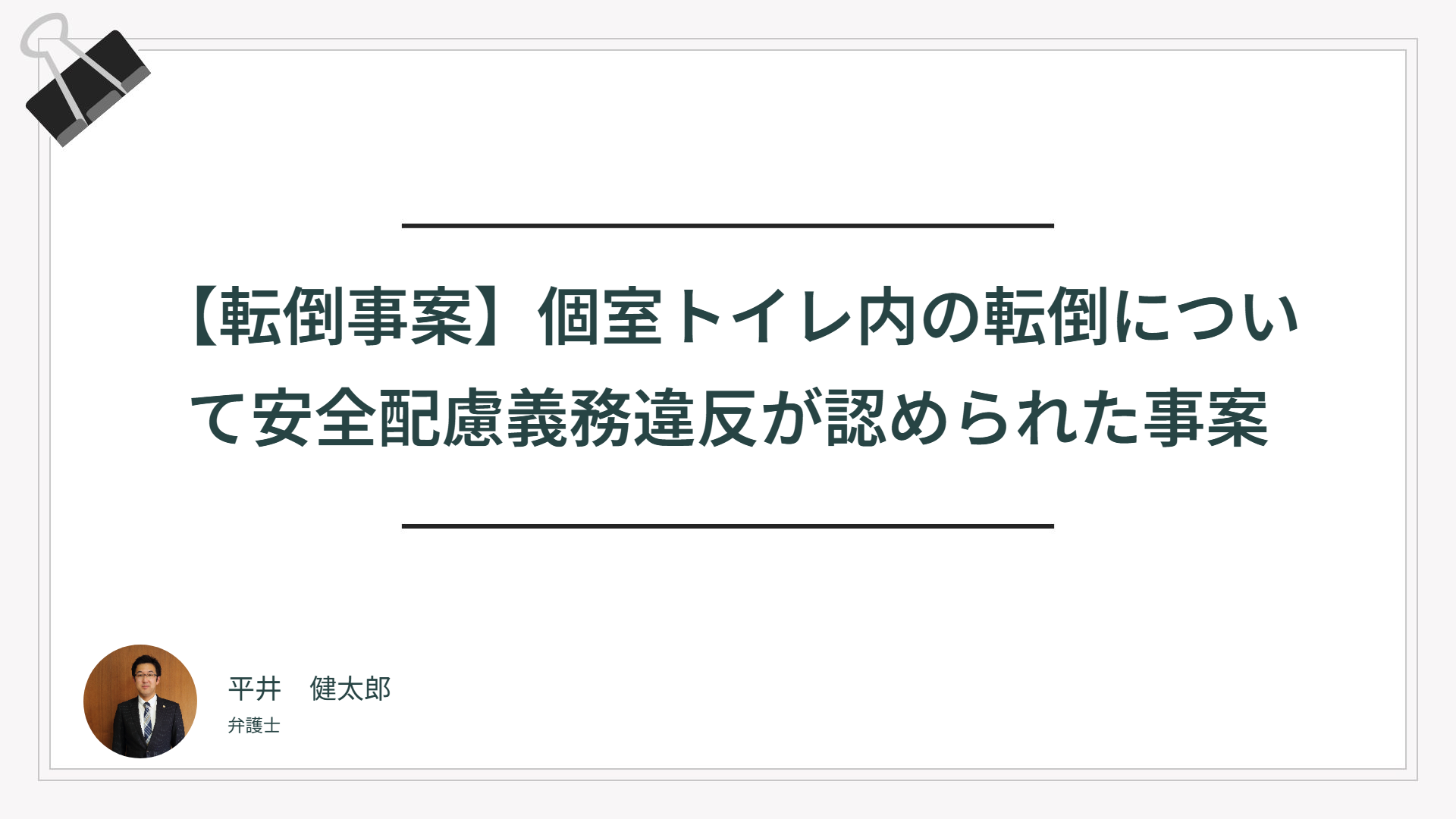二次性頭痛を疑い除外できていないとして検査義務違反が認められた事案
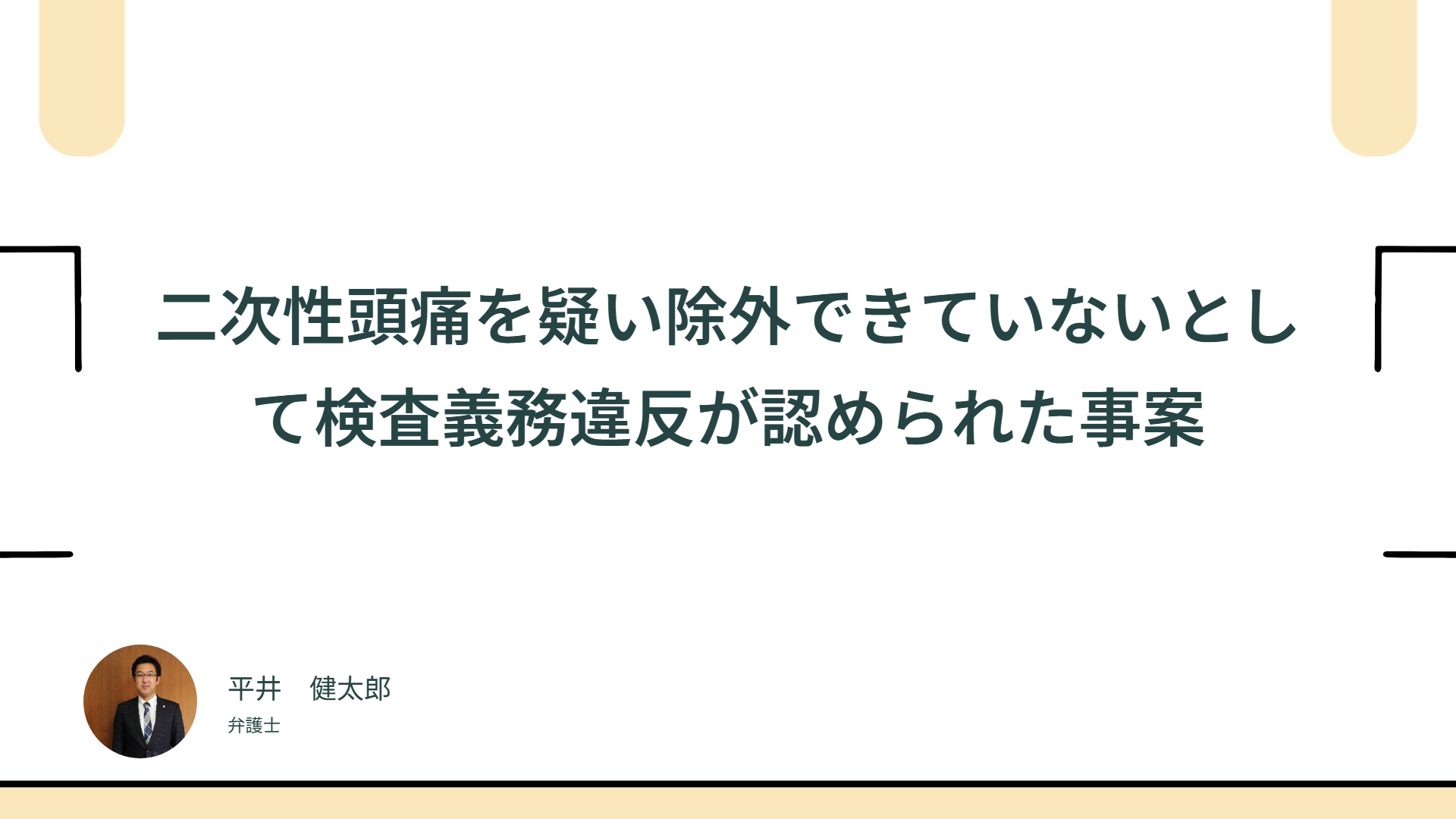
吐き気や頭痛で救急外来を受診した際に緊張性頭痛と診断され、後日にも頭痛の症状で救急車で搬送された際には一次性頭痛と診断されたが、その後に意識障害の症状を呈して救急車で搬送されたときにはCT検査で慢性硬膜下血腫及び脳梗塞と診断され、手術をしたが高度意識障害、四肢麻痺が残存した事案
(大津地裁令和7年1月17日判決、医療判例解説118号38頁)
【争点】
- 被告医師らに遅くとも4月30日午前9時頃までに、CT検査をして脳神経外科医師に相談すべき注意義務があったか
- 注意義務と後遺障害との因果関係
- 損害
【判旨+メモ】
慢性頭痛の診療ガイドライン2013や頭痛レッドフラッグ(red flag)の医学的知見に基づき、以下のとおり、二次性頭痛を疑い画像検査をすべきだったこと、二次性頭痛を除外できていたとは認められないと判断されている。
亡花子の症状が二次性頭痛を疑うべき診療ガイドラインにおける9項目のうち、①突然の頭痛、②今まで経験したことがない頭痛、③いつもと様子の異なる頭痛、④頻度と程度が増していく頭痛、⑤50歳以降に初発の頭痛に該当することを認識していた。
加えて、A医師は患者診療録(O:客観的情報)の欄に、「頭痛red flag」という二次性頭痛かもしれない危険な頭痛を示す記載をしており、このことからも、二次性頭痛の除外として診察やCT検査をしなければならない状態にあることを認識していたと考えられる。
A医師は、上記のとおり認識したものの、神経学的所見がないこと、急な発症でないことから、くも膜下出血は疑いにくく、体動で緩和することから緊張型頭痛と診断し、CT検査はしなかったが、二次性頭痛の原因はくも膜下出血に限られないのであり、くも膜下出血が疑われる場合でなくても、二次性頭痛が疑われる場合は、画像検査(特にCT検査)を実施し、原因を明らかにすべきであったと考えられる。(中略)
加えて、二次性頭痛は必ずしも神経学的所見を伴うわけではないから、神経学的所見が乏しかったことをもって二次性頭痛を除外することもできないといえる。したがって、B医師が二次性頭痛を除外できていたとは認められない。
因果関係については、慢性硬膜下血腫に関する医学的知見を基本に、三段階で高度の蓋然性を認めている。
慢性硬膜下血腫に関する医学的知見によれば、頭蓋内圧亢進が長時間持続し、脳ヘルニアを生じて、脳に不可逆的な損傷が起こってしまったりした場合を除き、予後は極めて良好であり、そのような不可逆的な損傷が生じる前であれば、穿頭術により流動性血腫を除去後、血腫腔を生理食塩水で洗浄した後、血腫腔にドレーンを1日留置することにより症状は劇的に改善するとされる。
(中略)
4月30日にB医師が診察した時点では、脳ヘルニアの直前の段階であるもののいまだ脳ヘルニアを生じていなかったことが窺える。
(中略)
亡花子が同時点で頭痛及び歩行困難という症状を有し、ワーファリンを内服しており、凝固障害があったことを考慮すると、CT検査後に脳神経外科医に相談していれば、緊急手術が行われた蓋然性が高いと認められる。
(中略)
亡花子(当時77歳)が脳ヘルニアの状態には至っていない4月30日段階で、CT検査及び手術を実施していれば、脳ヘルニア、脳梗塞及び脳梗塞より生じる後遺障害を回避することができた高度の蓋然性があると認めるのが相当である。
因果関係の判断では
①脳ヘルニアを生じていないこと
②緊急手術が行われた蓋然性が高いこと
③手術をしていれば後遺障害を回避できた高度の蓋然性があること
これらすべてを立証しなければならず、本件では認められているが、不作為事案は仮定の話になるため分析的思考と丁寧な立証が求められる。