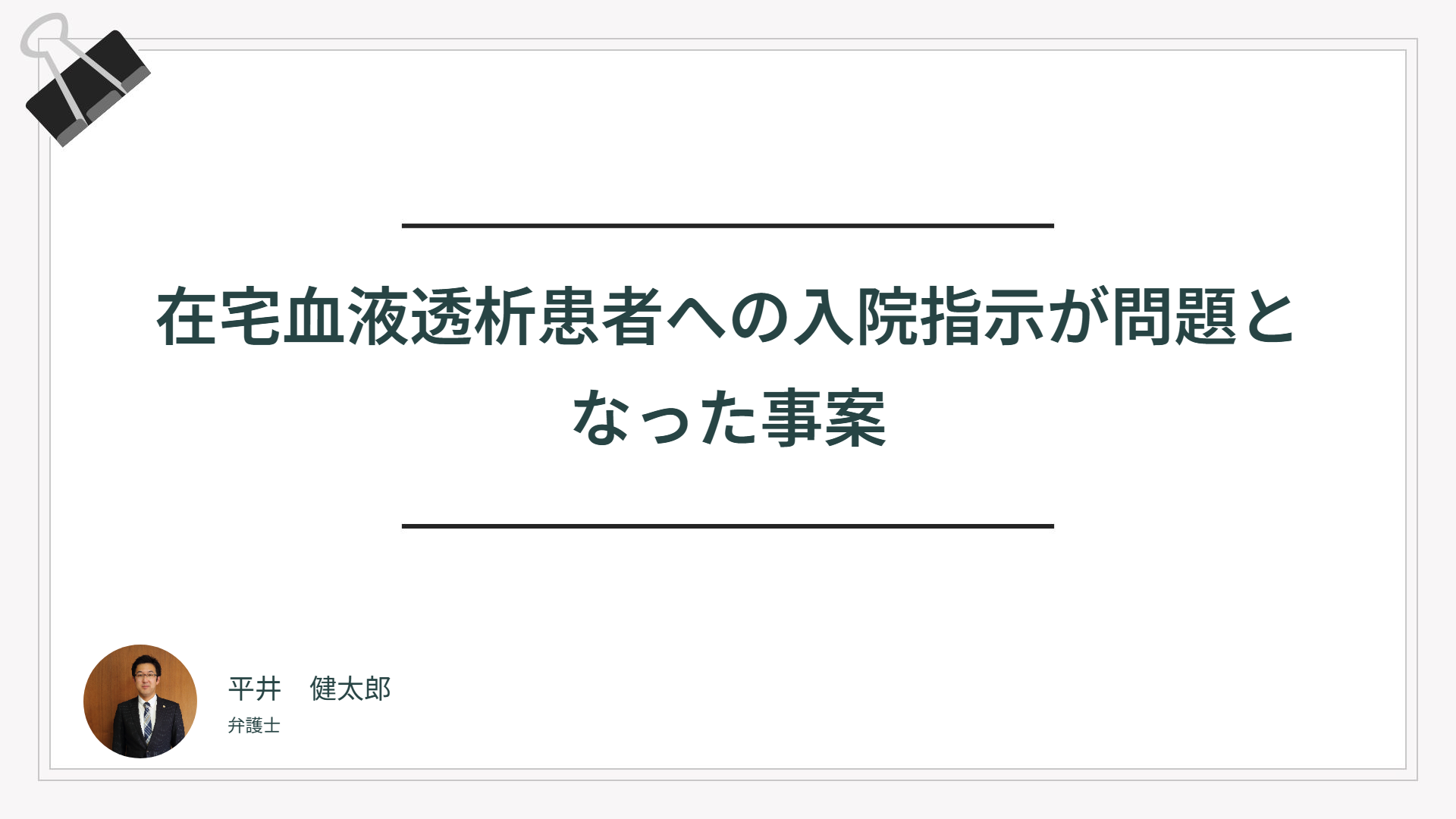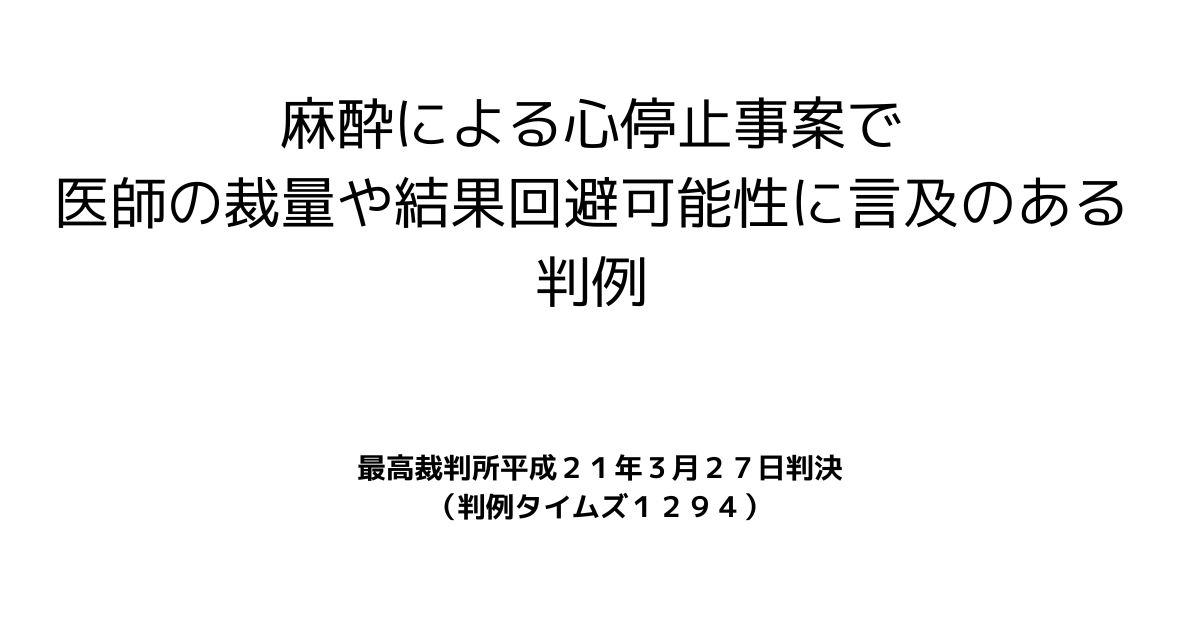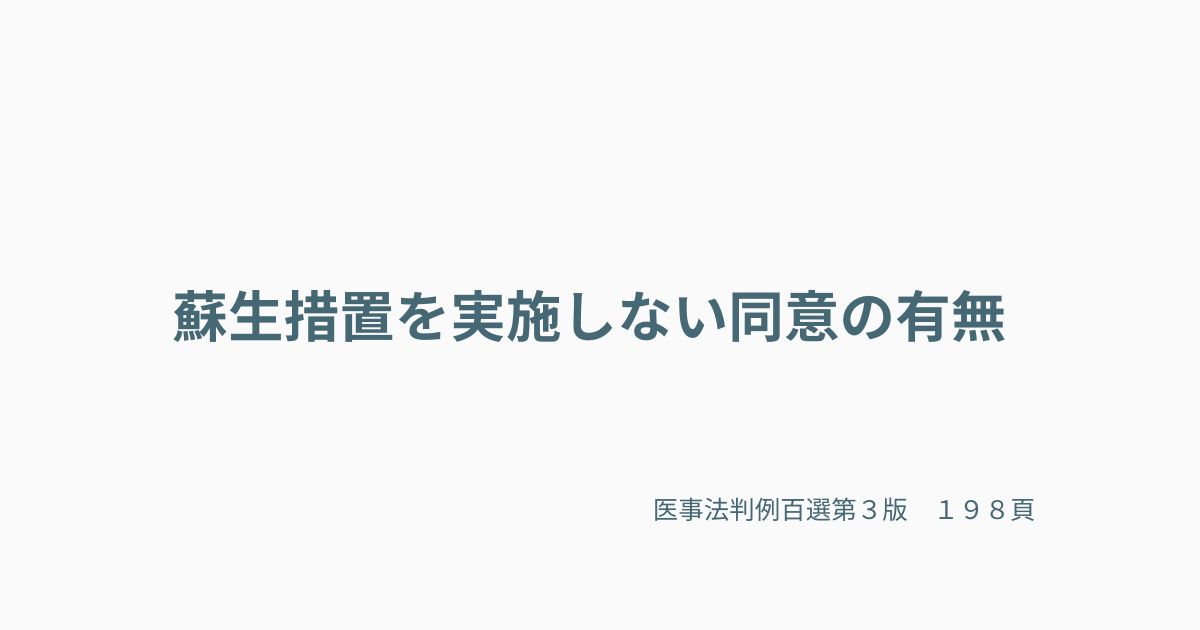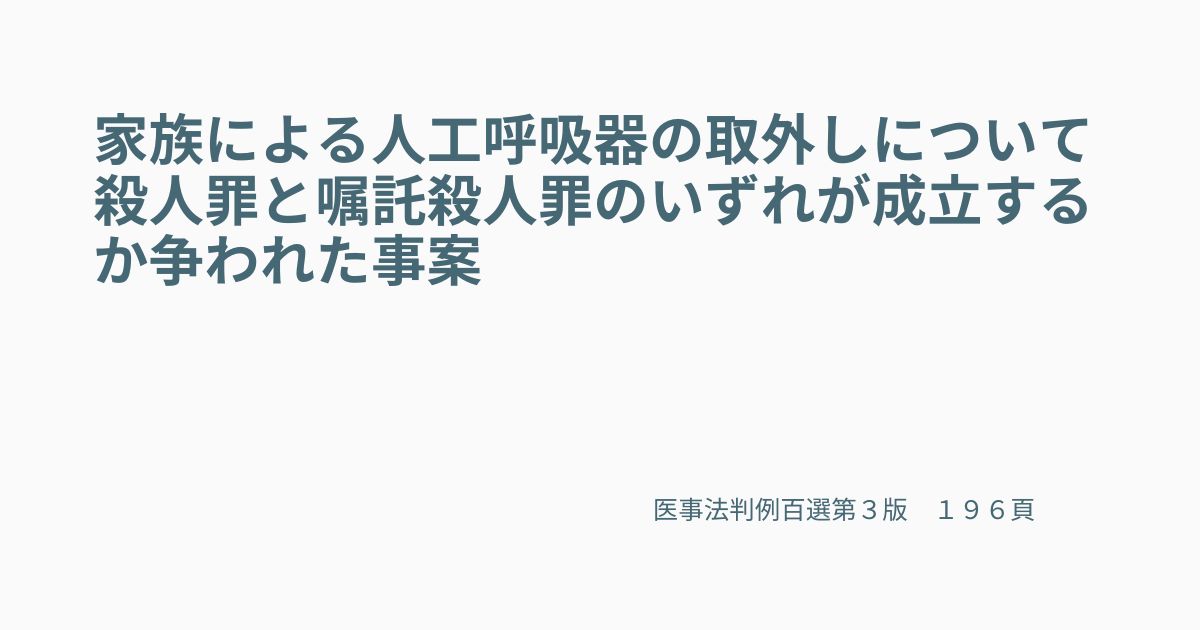大腿動脈穿刺の判断において原則と例外の基準を示した事案
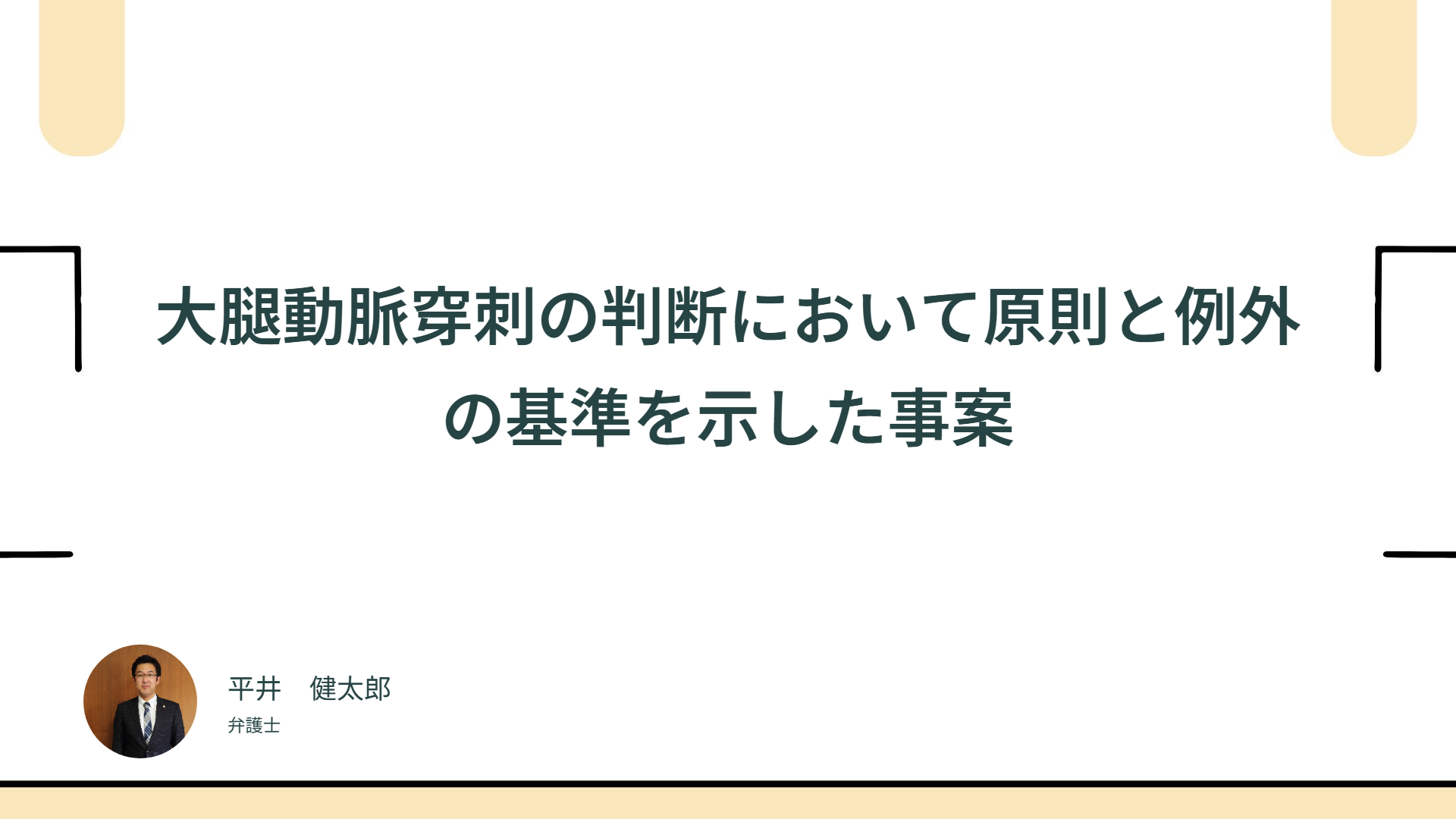
胸痛による呼吸困難のため右鼠径部からの大腿動脈穿刺による採血処置を受けたところ、採血時において丹念に触診して大腿神経を損傷しないように大腿動脈を穿刺すべき義務に違反したとして損害賠償を求め認められた事案
(仙台地裁平成25年2月14日判決、ウエストロー)
【争点】
- 手技上の注意義務違反(過失)の有無
- 原告が被った損害の有無及びその損害額
【判旨+メモ】
本件の採血処置は、「注射針を針のほぼ根元まで刺入(以下「第1刺入」という。)したが,血液の流入がなかったため,注射針を皮膚近くまで引き抜き,もう一度垂直に針をほぼ根元まで刺入したところ,血液の流入が見られた」といった事実経過があり、この第1刺入が問題となっている。
そのうえで、原告の痛み等の供述の信用性について、以下のように判示し認めている。
供述表現の具体性、明確性、不合理な点がないこと、一貫性、虚偽供述の動機について述べられている。
原告が本件採血の第1刺入時に強い痛みを訴えた点に関し,原告は,痛みを訴えた際の感覚につき,「全身に何かミミズが走るようなしびれみたいな感じ」と供述しており,その表現は特異ではあるが,かえって作為が感じられず,電撃的な強いしびれを自分なりの表現を用いて具体的に供述したものと理解することができる。原告は,採血に関する一連の経過のうち,最も強い痛みを感じた時点についても,一番奥まで刺入した時点であると明確に述べているのであって,その内容は全体として具体的かつ自然であり,格別不合理な点は見当たらない。さらに,供述内容等の変遷の有無を見ると,原告は,本件採血時に痛みを感じた状況について,本件採血の翌日には,被告病院内科及び整形外科においてそれぞれ,採血時に強い痛みを感じ,それ以後,右足がしびれている旨説明している上,その後も,後医の受診時を含め,同様の説明をしており,その供述の態度及び内容(被告代理人の反対尋問によっても供述内容は変わらず,維持されている。)は一貫しているといえる。
加えて,原告は,本件採血後に生じた障害により現にそれまで勤務していた会社を解雇され,従前より低い水準の給与しか受けられない勤務先への転職を余儀なくされており(原告本人8頁ないし10頁,弁論の全趣旨),原告が,実際には神経を損傷していないにもかかわらず虚偽の供述をしてまで上記解雇等を甘受する理由があるとは認め難いことからしても,原告の上記供述の信用性は高いといえる。
大腿動脈穿刺に関して、一般的判断基準を示し、過失を認めている。
一般に,注射により大腿神経を損傷した場合には損傷時に通常とは異なる強い疼痛(電撃痛)が生じ,注射後に支配領域のしびれや痛みが生じるとされていること(前記(1)オ)からすると,採血の手技時に強い疼痛があり,その後に支配領域のしびれや痛みがある場合には,原則として大腿神経損傷が生じたと推認される。そして,この場合には,他に神経損傷の原因が認められない限り,神経損傷の原因は大腿動脈からの採血にあると推認するのが相当である。
(中略)
大腿動脈からの採血が原因で神経損傷を生じた場合には,適切な手技によっても不可避的に神経損傷が生じたなどの特段の事情がない限り,採血の手技を担当した医師において,大腿動脈の拍動を正確に触知し,注射針を皮膚に対して垂直に刺入すべき注意義務に違反したものと認めるのが相当である
(中略)
そして,被告担当医は,注射針を一番奥まで刺入したが血液の流入がなかったため(完全に針を抜くことはせずに)皮膚近くまで針を戻した上で,微調整をしてもう一度,注射針を垂直に刺入したところ,血液の流入が認められた(上記(2)ア)というのであって,このように刺入箇所を変更することなく垂直に刺入し直した結果,採血に成功したという経過に加え,原告が本件採血時において身長167cm,体重89kgという肥満体型であったこと(前記前提事実(1))を考慮すると,被告担当医は,第1刺入時において,大腿動脈の拍動部分を正確に触知せず,あるいは注射針を皮膚に対して垂直に刺入しなかったと見るのが相当であるから,被告担当医は,本件採血における手技上の注意義務に違反したというべきである。
①採血の手技時に強い疼痛
②その後に支配領域のしびれや痛み
⇒原則として大腿神経損傷が生じたと推認
③この場合には,他に神経損傷の原因が認められない
⇒神経損傷の原因は大腿動脈からの採血にあると推認
④適切な手技によっても不可避的に神経損傷が生じたなどの特段の事情がない
⇒大腿動脈の拍動を正確に触知し,注射針を皮膚に対して垂直に刺入すべき注意義務に違反
上記のような推認などにより、3段階で過失の有無が判断されている。
それぞれの事情が、大腿神経損傷の有無、原因が採血であるか否か、不回避性の有無、を判断するうえでどう重要になるのか示唆しているといえ、他事件でも参考となる判決である。