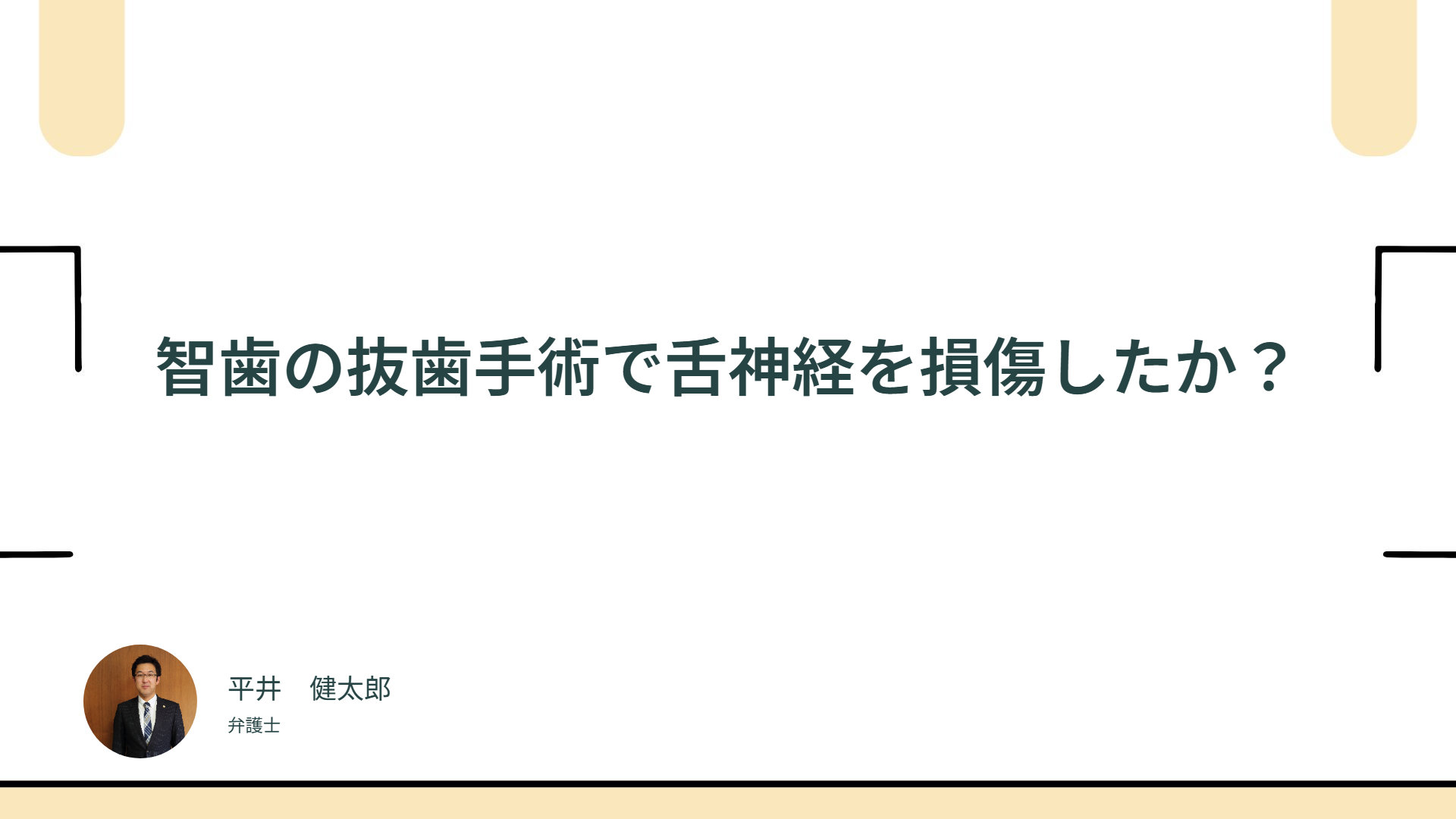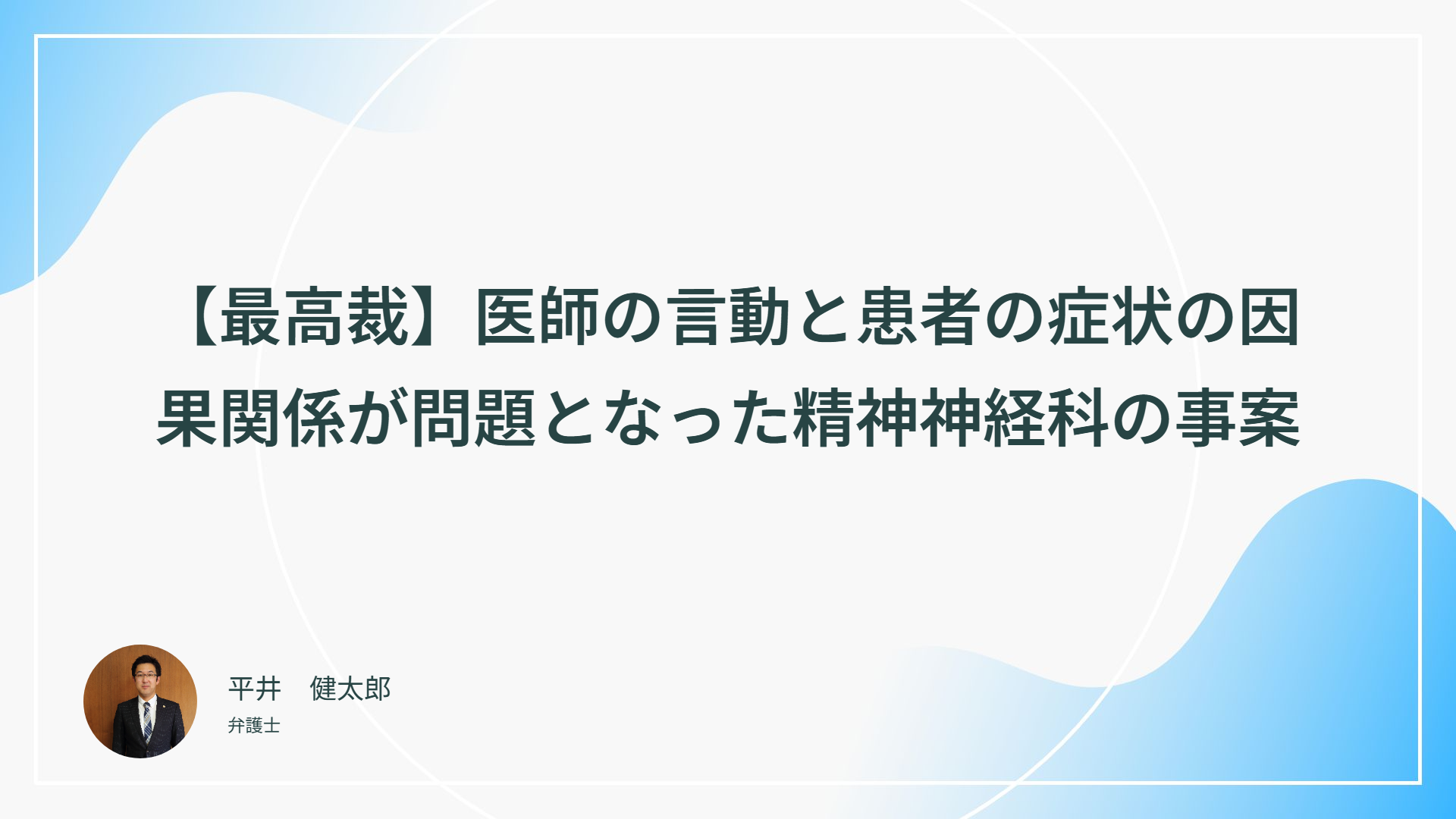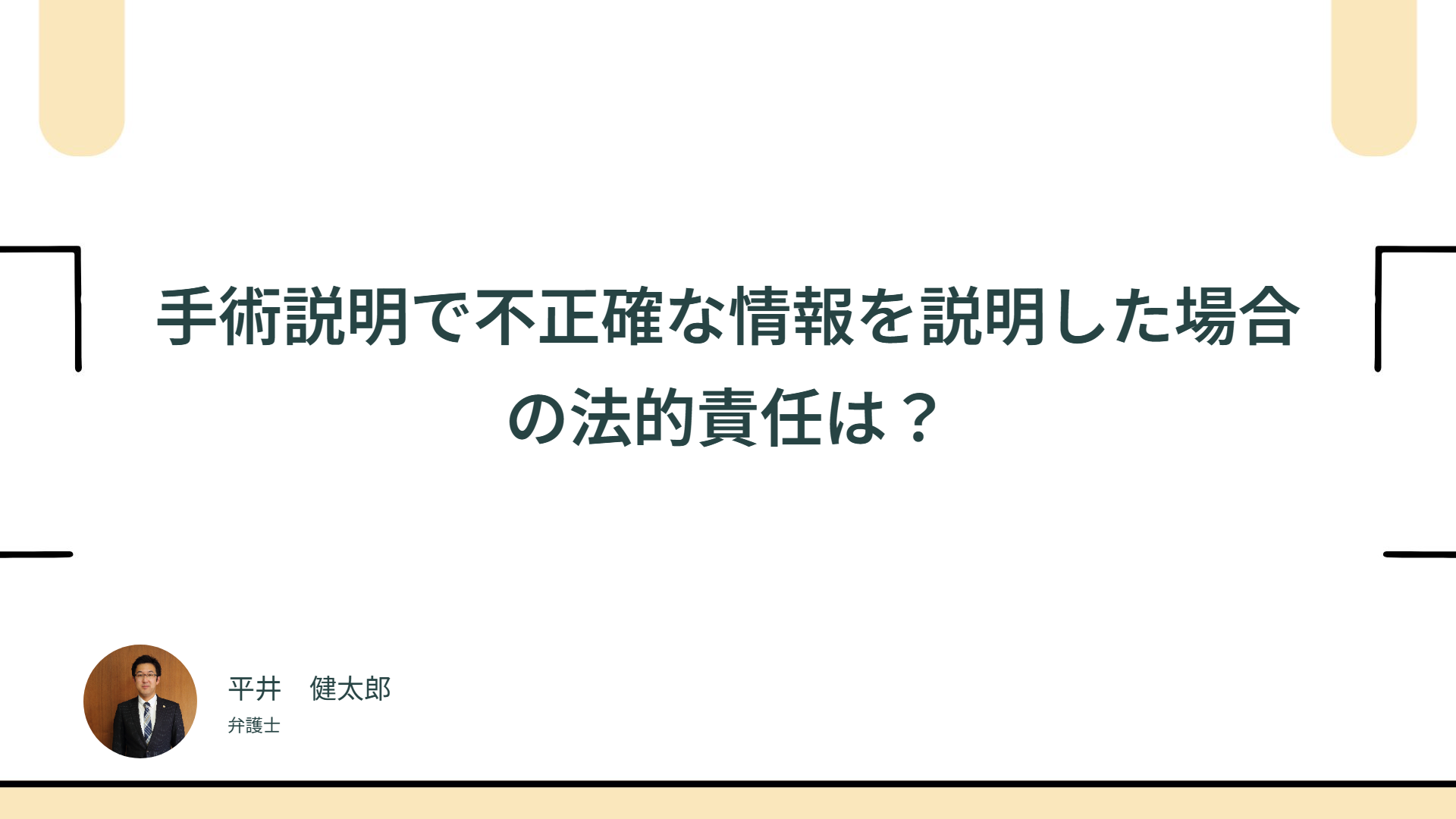鑑定書に基づき判断が示され、説明義務違反も否定された事案
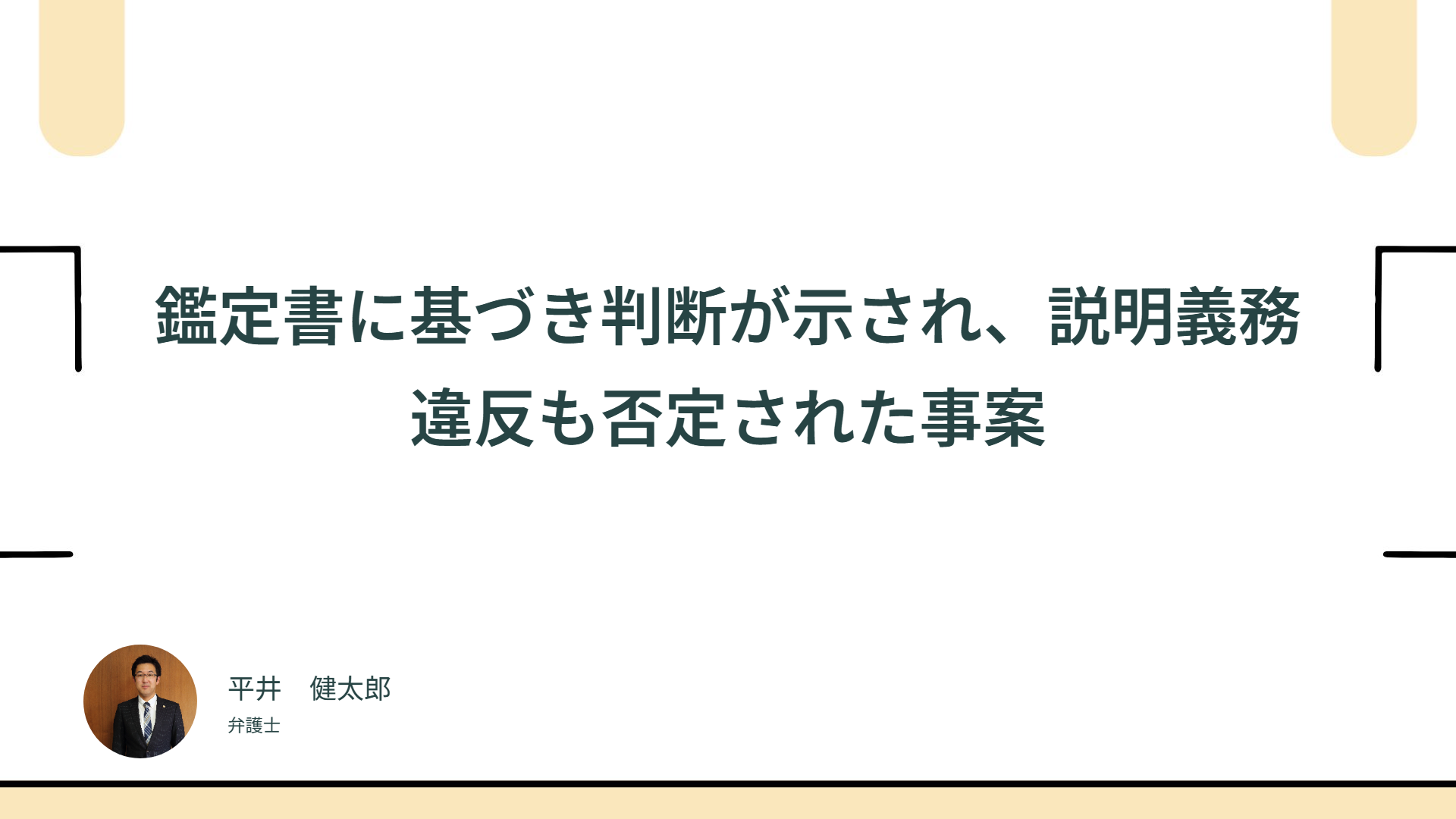
体調不良で救急受診し、卵巣腫大や肺炎の可能性が指摘され抗生剤が処方されたが、体調が改善せず、右肺肺炎や大動脈炎症候群の再燃を疑い気管支鏡検査(本件検査)を実施したが、急変して患者が死亡した事案(大阪地裁令和5年9月5日判決、医療判例解説116号79頁)
【争点】
- 本件検査を実施したことに関する注意義務違反の有無
- 1回目の生検箇所の止血の確認に関する注意義務違反の有無
- 出血時の対応に関する注意義務違反の有無
- 気管支鏡の操作又は生検部位に関する注意義務違反の有無
- マニュアルに沿った準備態勢に関する注意義務違反の有無
- 本件検査の実施に関する説明義務違反の有無
- 遺族に対する説明義務違反の有無
- 因果関係
- 損害
【判旨+メモ】
本件患者について器質的肺炎の鑑別は必要であり(鑑定書)、器質化肺炎は、気管支鏡検査による生検によって確定診断ができることからすると、本件患者に気管支鏡検査による生検の適応はあったといえる(鑑定書)から、本件検査を行ったことが不適切であったとはいえない。
争点①については鑑定書の記載に基づき判断されている。
また、心肺停止後に行われた措置及び時間的経過については(中略)F看護師が経時的に記録をし、(中略)B医師がF看護師の記録を基に経過を整理し、E医師の確認を得てカルテを完成させていることからすると、その各時刻が正確な日本標準時であるかどうかはともかく、各措置及び時間的経過については、上記カルテの記載のとおりの経過であったと認めるのが相当であり
争点③の出血時の対応に関するカルテの信用性について、上記のように、作成過程を認定し、時刻の正確性ではなく、時間的経過を重視していることがわかる。
気道確保の対応については、以下のように不適切と判断されている。
気道確保措置の点については、鑑定の結果によれば、気道確保の方法に関しては、気管支鏡を用いて気管内挿管を試みても血液により視野確保困難で断念した場合、引き続き輪状甲状靱帯切開を行った手順は通常考えられる方法であり不適切とはいえないが、心肺停止(「9:50気管支鏡検査中心肺停止」)から気管挿管に着手する(「10:05挿管開始」)までに15分経過しているのは長すぎるといわざるを得ず、不適切であるとされており(鑑定書)、これを覆すに足りる証拠はない。
因果関係については、救命可能性は極めて低いと判断されている。
鑑定の結果によれば、本件では、出血量が多かったことにより、止血できなかったので、出血を止めることができない以上、気管挿管等の処置を行うことはほぼ不可能であり、救命の可能性は極めて低かったとされ(鑑定書、補充鑑定書)、これを覆すに足りる証拠はない。
このように本件では鑑定が実施されたこともあり、裁判所は鑑定書の内容に沿って判断を示している。
なお、本件では、説明義務違反も争われているが、以下のとおり認められていない。
本件当時、日本呼吸器内視鏡学会安全対策委員会による手引き書において報告されていた平成22年全国調査において、診断的気管支鏡による大量出血を原因とした死亡例はみられなかった旨の報告がされていたことや、本件患者やその家族が、本件検査の死亡のリスクについて特に関心を示していたなどの事情も認められない(認めるに足りる証拠はない)ことに照らすと、本件検査の死亡のリスクについて説明義務違反があったとは認められない。
これは、患者や家族が関心を示さなければ説明しなくてもいいと判断したわけではない。
あくまで、手引き書において死亡例がみられなかったことから原則的には説明する必要はないと判断されており、例外的に患者が関心を示していたら説明しなければならない場合もあるが本件ではそういった事情は認められないから、原則どおり説明義務はないと判断されたと考えられる。