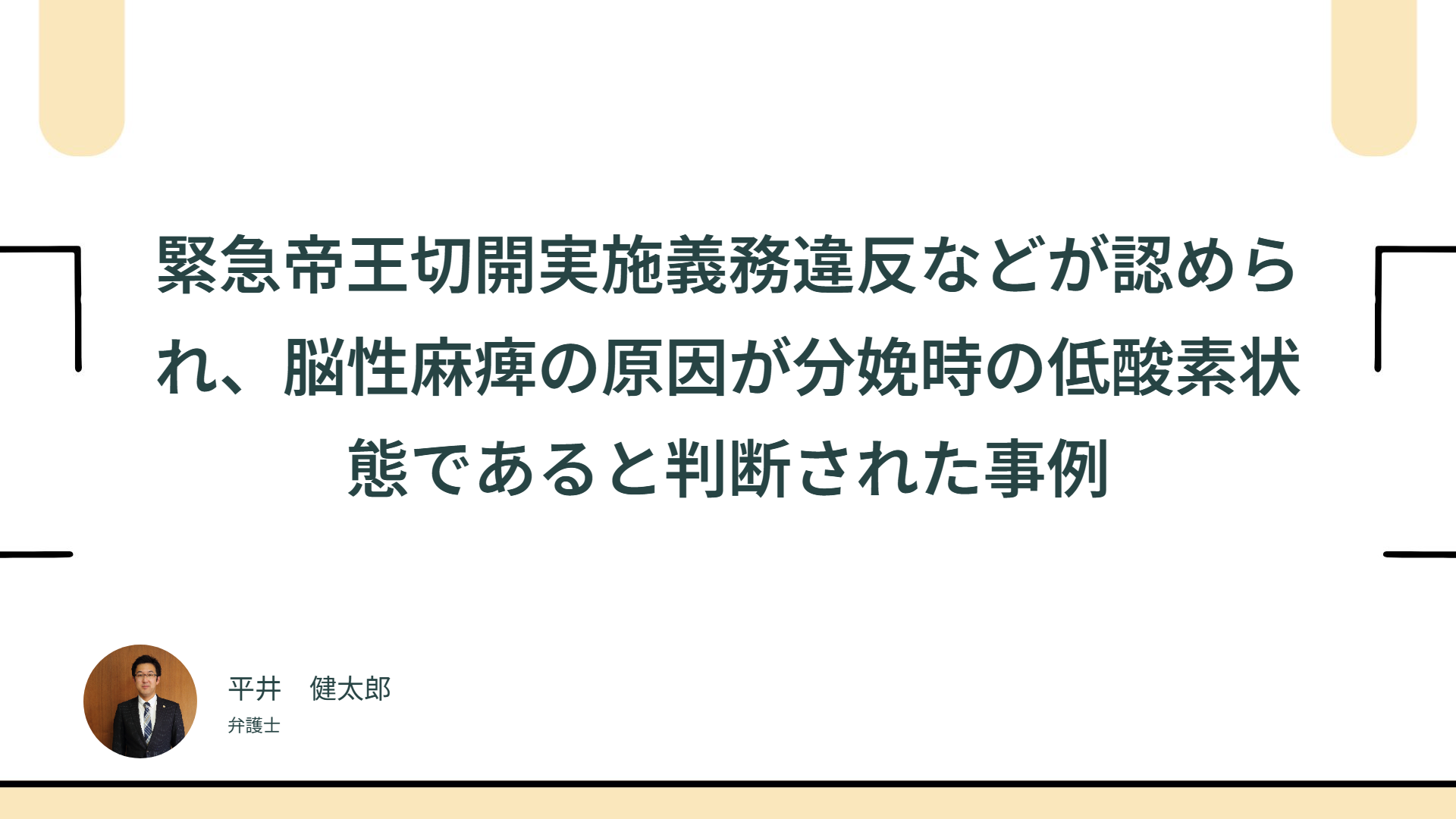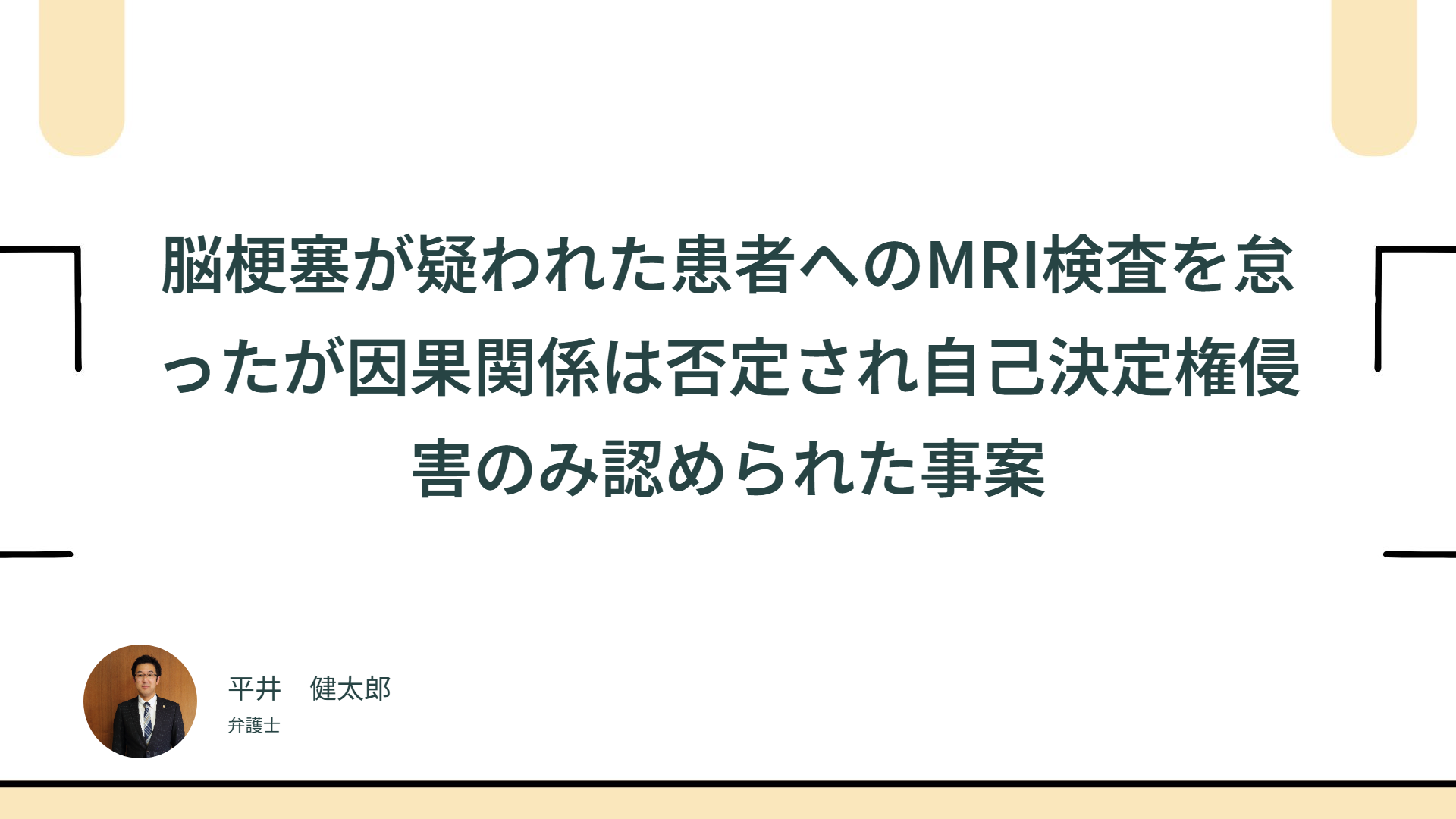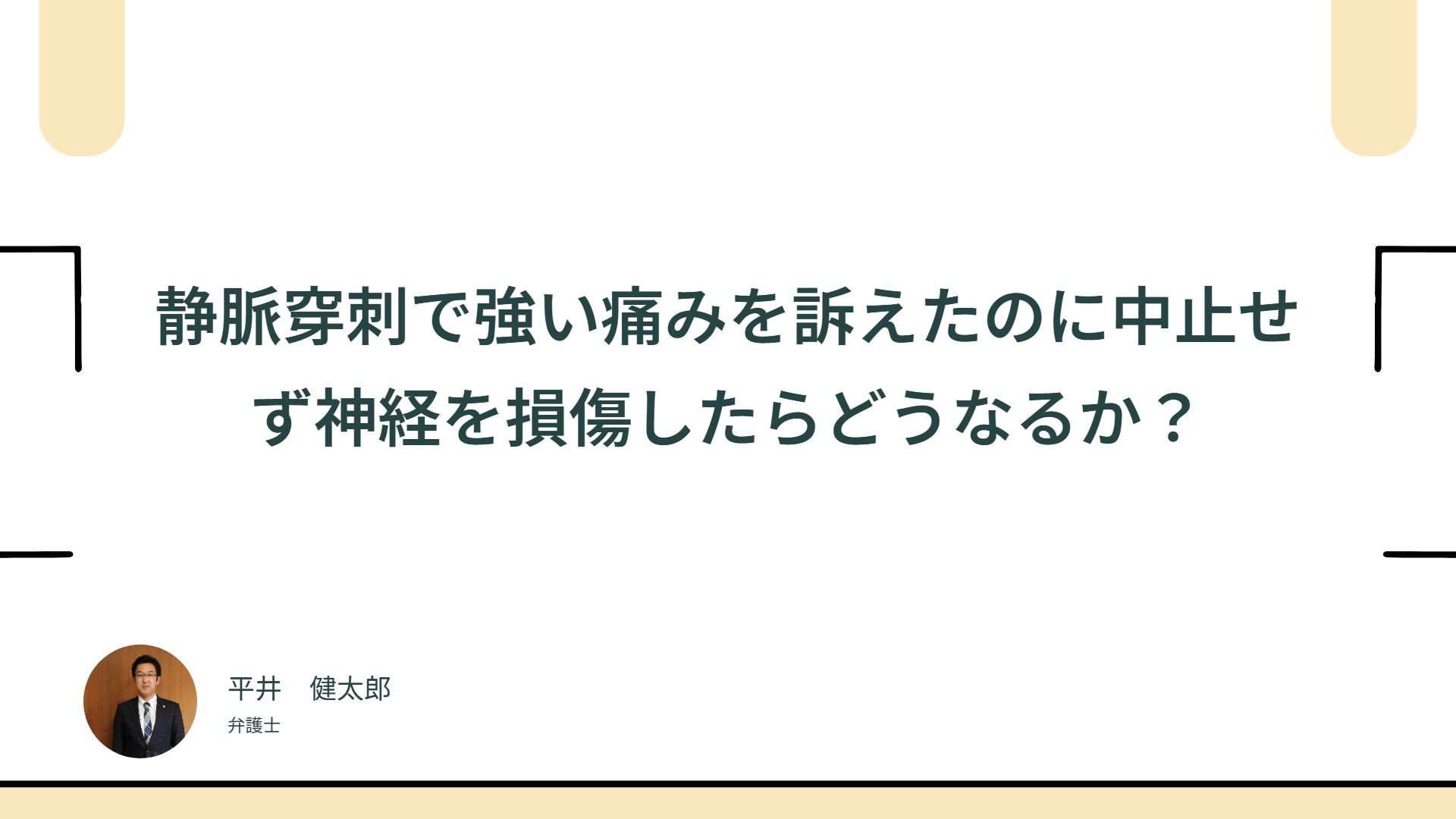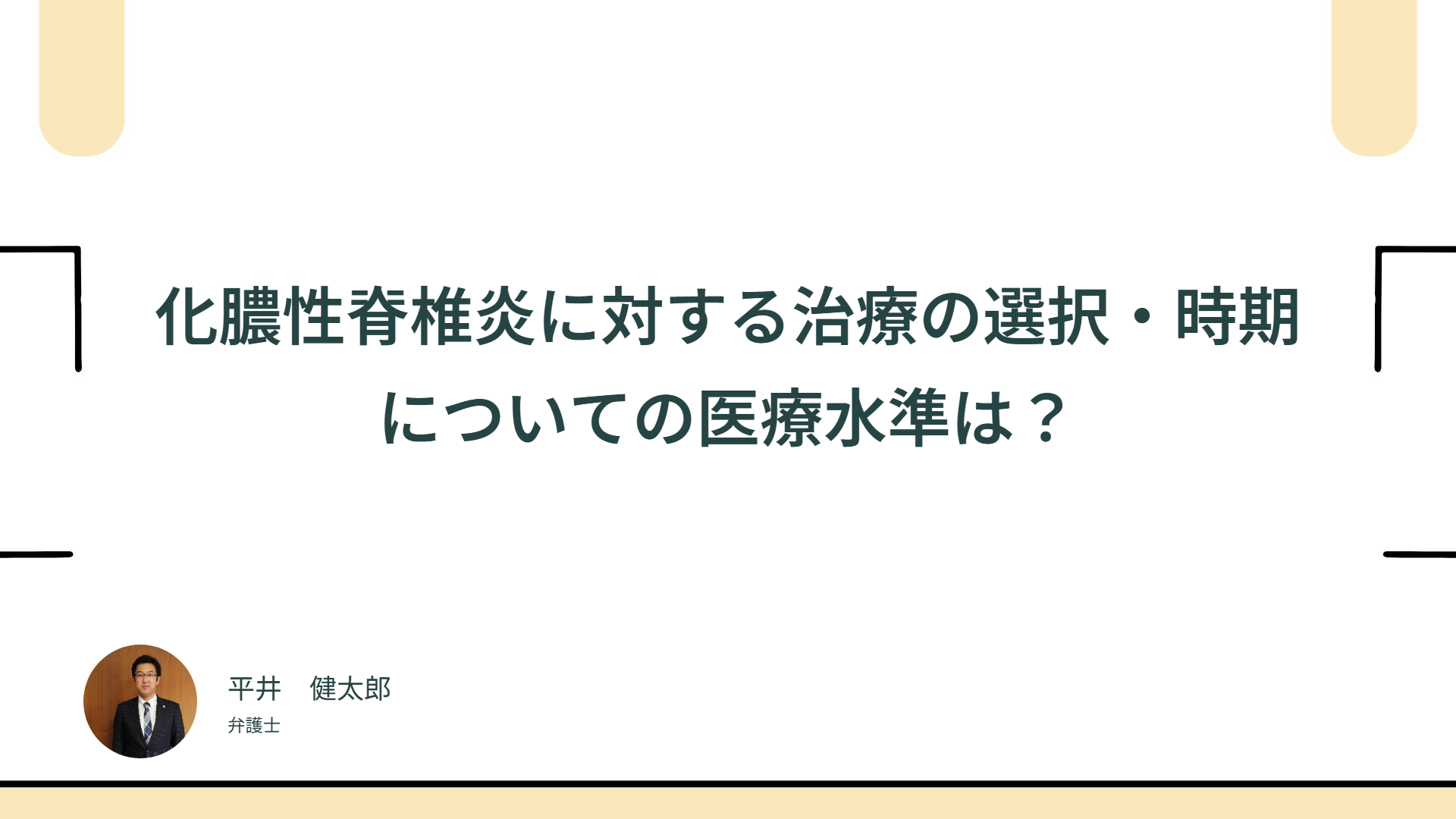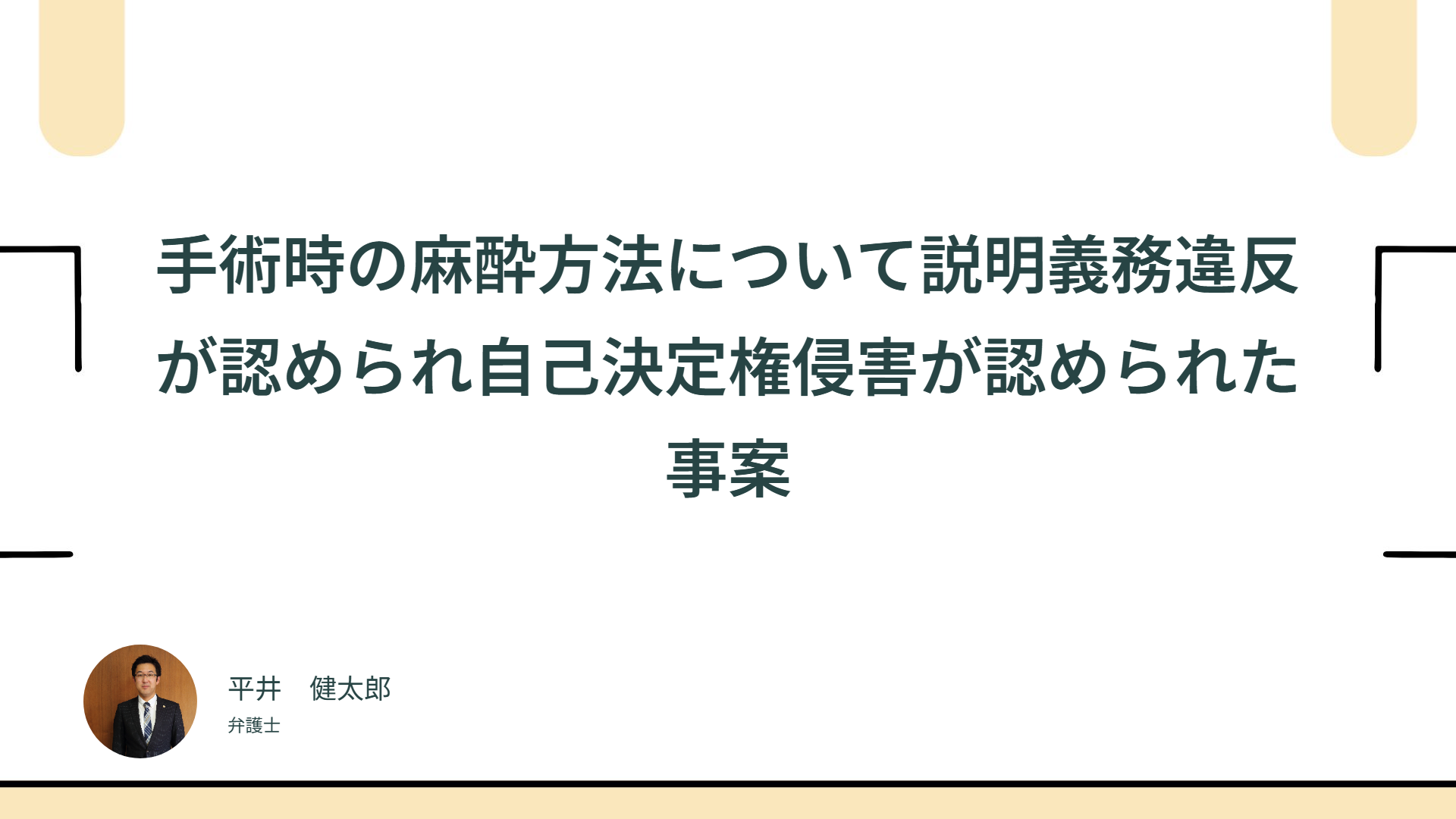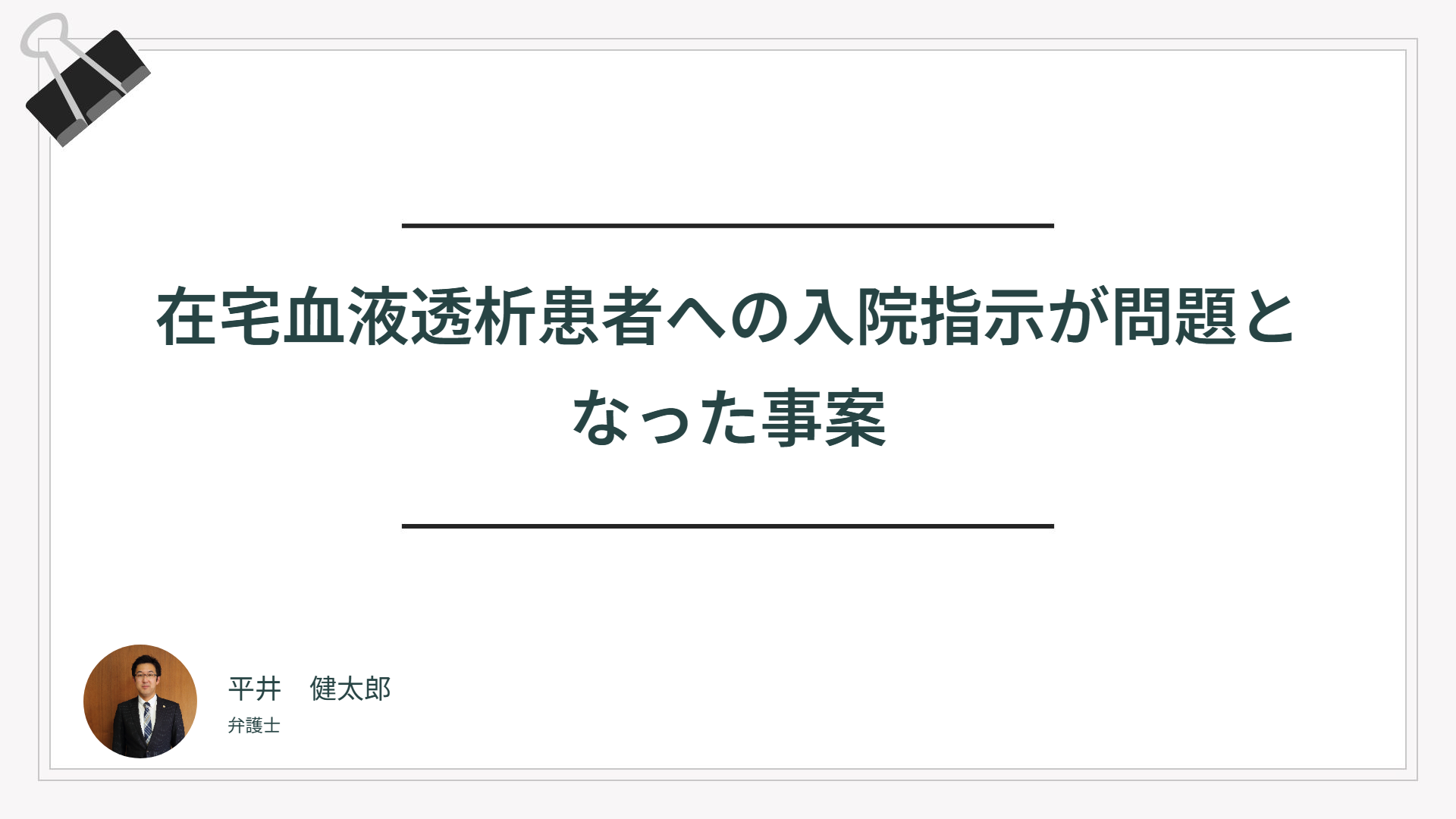子宮全摘術後に生じた尿管損傷に対する処置はどうすべきか?
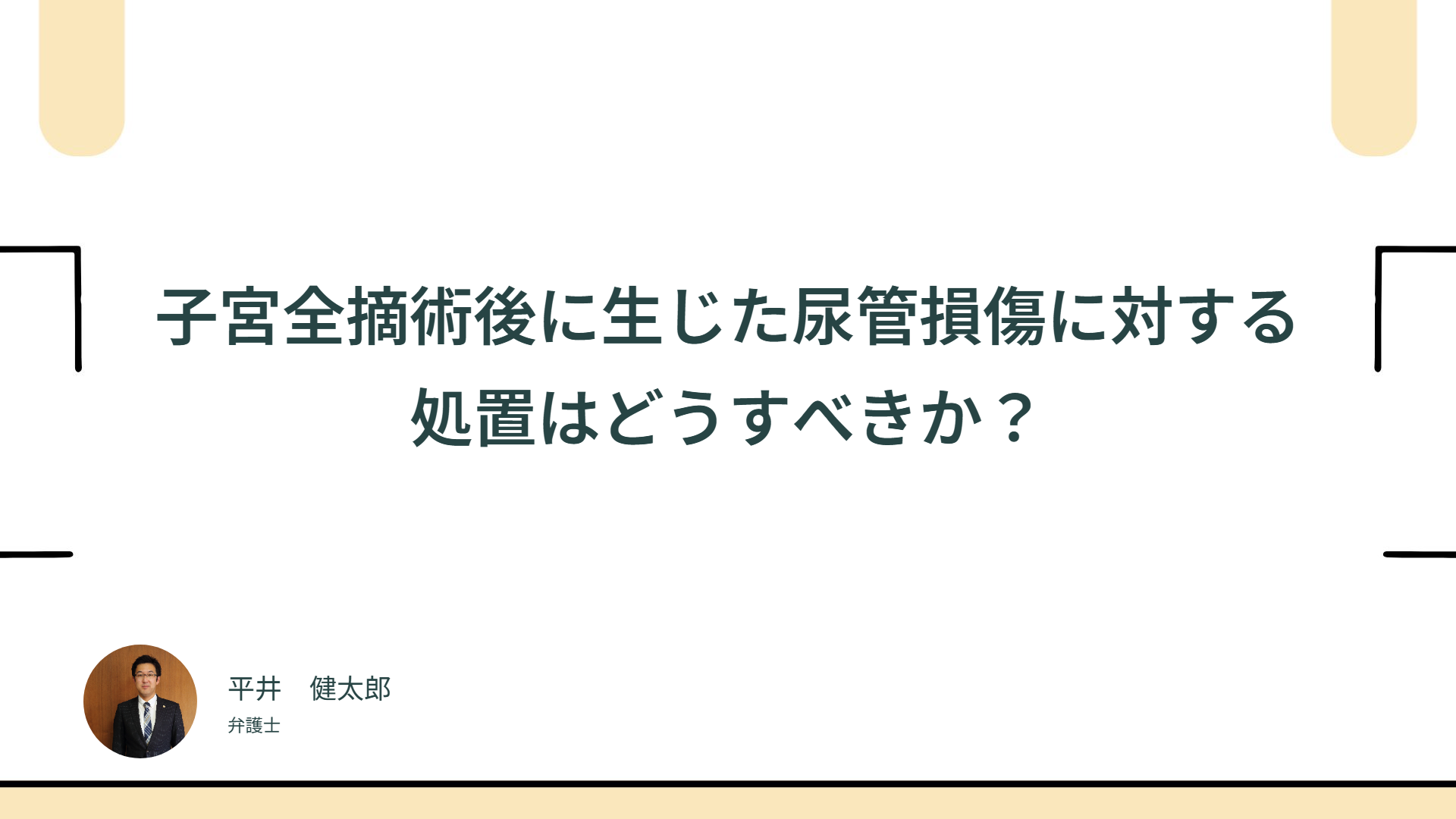
子宮体がんと左卵巣腫瘍に対し準広汎子宮全摘術、両側付属器切除術、骨盤リンパ節郭清術を受けた後に生じた尿管損傷に対して、損傷が左右どちらの尿管に生じているかを確認し尿管カテーテルを挿入すべき注意義務を怠ったとして、損害賠償を求めた(大阪地裁令和7年3月7日判決、医療判例解説117号25頁)
【争点】
- 8月13日の時点での尿管損傷の有無
- 被告病院の医師に、8月13日以降速やかに、患者の尿管損傷が左右どちらの尿管に生じているのかを確認し、患側に尿管カテーテルを挿入すべき注意義務の違反があるか
- 被告病院の医師に、8月13日以降速やかに、尿管カテーテルが腎臓まで到達しなかった場合に尿管損傷の手術を実施すべき注意義務の違反があるか
- 因果関係
- 損害
【判旨+メモ】
以上のように、原告について見られた本件手術後の膣からの排液の状況に、本件インジゴ検査や膀胱鏡検査の結果が尿管膣瘻の可能性を示唆するものであったこと、7月26日から8月10日までの経膣エコー検査でも腹水はないとされていること、さらには、9月4日の尿環境検査で本件手術によるものと考えられる熱損傷による狭窄が認められたことを併せ考慮すると、後方視的に見れば、8月13日の時点で原告に尿管損傷が生じていた可能性が高いというべきであり、同日の時点で原告に尿管損傷が生じていたと認められる。
本件では、尿管損傷がいつの時点で生じていたかが問題となっている。時点は過失や因果関係を構成するうえで重要である。
本件でいえば、8月13日の時点の過失を尿管損傷が生じていることを前提に主張している。
仮に、尿管損傷が生じた時点が8月20日だったとした場合、それより前の時点である8月13日において「尿管損傷が左右どちらの尿管に生じているのかを確認」する義務などが生じる余地がなくなる。
患者側代理人としては、どのような過失(ミス)があるかを検討することも重要であるが、どの時点の過失を設定するかも非常に重要であり、裁判であれば勝敗に影響することもある。
そのため、時点については時間をかけて検討する必要がある。
なお、本件の時点の設定に問題があると述べているわけではなく、一般論として時点の設定が重要であることを言及するものである。
しかし、比較的近時の複数の医学文献でも、損傷部位の特定方法として造影CTや逆行性腎盂尿管造影以外の方法は紹介されておらず、本件証拠上、昭和43年のものである上記論文の他に、尿管カテーテルを挿入すべき患側の尿管を判別する方法として上記①ないし③の方法があることを示す医学文献等は認められない。
(中略)
そうすると、術後に尿管損傷が疑われる場合に、上記①ないし③の方法により尿管損傷が左右どちらの尿管に生じているのかを確認して患側に尿管カテーテルを挿入するという措置を採ることが、本件当時の医療水準において一般的であったとはいえず、むしろ、その有用性には疑問もあるといわざるを得ない。
(中略)
これに対し、原告協力医の意見書は、尿漏れは術後長時間持続し、その漏出量も決して少なくなく、本件インジゴ検査でも陽性反応が出ているから、この時点で自然治癒は期待できなかったと思われる旨の意見を述べるが、かかる意見は、上記の各医学文献と整合しないものであり、客観的な医学的知見による裏付けを伴うわけでもないから、直ちに採用することはできない。
(中略)
原告に排液による不快感が継続していたことを踏まえても、有用性に疑問のある原告主張の方法による処置を速やかに実施する程度の緊急性があったということはできないから、被告病院の医師が8月13日以降速やかにこれらの処置を採らなかったことが、本件当時の臨床医学の実践における医療水準を下回るものであったとは認められない。
裁判所は、患者側がが主張する患側の尿管を判別する方法に医学的根拠(文献等)が認められないとし、病院主張の自然治癒の可能性についてはそれを認めつつ、患者側提出の協力意見書について文献との整合性がないこと、他に医学的裏付けがないことを理由に採用しなかった。
協力医の意見も重視していると思われるが、医師の意見についても裏付けとなる文献等を重視していると考えられる。
本件では、医療水準を下回っていないという判断をされていることから、患者側主張の手技自体を否定するものではなく、それが「医療水準」とは言えないと判断している。
繰り返しになるが、患者側の主張としては、根拠となる文献を提出することが、裁判官を説得するうえで重要になるということだろう。
もっとも、意見書が不要というわけではなく、文献と意見書をセットで提出することが望ましいが、実際の訴訟では準備が難しいこともあり、そのような場合には手元にある資料等でなんとか主張を組み立てることになる。