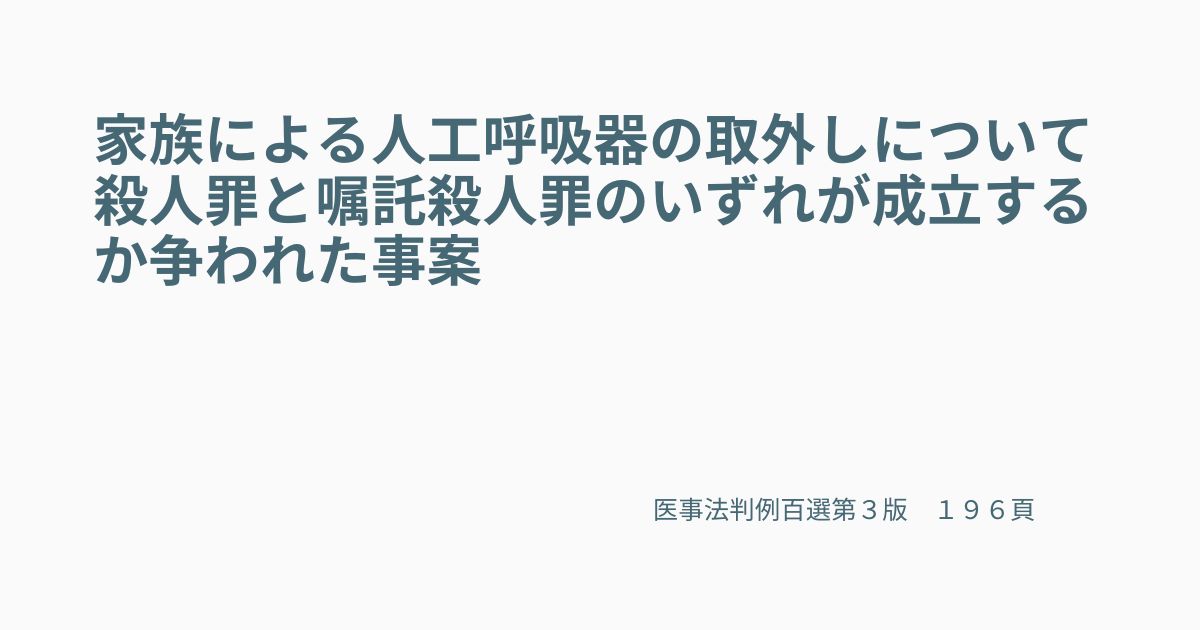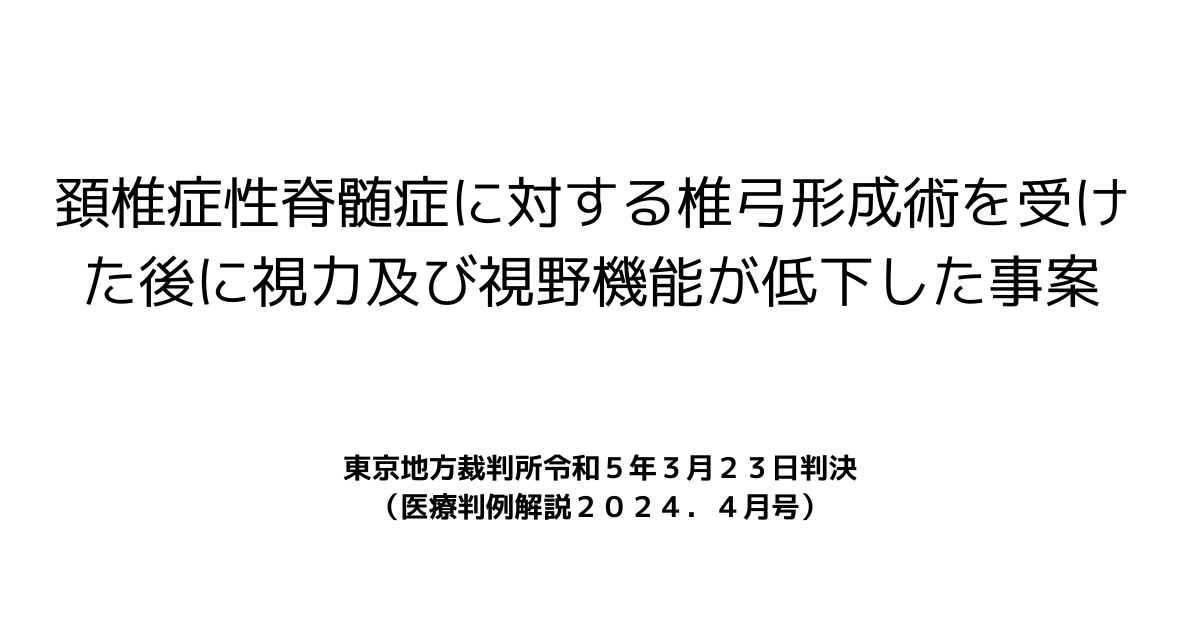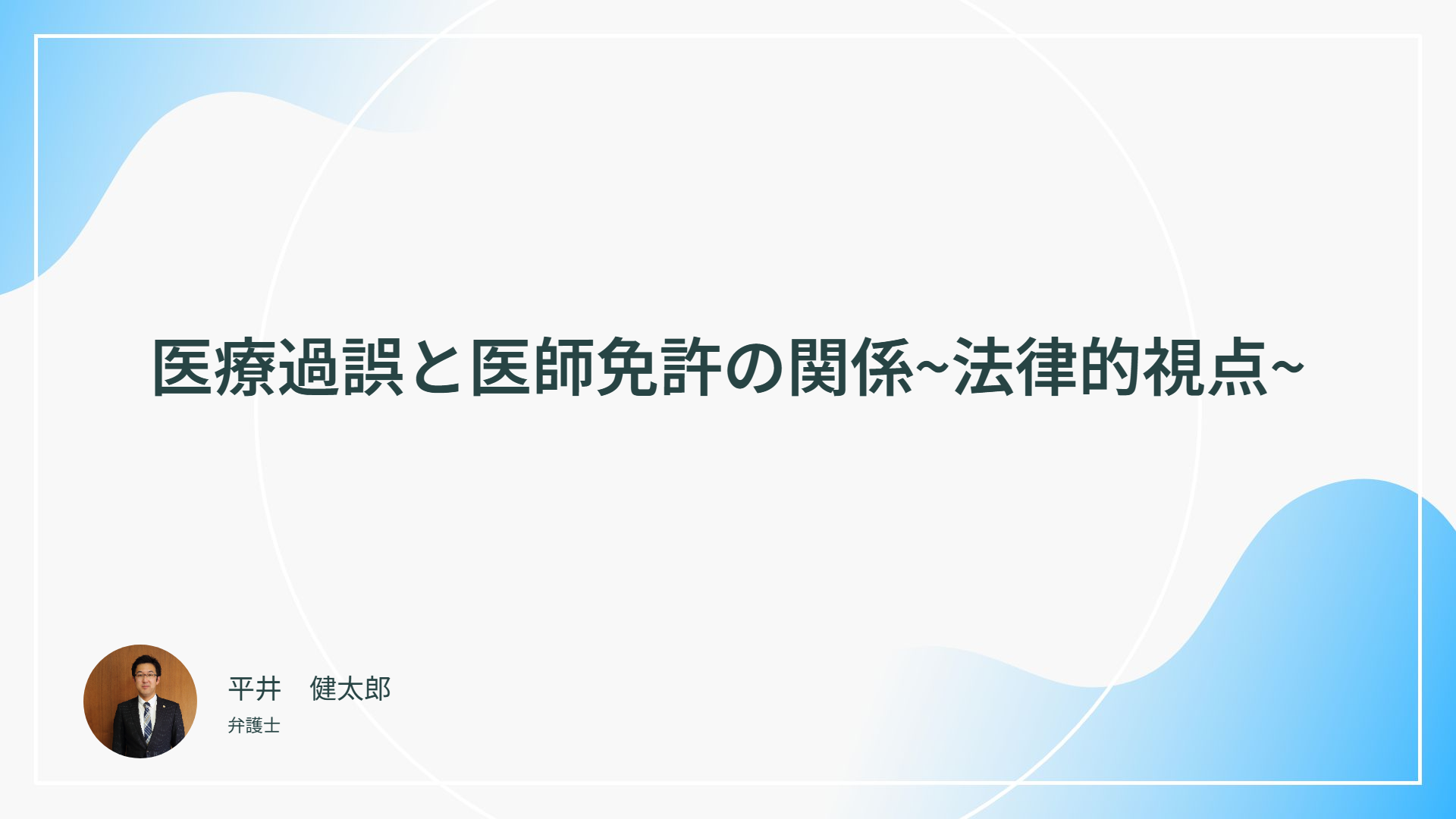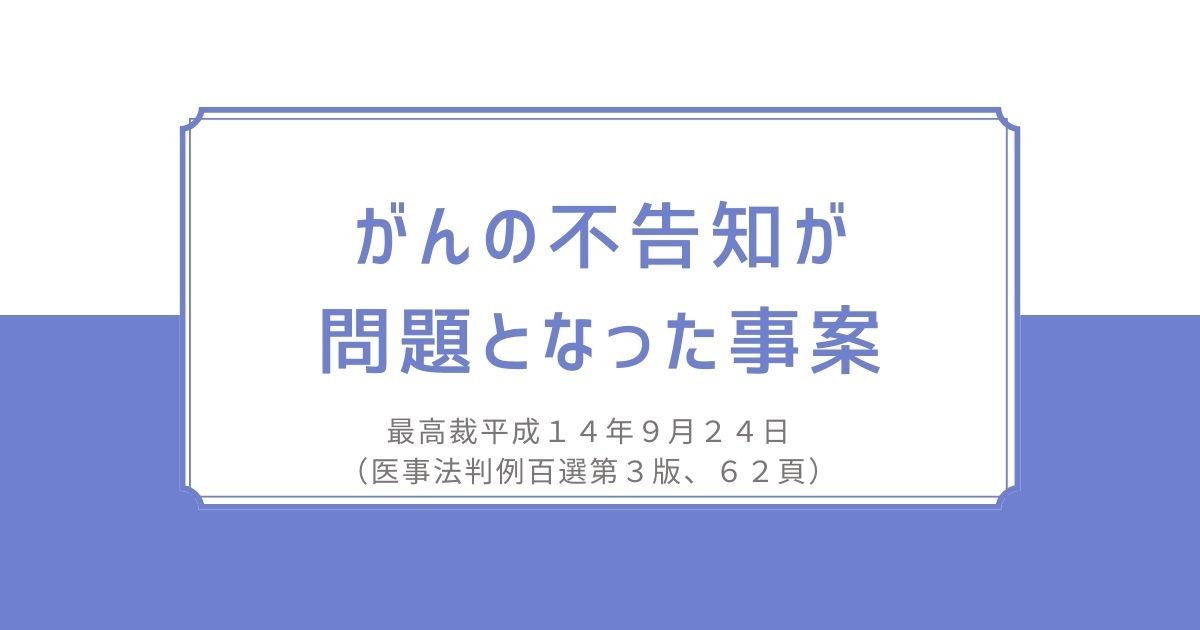分娩監視に係る過失が認められ結果との因果関係も認められた事案
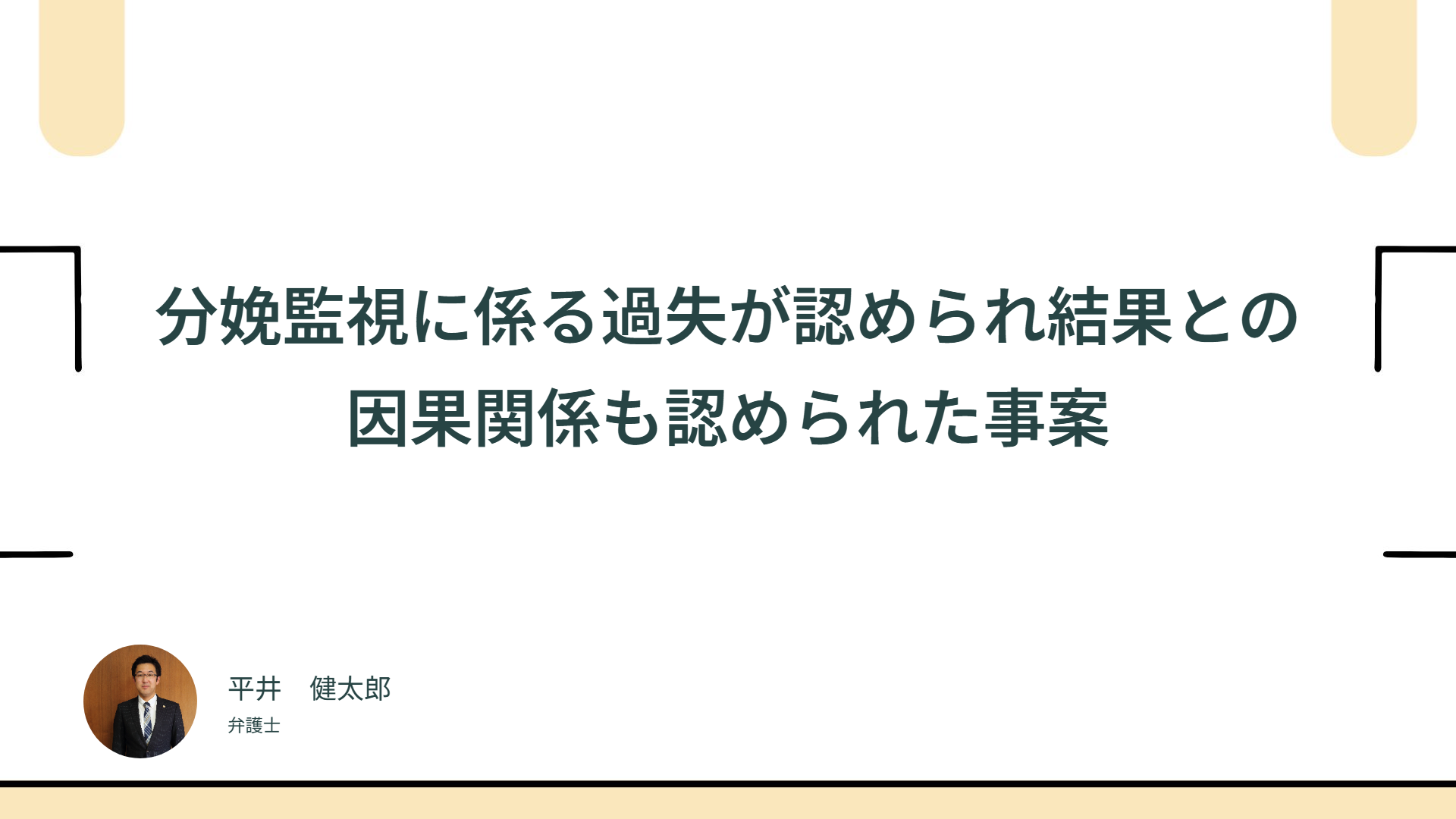
重症新生児仮死の状態で出生し脳性麻痺等の後遺症が残ったことについて、陣痛促進剤投与や分娩監視に過失があったとして争われた事案
(名古屋地裁平成26年9月5日判決、判時 2244号65頁、医療判例解説52号24頁)
【争点】
- プロスタルモン・F投与の判断に係る注意義務違反の有無
- プロスタルモン・F投与量に係る注意義務違反の有無
- 分娩監視に係る注意義務違反の有無
- 蘇生措置に係る注意義務違反の有無
- 因果関係
- 損害
【判旨+メモ】
まず、争点①②については認められなかった。争点に対する証拠として意見書も提出されていたが、以下のような評価がされている。
そこで検討するに、D意見書には、要旨として、妊娠三七週以降の前期破水の場合、その八〇%が二四時間以内に陣痛が始まり、出産に至るので、感染のおそれがなければ分娩待機とし、二四時間過ぎても陣痛が発来しない場合に、陣痛誘発を試みるのが一般的であるところ、本件では、入院時に感染所見はなく、陣痛周期が五分から六分間隔で認められており、一〇時前時点で陣痛がほぼ消失していたとしても、B医師が、プロスタルモン・Fの投与を指示した八時頃及びプロスタルモン・Fの投与を実施する直前である一〇時前頃には、必ずしも遷延分娩を予測させる所見はなかったのであるから、プロスタルモン・Fを投与する必要性はなく、しばらく様子を見て、自然な進行を待つべきであった旨の記載がある。
しかしながら、ガイドライン二〇〇八の記載内容やE医師作成の意見書(以下「E意見書」という。)に照らすと、D意見書で述べられた根拠は、八時頃及び一〇時頃の時点で、プロスタルモン・Fの投与を行わないで待機することの相当性を示す根拠とはいい得るものの、それを超えて、同時点で、プロスタルモン・Fを投与することが採り得る選択肢の一つではなく、不適切な医療行為であったという根拠として十分なものとはいえない。
上記は、鎮痛促進剤投与の必要性が争われ、患者側は必要性がなかったことを証明しなければならない立場にあった。
裁判所は、意見書の見解は否定しておらず、陣痛促進剤を投与しない選択肢の相当性として認めたが、投与したことが不適切とまでは言えないとして評価している。
この判決からわかるとおり、患者側としては、他の選択肢を示すだけではなく、病院が選択した方法が「不適切」であったことまで立証しなければならない。
この裁判例では、争点③分娩監視に係る注意義務違反の有無がメイン争点であった。
分娩監視に関しては、胎児心拍数陣痛図をもとに、どの時点で・どのような波形が認められ・何をすべきであったかを証明しなければならず、胎児心拍数陣痛図を読めることが求められる。
証拠〈省略〉によれば、一五時四三分頃及び一五時四五分頃に遅発一過性徐脈と評価し得る徐脈が認められる。その時点における基線細変動であるが、基線を読むためには、本来、一過性変動の部分を除き、その部分が少なくとも二分以上続かなければならないところ(前提事実(3)ア(ア))、一五時四〇分頃の原告X1の胎児心拍数図においては、一過性変動の部分を除いて二分以上続いている部分がなく、正確に基線を読むことができないほどに徐脈が頻発しているということができる。そして、その波形の様子は、一五時四〇分までのものとは様相が異なり、明らかに振幅の程度が減少している。このように、遅発一過性徐脈と評し得る徐脈が複数回発生し、かつ、基線細変動の状態にも異常が生じていることに照らすと、被告病院の助産師及びB医師は、遅くともこの時点で原告X1の胎児機能不全を疑い、少なくとも母体の体位転換、陣痛促進剤の投与停止をまず行い、並行して急速遂娩の準備を行うべき注意義務があったと認めるのが相当である。
(中略)
遅発一過性徐脈は基線細変動の状態によらず胎児機能不全と診断されるとの医学的知見が日本産婦人科学会による「産婦人科研修医のための必修知識二〇〇七」に記載されており、遅発一過性徐脈は、それだけで直ちに胎児機能不全と診断し得るかどうかは措くとしても、その出現自体が胎児機能不全の発生について十分に警戒すべき重要な徴表であるということができる。そして、前記のとおり、一五時四〇分頃以降の原告X1の胎児心拍数図には、二分以上続いている基線部分の消失、徐脈の頻発、振幅の程度の減少など、一五時四〇分までのものとは様相が異なる波形が出現していたものであるから、これらの波形異常と遅発一過性徐脈の出現を併せ考慮すると、酸素投与のみでは不十分であったと認めるのが相当である。
胎児心拍数陣痛図の判断では、何時何分に遅発一過性徐脈が認められるか、基線細変動はどうか、といったことを詳細に主張し認定してもらう必要がある。
当然、意見書を準備して主張をすることを考えるが、書面を作成するにあたっては自身が理解していないと説得的な主張は難しいと思われる。
また、引用を省略しているが、どの時点で過失を捉えるか問題となり、本件でも複数の時点の過失が争われていた。
因果関係については以下のとおり認められている。
そして、被告病院の助産師及びB医師が、一五時四五分頃の時点で、適切に原告X1の胎児心拍数図等を監視し、母体の体位転換、陣痛促進剤の投与停止をまず行い、並行して急速遂娩の準備を行い、状態が改善しない場合には急速分娩に踏み切るという注意義務を果たしていれば、一五時四五分に近接した時間において原告X1の上記胎児機能不全は解消された高度の蓋然性があるというべきである。被告病院の助産師及びB医師が上記注意義務を怠った結果、原告X1は、一六時三六分に出生するまで約四八分間胎内で胎児機能不全の状態に置かれていたというべきであり、この間に原告X1の脳性麻痺が発症したと推認するのが相当である。
(裁判で引用されている書証)
①「産婦人科研修医のための必修知識2007」(2007年1月発行)
②「胎児の評価法―胎児評価による分娩方針の決定―」(平成20年2月、社団法人日本産婦人科医会)