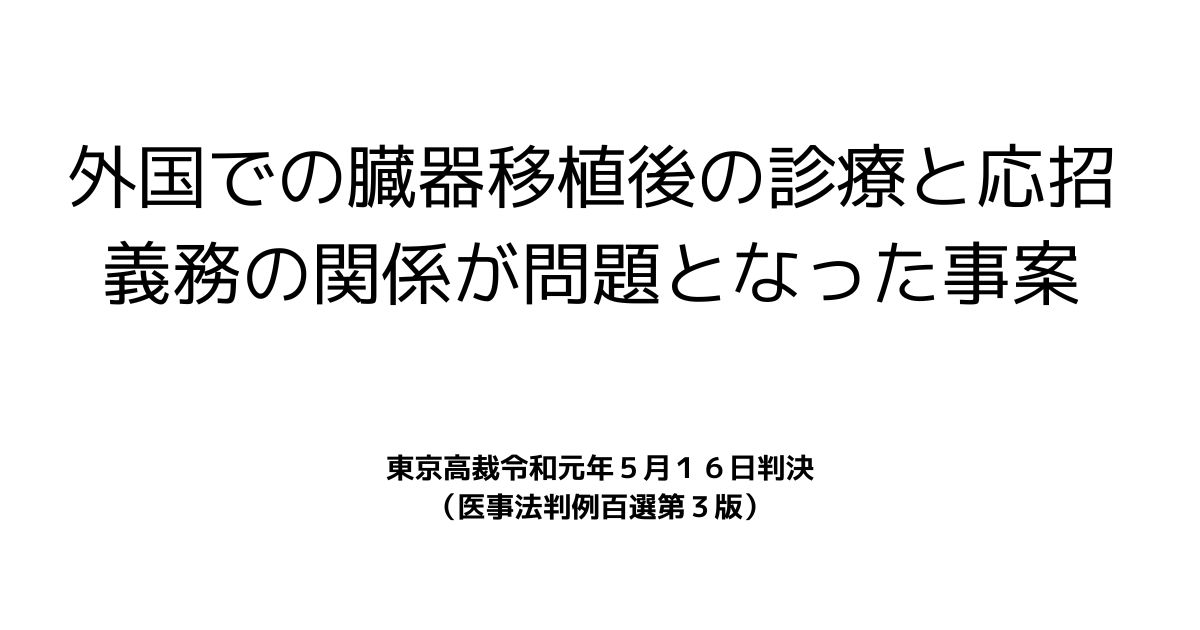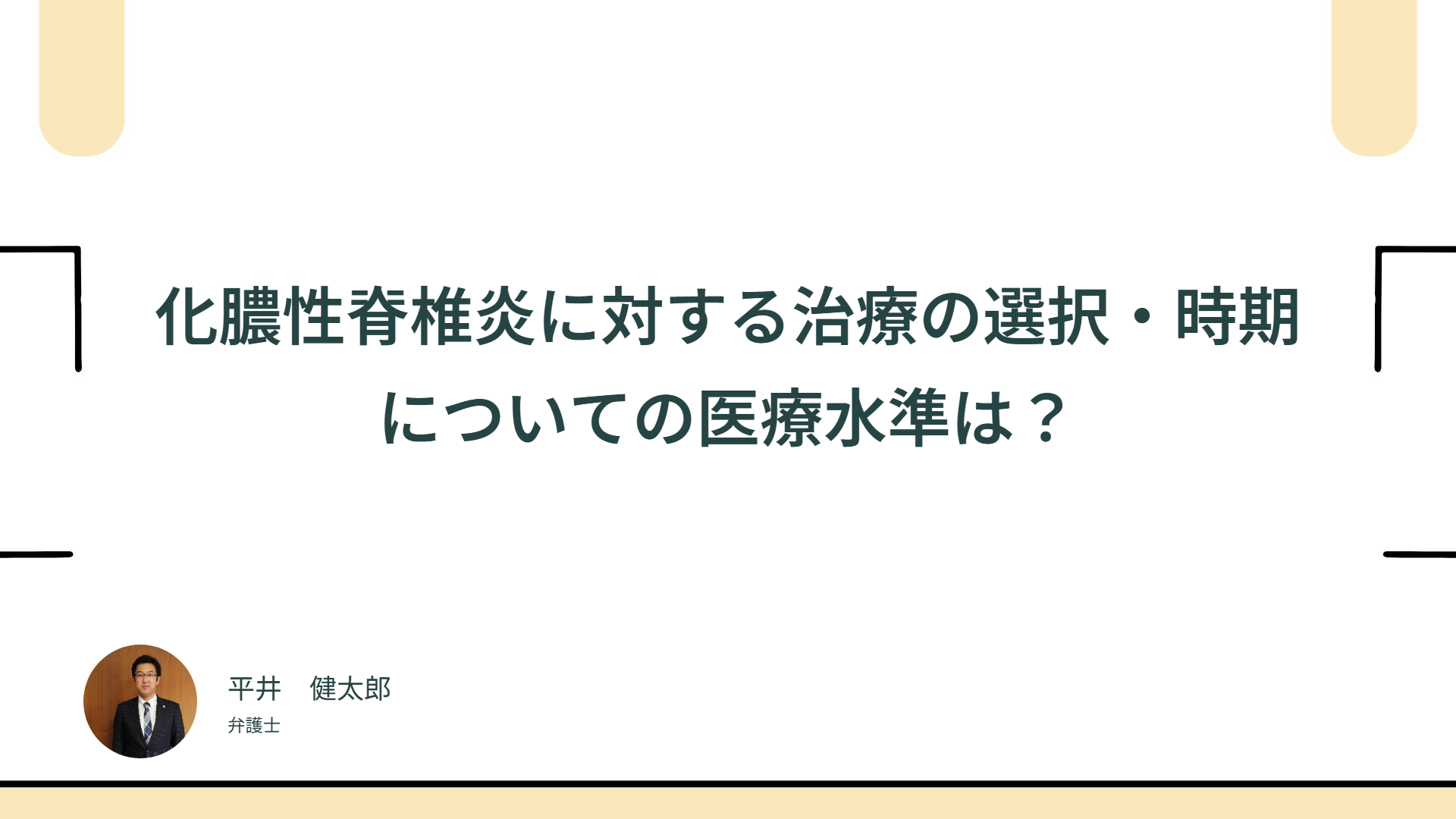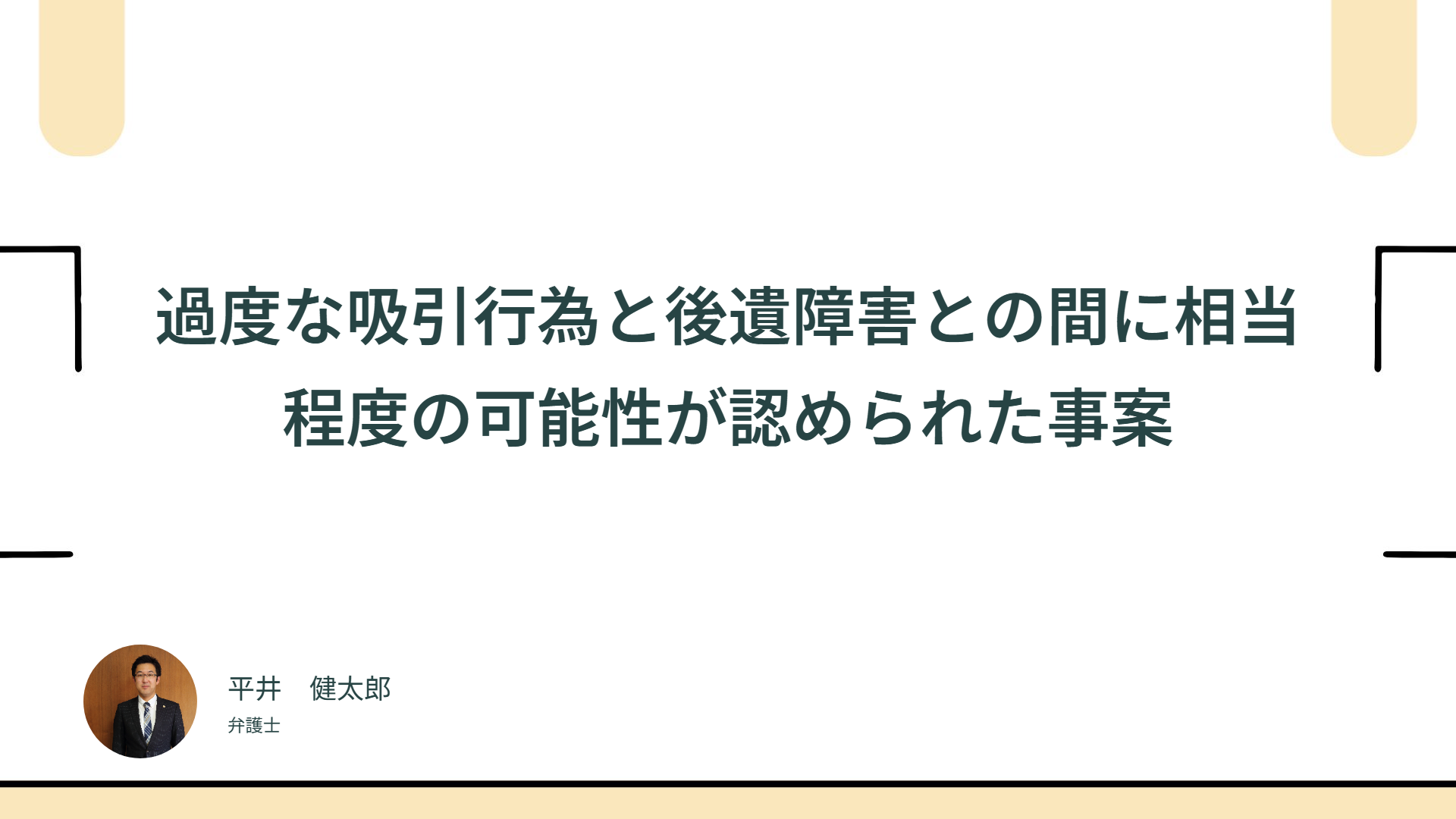クリステレル圧出法を併用して吸引分娩を試みた選択が違法と判断された事案
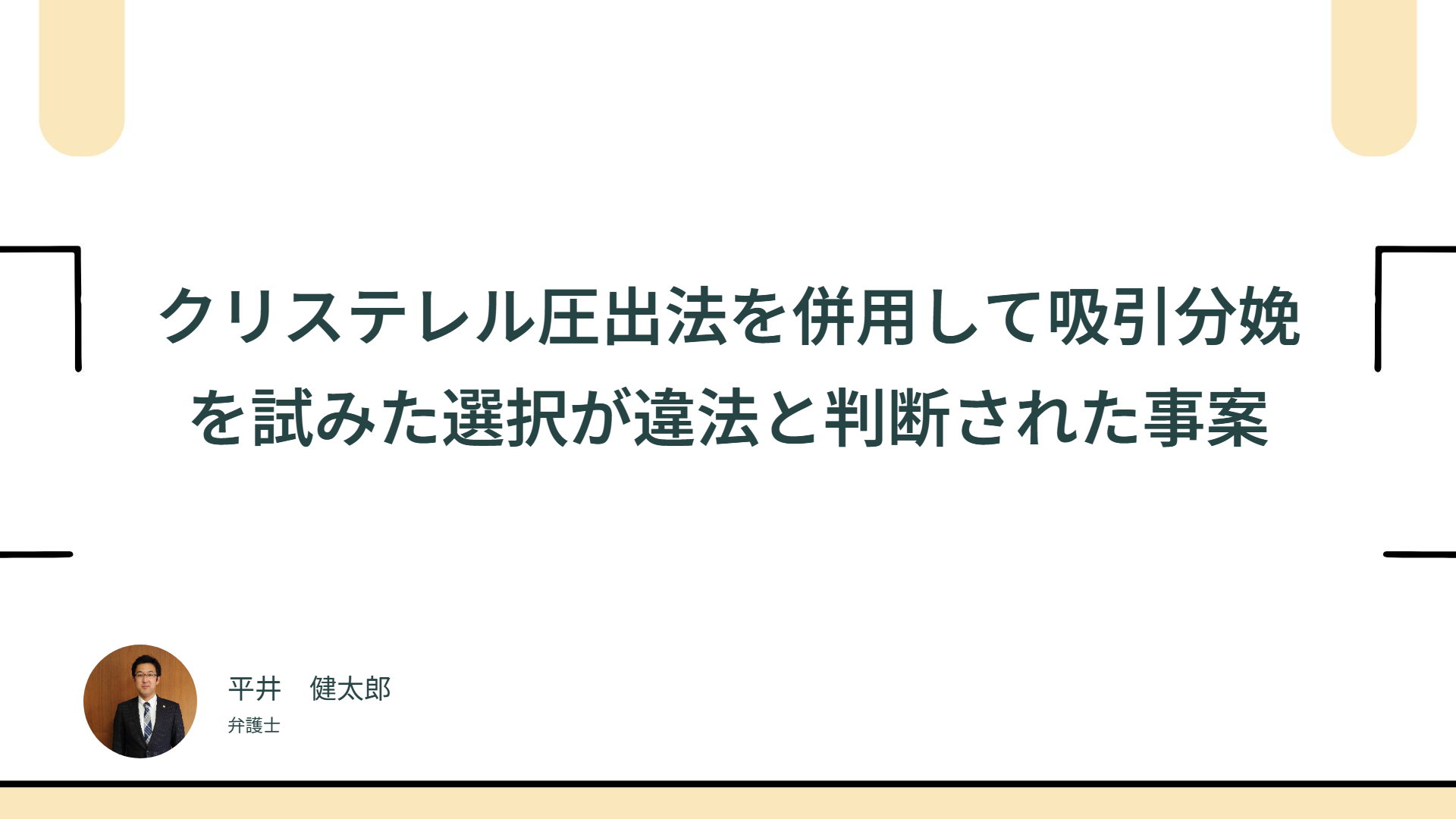
クリステレル圧出法を併用した吸引分娩の実施した後、帝王切開により娩出したが子が出生後に死亡した事案(福岡高裁那覇支部平成15年3月18日判決、判時1884号52頁)
【争点】
- 陣痛促進剤を使用したことについての義務違反ないし過失
- 陣痛促進剤を使用する際の説明義務違反
- 分娩監視中の診療行為についての義務違反ないし過失
- 急速遂娩術の実施についての義務違反ないし過失
- 因果関係
- 不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効
- 予備的請求に関し、一郎が第一審被告に対する債務不履行に基づく損害賠償請求権を取得したか
- 損害額
【判旨+メモ】
争点①について、用いる薬剤に関する説明義務の考え方が示されている。
一般的に、医師が診療行為を行うに際し、用いられるあらゆる薬剤について、これによって生じる可能性のある副作用につき患者に対して説明すべき診療契約上の義務があるということはできず、医師がこのような副作用につき患者に対して説明すべき義務を負うか否かは、当該診療行為を行う必要性の有無、程度、当該診療行為によって副作用が生じる危険性の程度(頻度)、その重大性、当該患者の当該診療行為についての知識・経験の有無、程度、当該診療行為が一般的に広く行われているものであるか、それとも、先駆的又は特殊な診療行為であるか、副作用について説明することにより当該患者の状態に悪影響を及ぼす可能性の有無、当該患者の関心の有無、程度等の諸事情を総合的に考慮した上で個別具体的に判断すべきである。
この判旨にもあるとおり、薬剤投与において副作用の説明がなかったからといって、直ちに過失が認められるわけではなく、様々な当時の事情を考慮して義務の有無が判断されることになる。
その際、どのような事実を考慮すべきか、具体的に挙げられているため、他の裁判においても主張立証の参考になると思われる。
本件では、以下のような事情が考慮され、過失は認められなかった。
これを本件についてみるに、(中略)、今回の分娩も急速産になる可能性が高かったというのであるから、医師が分娩の開始から最後まで確実に付き添うことができるように分娩誘発を行う必要性は相当程度高かったと認められる上に、(中略)、分娩開始時から医師が付き添い、分娩の状況を常時監視して不測の事態に備えることにより対処しうると考えられること、(中略)、平成四年当時において格別特殊な診療行為ではなく、第一審原告花子自身も第二子出産の際には他病院で分娩誘発を経験していたこと、(中略)、格別これに対して異見を述べたり反対の意思を表明したりしたことはなく、(中略)、B山医師が第一審原告花子に対して行った分娩誘発についての説明内容に格別不適切ないし不十分な点があったとは認められず、同医師が、陣痛促進剤を使用した場合に生じうる副作用について第一審原告花子に説明した場合に同人の精神状態に悪影響を及ぼす可能性を危惧し、あえて副作用についての説明をしなかったとしても、これをもって、診療契約上の義務に違反するとか、第一審原告花子の人格権(自己決定権)を違法に侵害する行為であるということはできない。
次に、この件で過失が認められたのは、争点④急速遂娩術の実施についての義務違反ないし過失、である。
簡単にいうと、クリステレル圧出法を併用して吸引分娩を試みたことが問題なかったか、帝王切開すべきでなかったかが問題となっている。
まず、急速遂娩が問題になる場合、急速遂娩を必要と判断できたか否かが争点になることもあるが、本件では問題なかったとされている。
午後二時五〇分及び同五四分に、胎児の高度の遅発一過性徐脈が突然に連続して出現したことから、B山医師は、胎児仮死の症状が発現していると認め、その原因として常位胎盤早期剥離を疑い、急速遂娩が必要であると判断したものであって、同医師のこれらの判断は、いずれも相当であって問題とすべき点はない。
しかし、吸引分娩に関する医学的知見を整理したうえで、本件ではそれを満たさないと判断されている。
B山医師は、午後二時五五分に人工破膜を実施した上、経膣分娩により胎児の娩出を試みることとし、児頭に吸引カップを装着し、第一審原告花子に怒責を促し、クリステレル圧出法を併用して吸引分娩を実施したわけであるが、この時点でもいまだ子宮口開大九センチメートルであって全開大とはいえず、児頭もステーションプラスマイナスゼロの位置にあったから、吸引分娩の要約を満たさないか、せいぜい、吸引分娩の要約を最も緩やかに考える見解においてかろうじてその要約を満たしていたに過ぎず、吸引分娩によって容易かつ確実に胎児を娩出することができる状況にあったとは認めがたい。
(中略)
B山医師としては、胎児仮死と判断し、その原因として常位胎盤早期剥離を疑い、人工破膜を実施して出血を確認した午後二時五五分ころの時点で、緊急帝王切開術を施行することを決定すべきであって、同医師が、子宮口開大度及び児頭の位置の点で吸引分娩の要約を満たさないか、かろうじて満たしていたに過ぎない状況下で、胎児仮死の場合には禁忌とされ、また、子宮破裂を生じる危険性もあるクリステレル圧出法を併用して吸引分娩を試みた行為は、診療契約上の義務違反ないし過失があるというべきである。
その他、死亡との因果関係も認められ、患者側の請求が認められている。
本件のような事案では、まずはガイドラインを参照し、急速遂娩の必要姓の有無、手技の適応の有無など丁寧に当てはめることからはじめ、その後に例外的な事実の有無など検討していくことになると思われる。