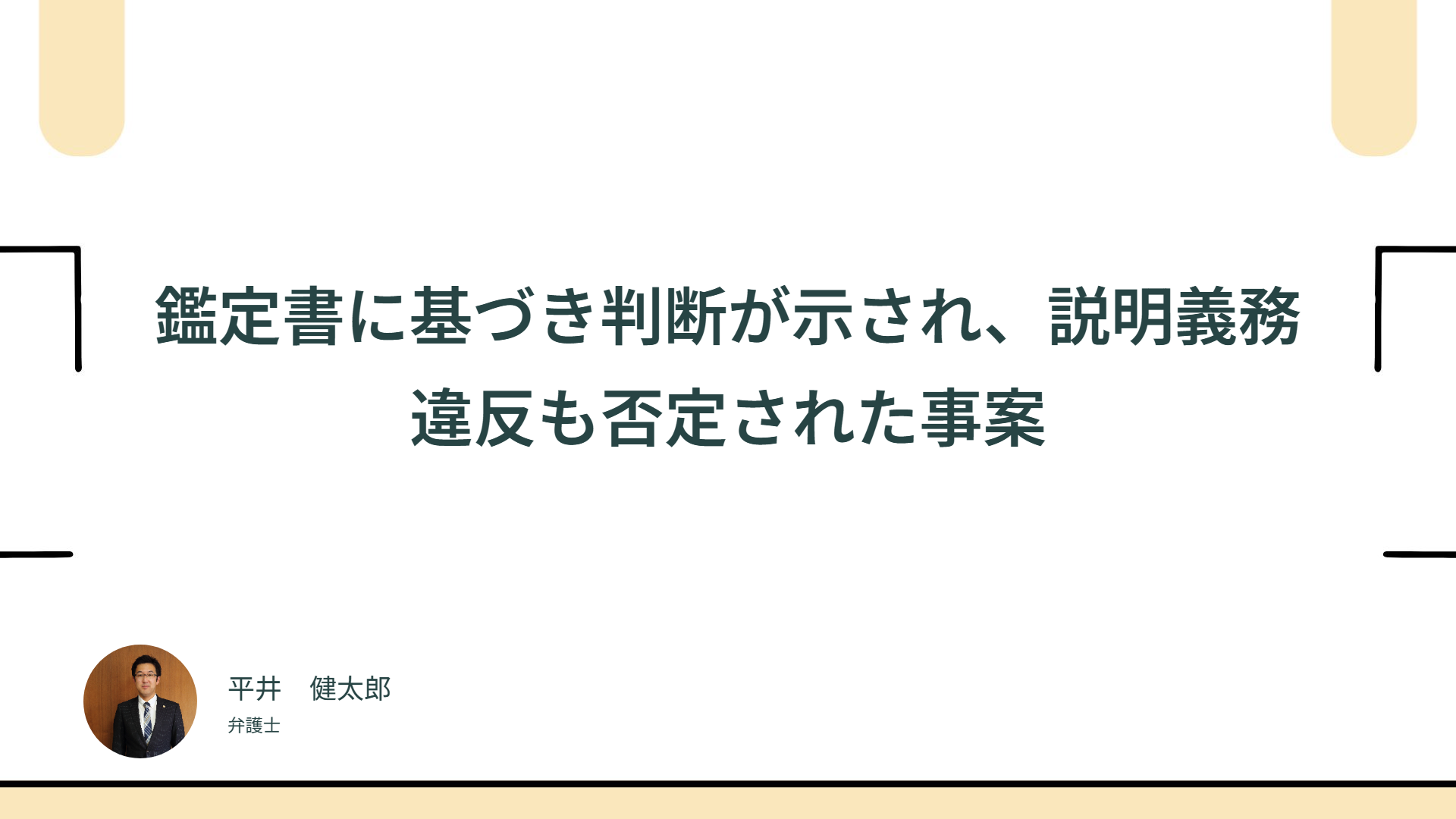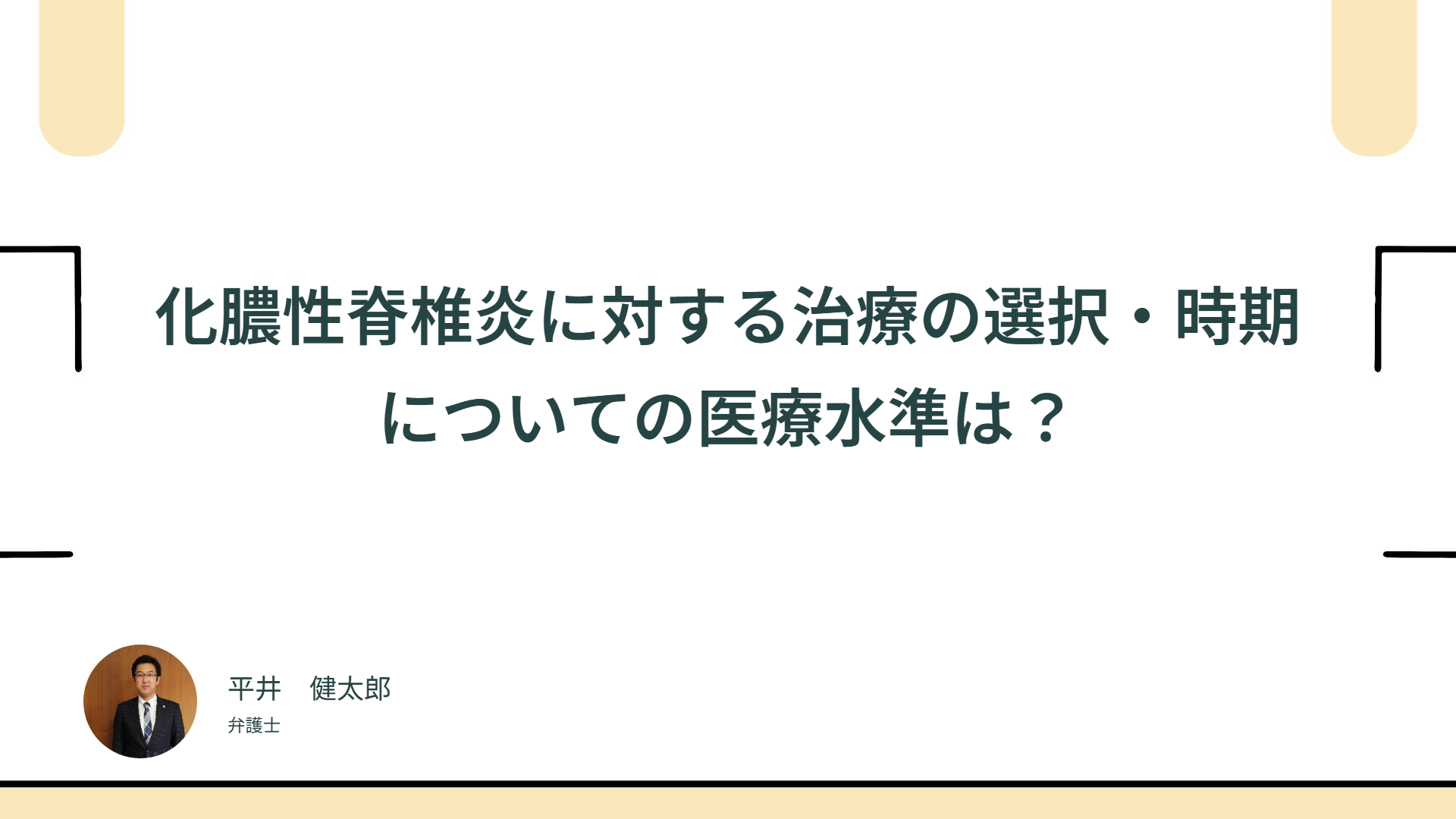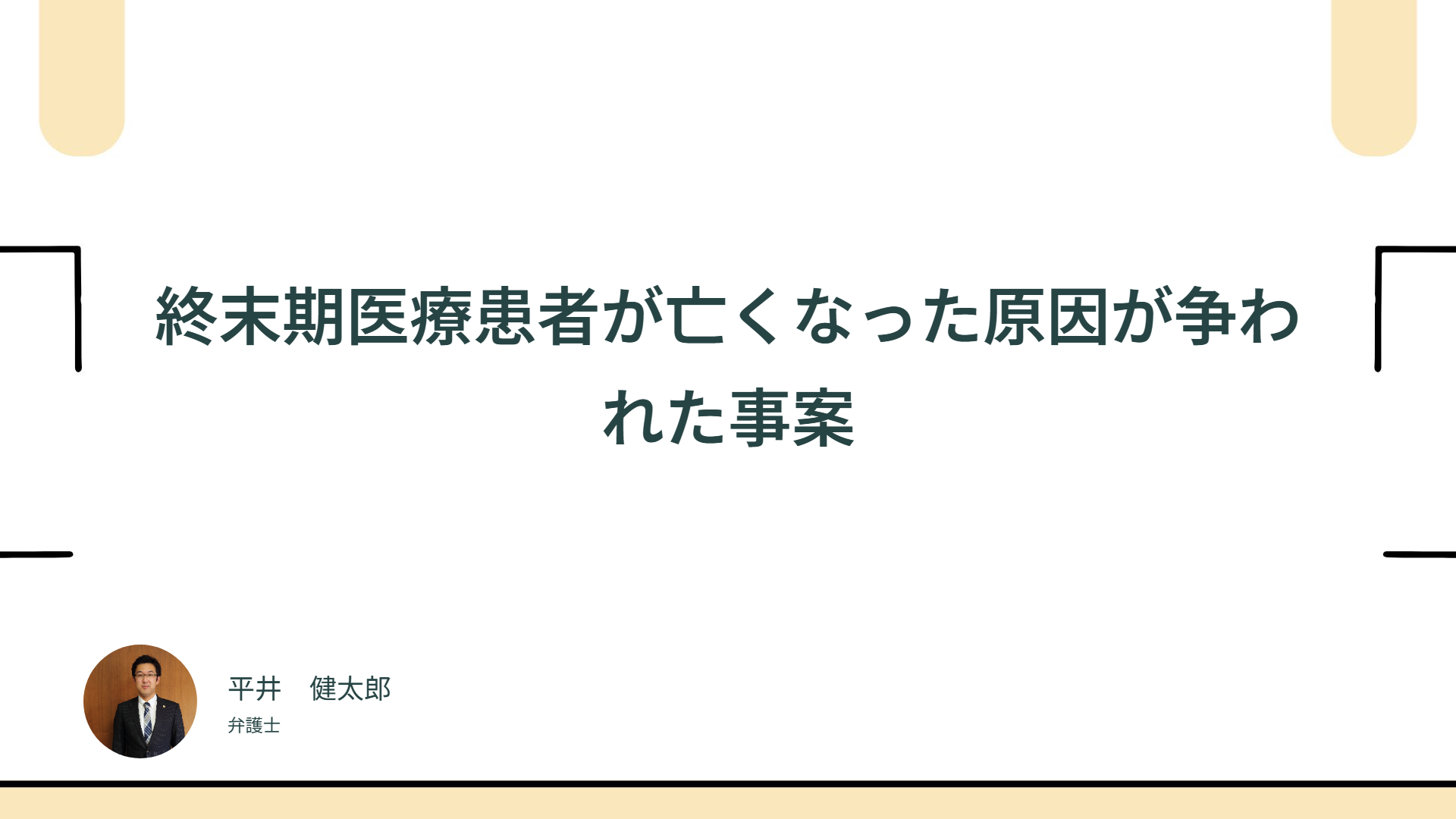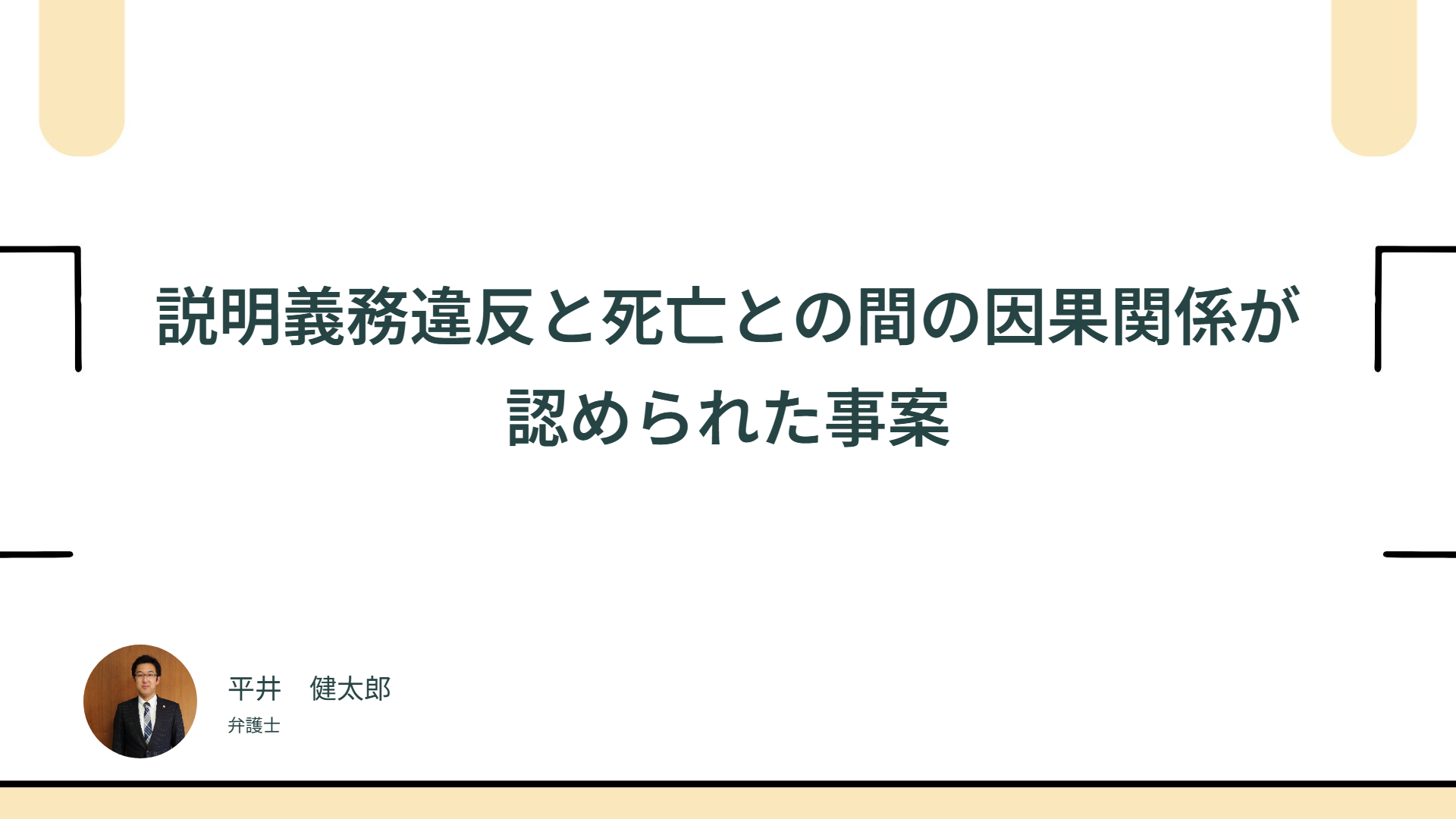手術説明で不正確な情報を説明した場合の法的責任は?
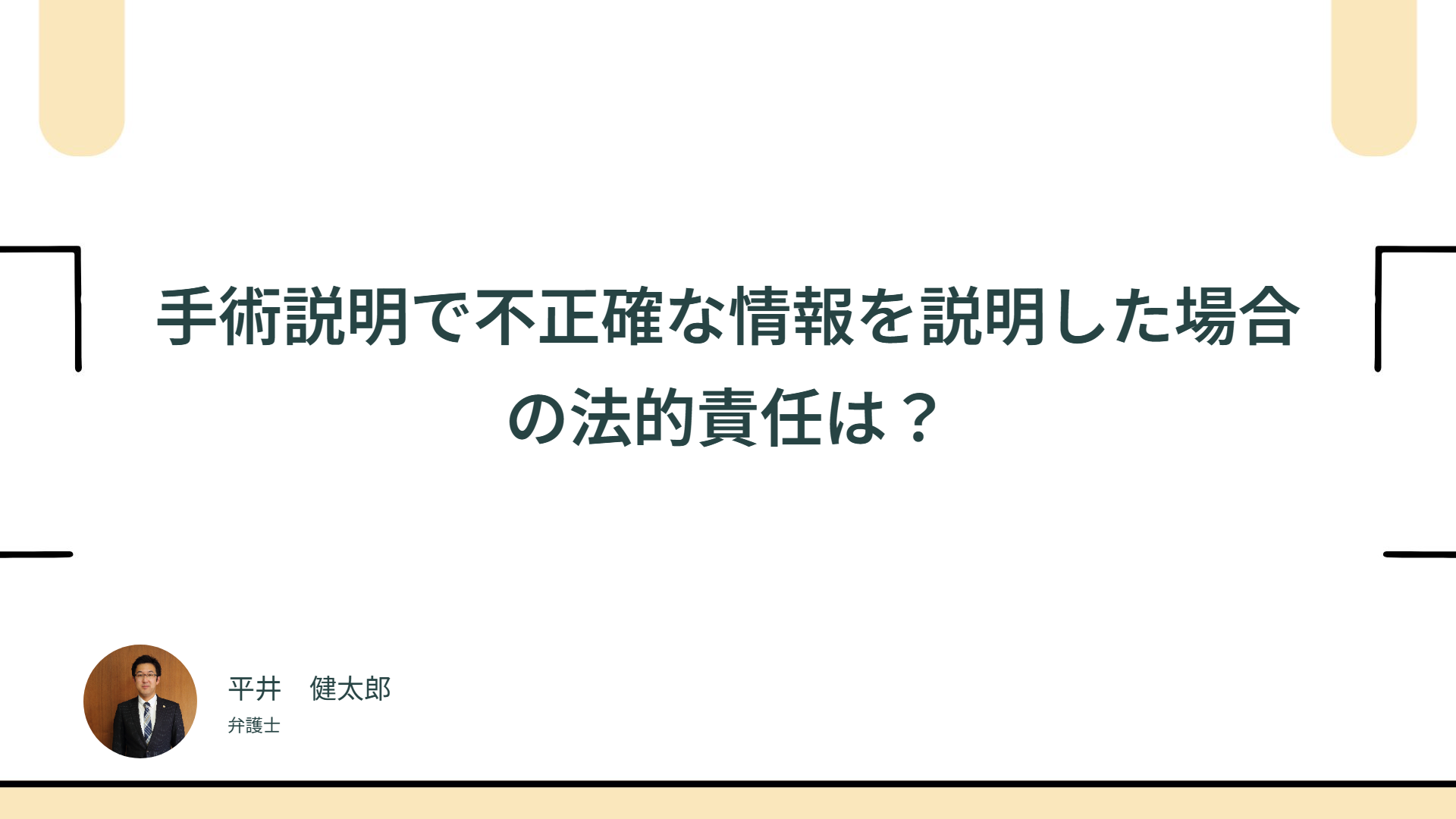
右前頭葉の脳動静脈奇形(AVM)に対する手術の前処置としてAVMへの血流を遮断する塞栓術が行われ、その後AVM摘出術が行われたが、手術中に硬膜外血腫が確認され、開頭術による除去手術が実施されたが、脳幹障害による左上下肢の不全麻痺および、左前頭葉損傷による高次脳機能障害が残った事案(大阪地裁令和7年3月25日判決、医療判例解説117号73頁)
【争点】
- 本件塞栓術にOnyxを使用してはならなかったか
- 本件AVM摘出術の実施が遅滞したといえるか
- 本件血腫除去術の開頭範囲に誤りがあったか
- 説明義務違反の有無
- 因果関係の有無
- 損害額
【判旨+メモ】
①と②の争点については、以下のように判示され過失は認められなかった。
原告の左中硬膜動脈は、上記添付文書記載の「AVMナイダスへの遠位の流入動脈」には該当しないか、仮に該当するとしても、例外的にOnyxの使用が許されるものであったと解するのが相当である。
(中略)
このような、本件塞栓術前の治療歴、本件塞栓術後の経過観察状況、本件塞栓術から本件AVM摘出術までの具体的な期間を総合的に勘案すると、本件AVM摘出術の実施が遅きに失したと評価することはできない。
争点③も認められなかったが、争点④の説明義務違反は認められている。
AVMは、生命予後を決める最大の因子が出血であり、初回出血における死亡率も後遺障害の残存率も決して低いとはいえず、出血の防止を目的として治療されるものであるから、患者にとって、AVMに対する外科的治療を選択するに当たり、経過観察を選択したときの出血の危険性の大小は、重要な考慮要素になるというべきである。
(中略)
そうすると、医師は、AVMの患者に対し、治療方針の選択に当たり、生涯出血率を説明する際には、上記の計算式に従った正確な説明をすべき注意義務があるといのが相当である。
重要な考慮要素について正確な説明をすべきとし、本件では、「原告の生涯出血率はほぼ100%である旨の説明をしたものであり、この生涯出血率の説明には明らかな誤りがあるといわざるを得ないから、この点に説明義務違反があったというべきである。」と判示して、明らかに誤った説明があったことを捉え、違法と判断しています。
損害については、人格権としての自己決定権侵害(「意思決定に必要な医療情報の提供を受ける権利」)が認められ、以下のように金額が算定されています。
その慰謝料額は、説明当時、AVM摘出術は必ずしも緊急性が高い手術であったといえないこと、説明義務違反の態様は、不正確な生涯出血率を積極的に説明したというものであること、AVM摘出術には重大な合併症が想定され、実際、原告には左上下肢不全麻痺、高次脳機能障害という重大な後遺障害が残遺したこと、その他本件に現れた一切の事情を考慮すると、200万円を認めるのが相当である。
説明不足の事案が多い中、「不正確な生涯出血率を積極的に説明したというものであること」とあるように不正確な情報を積極的に説明したことを損害の算定で評価した点に特徴があると考えられる。