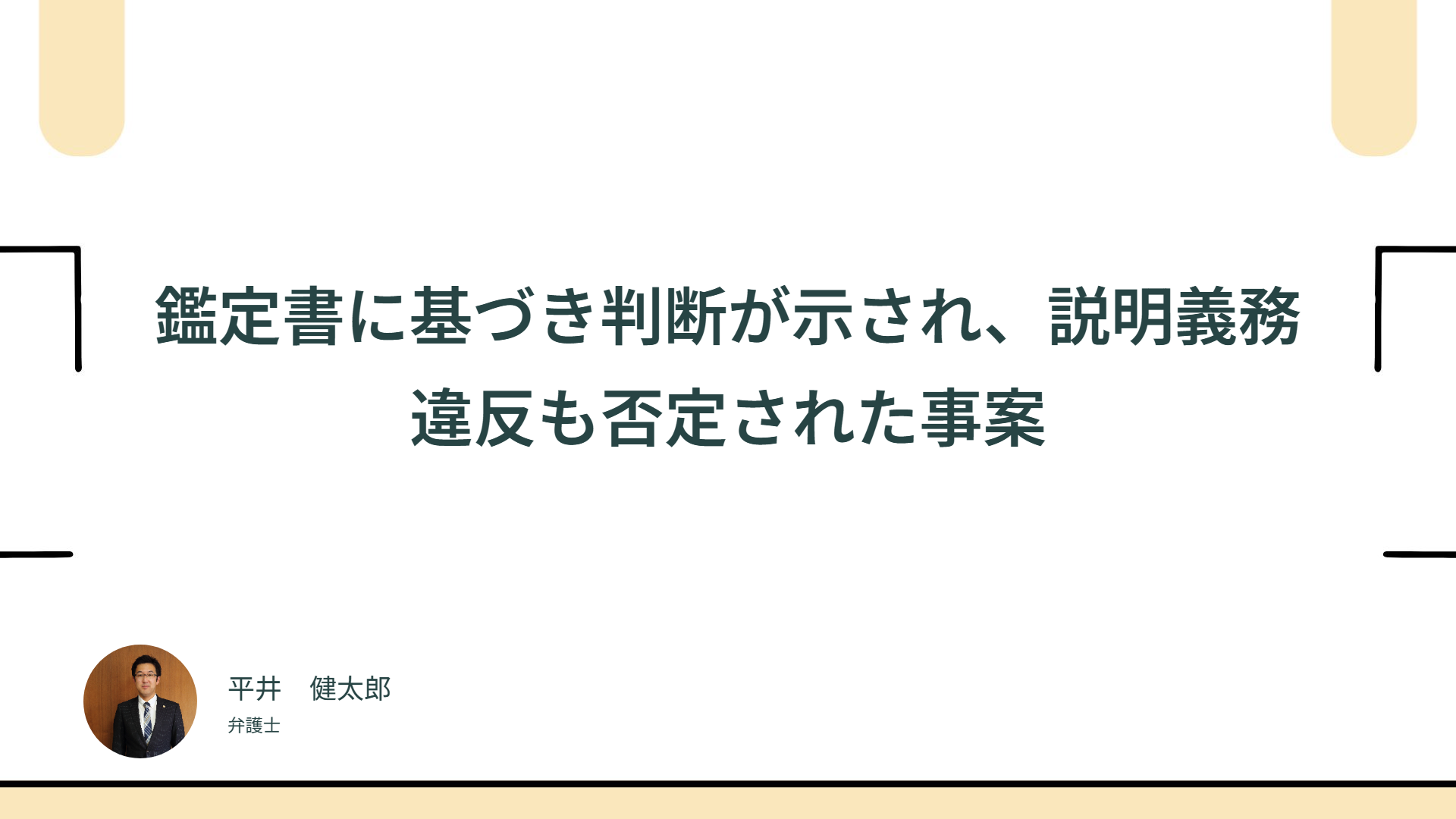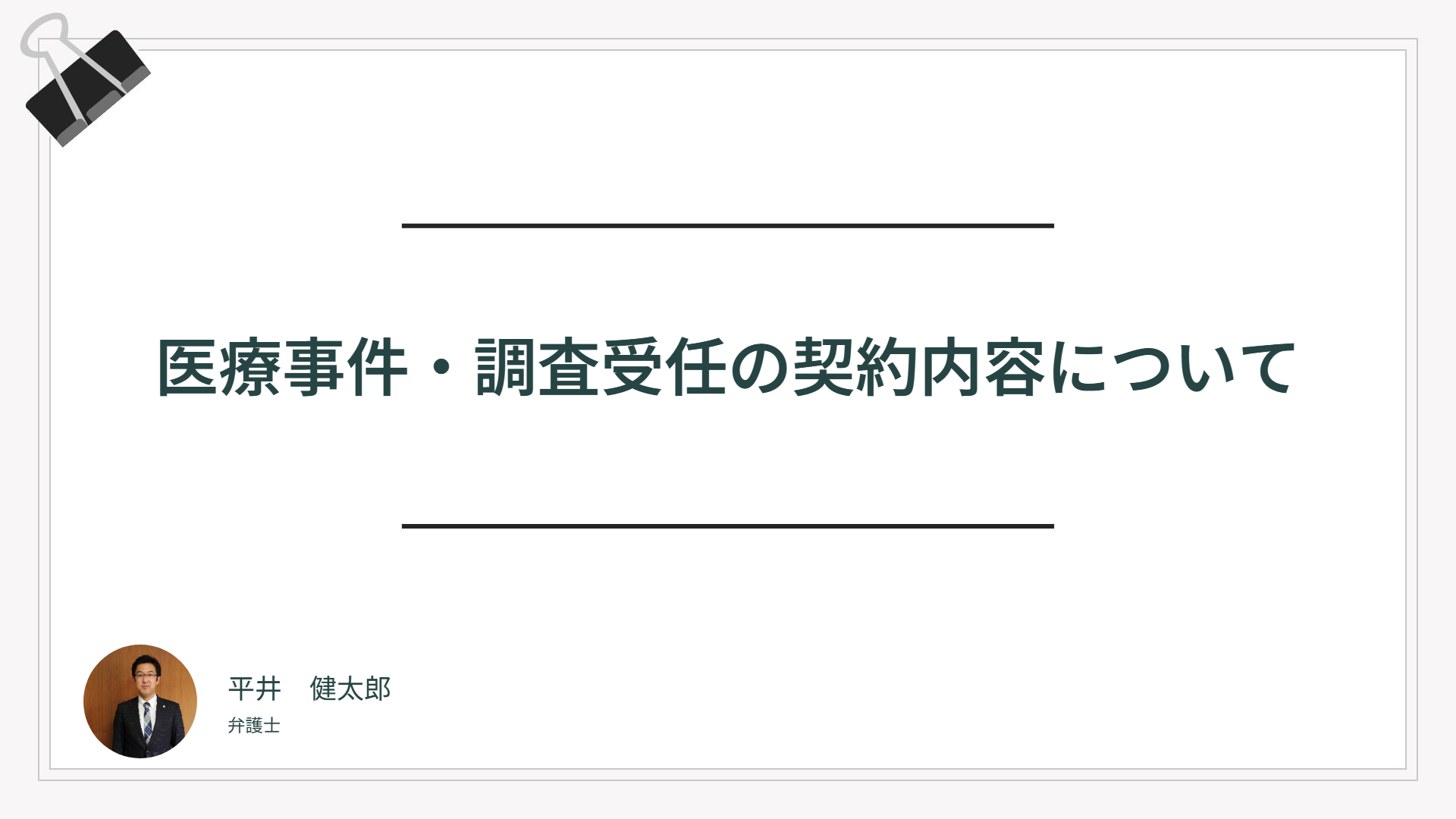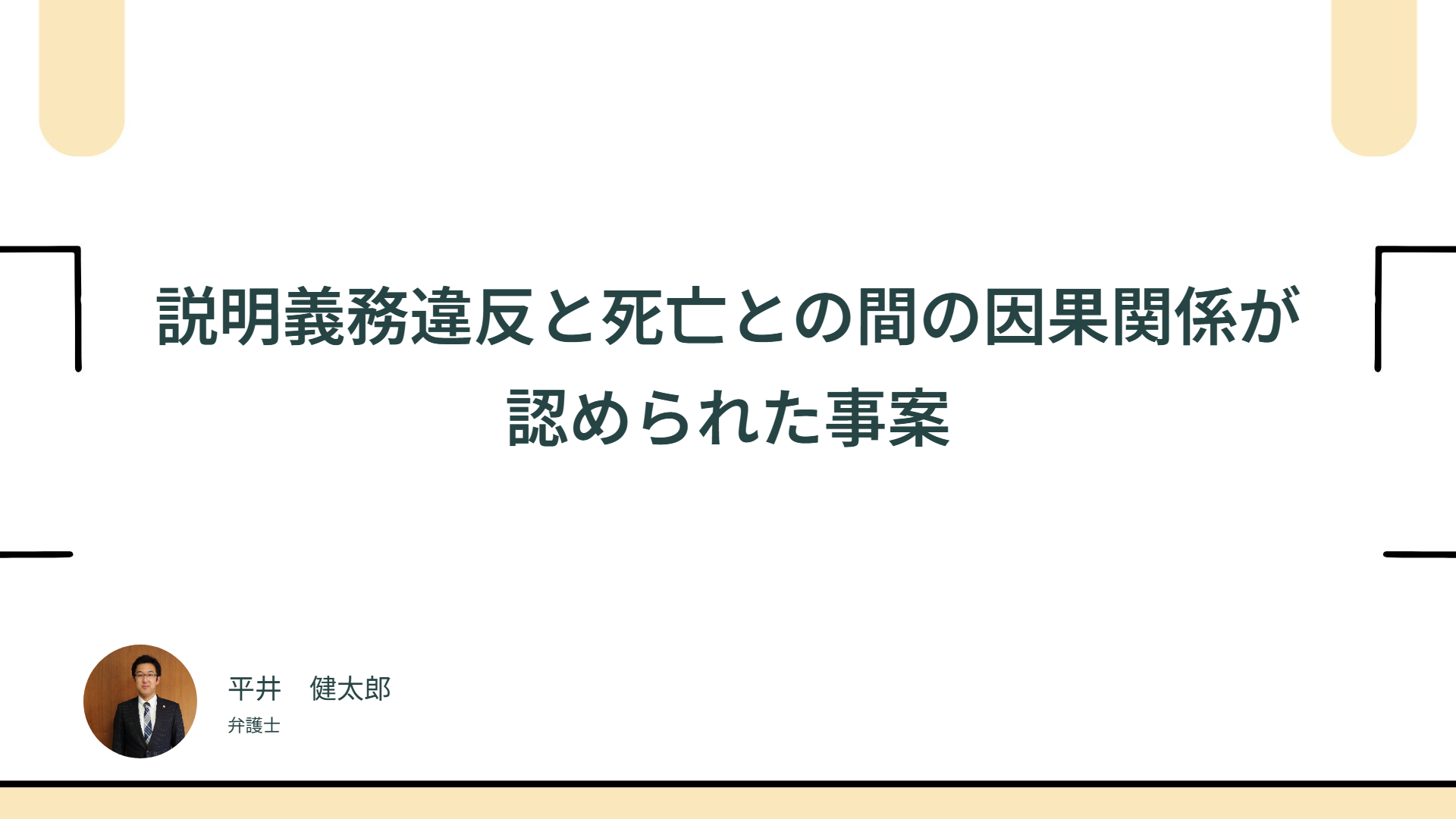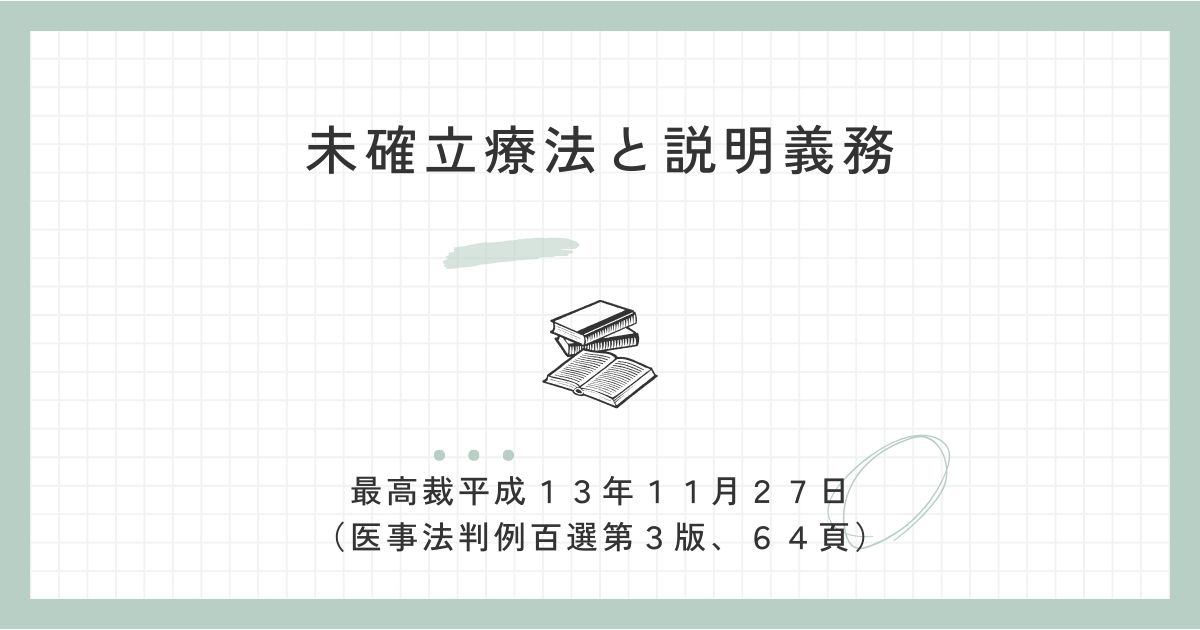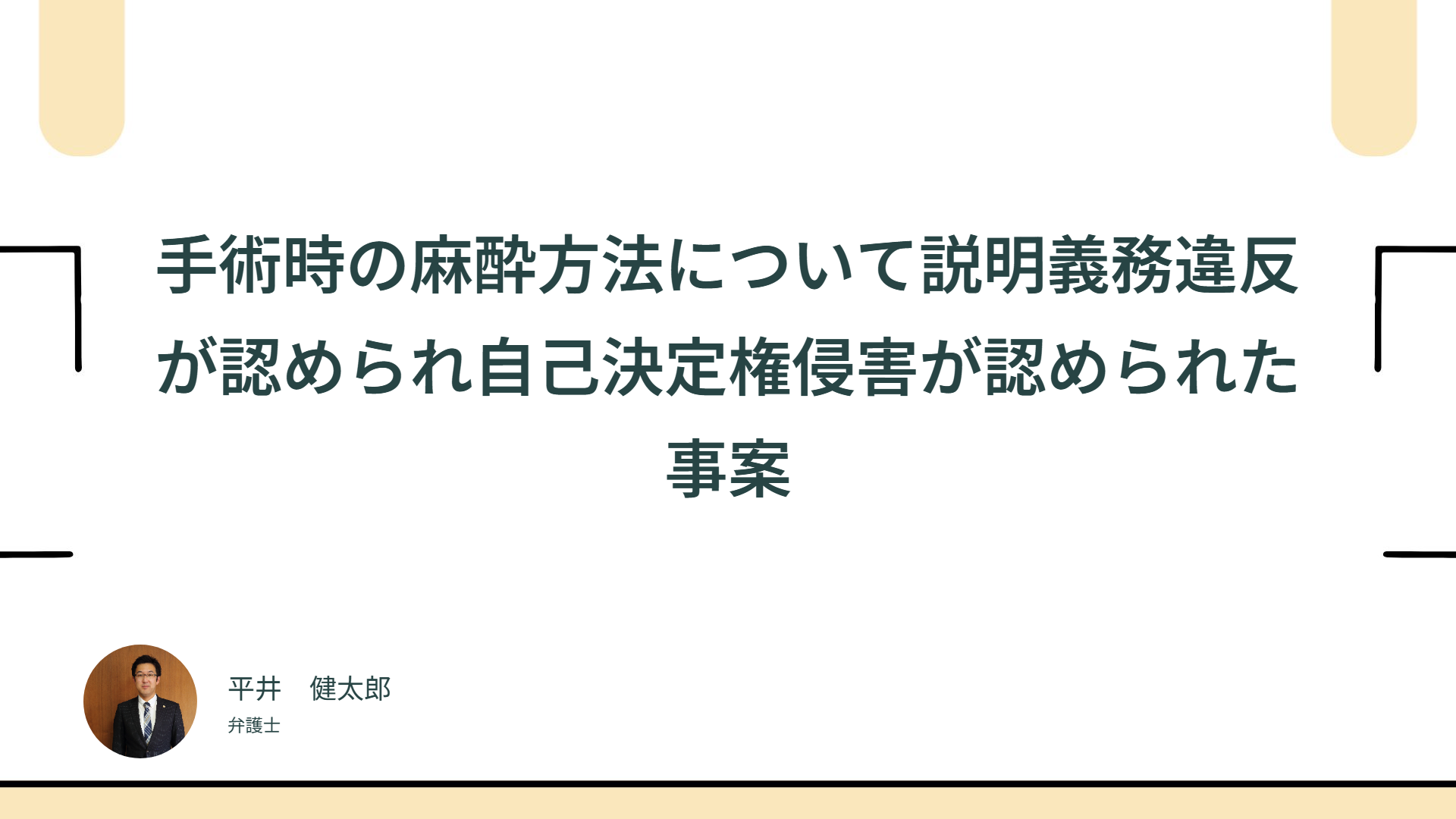静脈留置針の穿刺によって右橈骨神経を損傷しCRPSを発症したといえるか?
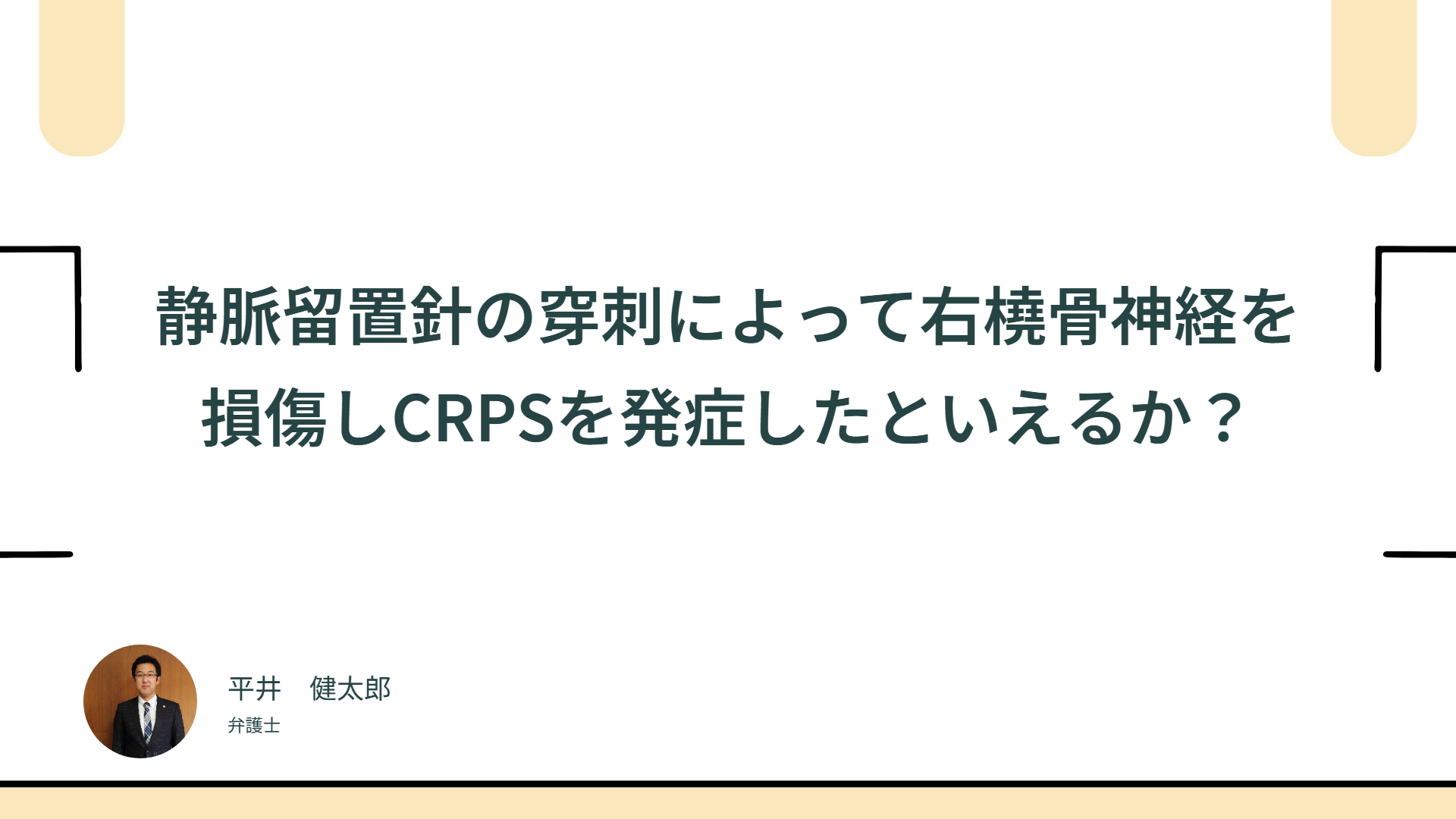
インプラント埋入術に先立つ静脈留置針の穿刺によって右橈骨神経を損傷させられCRPS(複合性局所疼痛症候群)を発症し右前腕を中心に右半身の痛みや手指のしびれ等の後遺障害が残ったとして損害賠償を求めた事案(東京地裁平成31年3月27日、ウエストロー・ジャパン)
【争点】
- 本件穿刺部位は,右橈骨茎状突起から中枢側に12cm未満の位置であったか否か。
- 歯科医師が,静脈路を確保する目的で静脈留置針を穿刺する場合,橈骨茎状突起から中枢側に12cm未満の位置で行うべきではないという注意義務は,本件手術当時の医療水準であったか否か。
- 被告は,右橈骨神経を損傷させられ,CRPS(複合性局所疼痛症候群)等を発症したか否か。発症した場合,これと本件穿刺との間に相当因果関係が認められるか否か。
- 被告の損害
【判旨+メモ】
被告は,本件手術から3日後の平成27年2月23日に後医であるB医師が作成した本件診療情報提供書中の「右手関節橈側に針の刺入点を認めました。」という記載について,被告の主張に沿うものとして援用する。
しかしながら,通常は小児・乳幼児に用いられる24G(外径0.55mm)という細い針を,体毛が少なくない被告の腕(乙A14)に刺入した跡が,それから3日後に外観上判別できたか否かについては,疑問がないわけではない。(中略)また,他方で,D医師作成の同年6月11日付け診断書(乙A5)には,本件穿刺部位について「右前腕橈側中央よりやや遠位」という記載があり,この表現は,被告主張部位より,むしろ原告主張部位と符合するものである。そして,この記載をも併せ考慮すると,被告が援用する本件診療情報提供書中の前記記載は,B医師の現認に基づくものではなく,被告の申告に基づくものである可能性が高いと考えられ,また,本件穿刺部位についての被告の説明内容が変遷した可能性がある。
次に,本件診療情報提供書中の「右手関節橈側」という表現は曖昧であり必ずしも一義的とはいえない。(中略)
この点に関し,B医師は,本件回答書において,「カルテには手関節橈側に刺入点ありと記載あり。茎状突起より7cm以内の距離と考えます。それ以上近位ですと前腕と記載すると考えます。」と記載する。
しかしながら,上記のとおり,本件ガイドライン上は,「手関節橈側」には橈骨茎状突起から中枢側に12cm以上離れた部位も含まれることからすると,B医師が,本件回答書において,「手関節橈側」は橈骨茎状突起から中枢側に7cm以内の範囲であり,それ以上近位であれば「前腕」と記載するはずであるとする根拠は必ずしも明らかではない。また,本件回答書に記載された橈骨茎状突起より「7cm」以内という数値が,本件回答書の作成以前から本件で被告が主張してきた数値と完全に一致することに関して,これを単なる偶然と考えることについては,疑問がないわけではない。
以上によれば,本件診療情報提供書及び本件回答書の各記載内容については,直ちにこれを客観的かつ合理的で信用性の高いものとして採用することはできない。
穿刺部位の立証として、客観的証拠である診療情報提供書の記載を根拠としたが、記載内容の作成経緯や用語の意味が一義的といえるかという観点で評価され、結論として、信用性が高いとは認められなかった。
写真等の客観的証拠があれば証拠として提出していると思われるが、判決文で診療情報提供書の記載が問題とされていることからすると、当時の状況を明確に記録した証拠がなく、患者側は、手元にある診療記録から根拠を見つけ、主張したものと考えられる。
教訓としては、診療記録は、医師や看護師が知覚したものを記憶し表現しているものであるから、この過程のどこかで誤りであったり、記憶が薄れる点があったりするおそれがあることはやむを得ない(改ざんとは異なる)。
そのため、治療当時の身体の状況などは、医療事故のためではなく、例えば治療経過を記録にする目的でも構わないので、写真などで記録化していれば問題が起きた際に検証しやすくなる。
このように,A歯科医師の証言は,一貫している上,その有する医学的知見に立脚した具体的かつ詳細なものであるし,また,本件訴訟においては,橈骨茎状突起から中枢側に12cm未満の位置に穿刺すべきではないという知見が本件手術当時の医療水準であったか否かという点が激しく争われており,原告はこれを否定する旨の主張をしているところ,A歯科医師は,自己や原告に不利益であるにもかかわらず,躊躇や逡巡なく明確にこれを肯定する旨の証言をしており,証言態度に誠実さや真摯さが認められるから,その信用性は高いというべきである。
A医師というのは病院側の医師であるが、その医師が、病院側の言い分に合わせるのではなく、味方である病院に不利になるおそれのある証言をしたことが、裁判所からすると信用できる証言という評価に繋がっている。
一般的に証言は、自分側に不利益な証言をした場合、その証言は信用できると評価されるというルールのようなものがある。わざわざ裁判所に来て自分に不利なことは普通言わないよね、という経験則が根底にあります。
本件穿刺部位は被告主張部位であると認定するには合理的疑いが残るといわざるを得ず,本件穿刺部位が右橈骨茎状突起から中枢側に12cm未満の位置であったと認めることはできない。
被告は,本件穿刺部位が右橈骨茎状突起から中枢側に12cm未満の位置であったことを前提に,原告の履行補助者であるA歯科医師に注意義務違反があったと主張するところ,その前提が認められないことは上記説示のとおりであるから,A歯科医師の注意義務違反を認めることはできない。
したがって,その余の点について判断するまでもなく,原告に診療契約の債務不履行責任が成立する余地はない。
本件では、穿刺部位について、患者側の主張は認められなかったため、争点②以降については判断されなかった。
患者側としては、病院側が主張する穿刺部位を前提に過失を構成することを考えることもあるが、その場合、注意義務を裏付ける医学的知見が存在しないことも多く、結果として、本件のように穿刺部位から争わないといけない事案は多いと思われる。