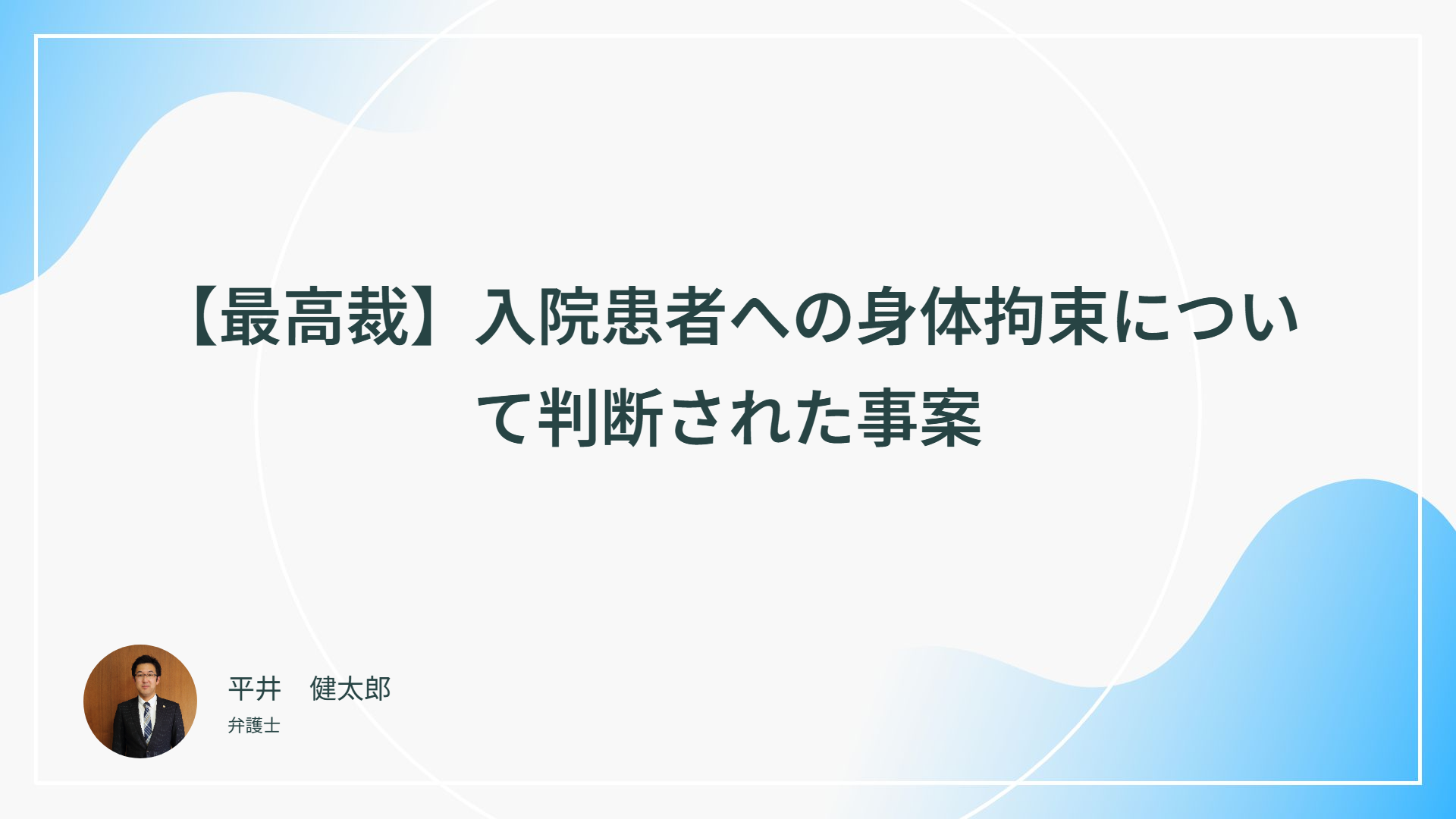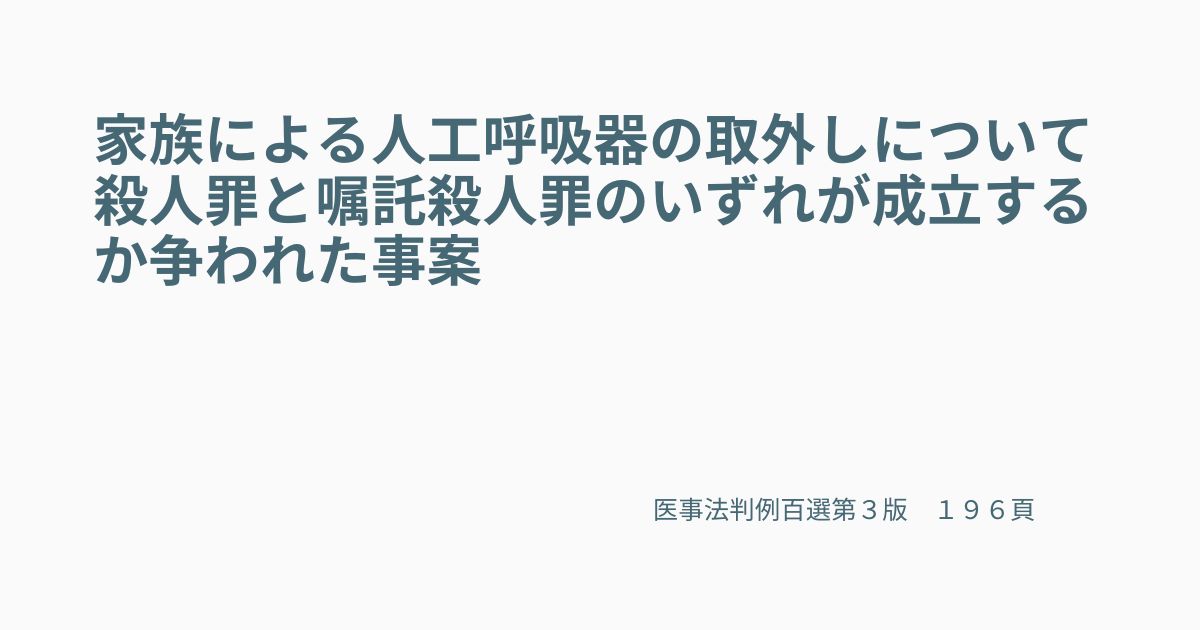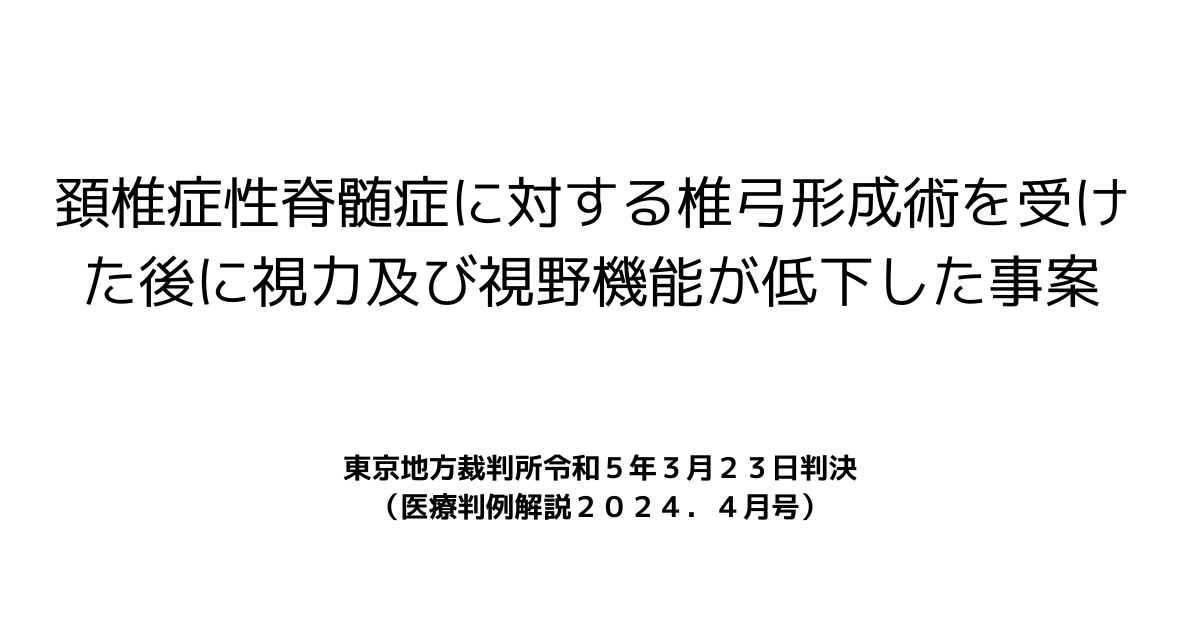化膿性脊椎炎に対する治療の選択・時期についての医療水準は?
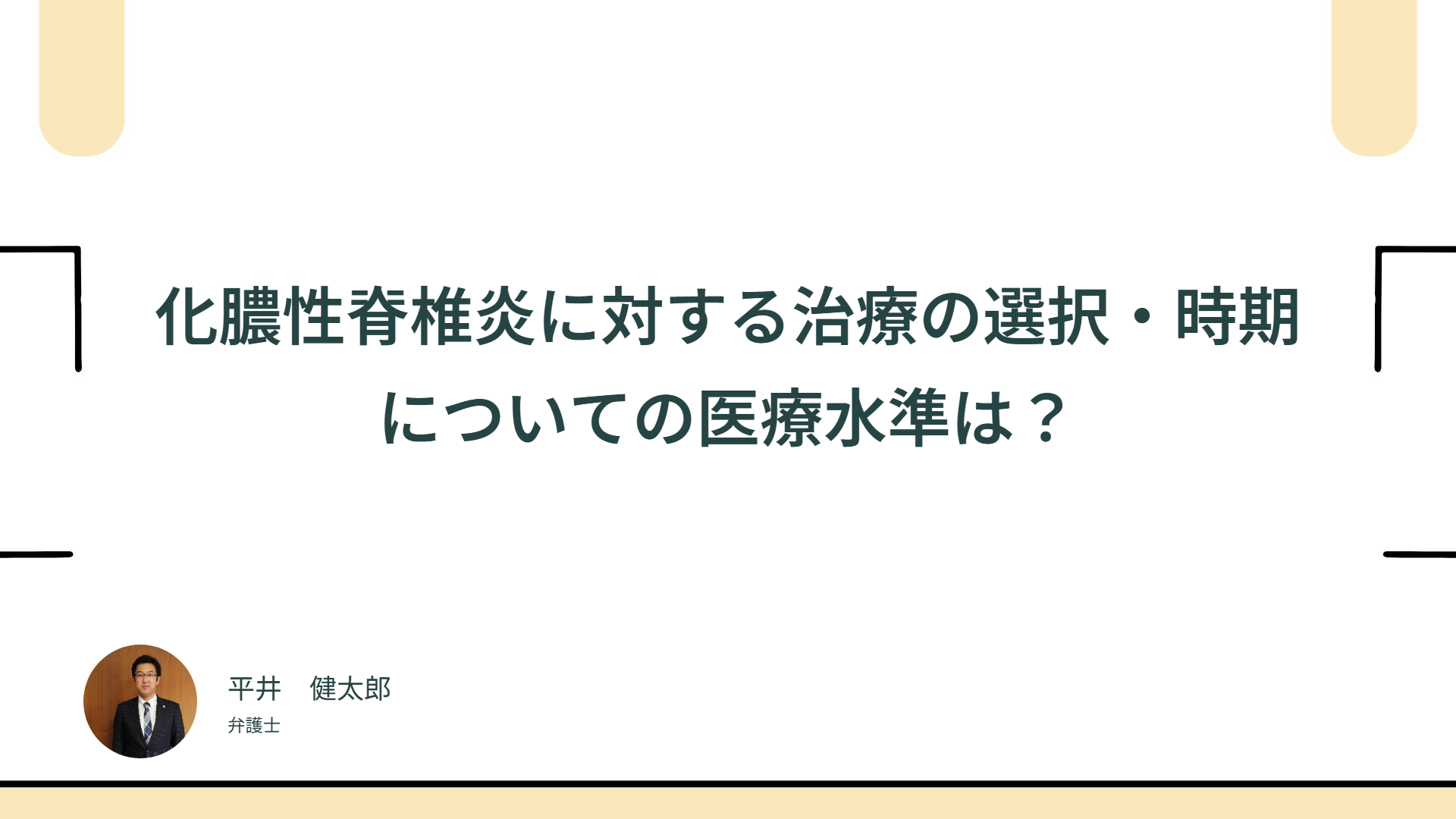
頚部痛を訴えて入院していた患者について、化膿性脊椎炎に対するMRI検査や緊急手術を実施されず、頚椎前方除圧固定術を受けた後に四肢麻痺が確認された事案において、MRI検査・緊急手術実施義務が争われた(名古屋地裁令和6年10月18日判決、医療判例解説117号42頁)
【争点】
- 平成29年6月20日のMRI検査実施義務
- 平成29年6月21日の緊急手術実施義務
- 前記(1)(2)の義務の違反と原告の後遺障害との間の因果関係
- 損害の発生及びその額
【判旨+メモ】
原告が指摘する同日時点における頸部及び両上肢の痛みは、頚椎症による神経根圧迫の症状であった可能性が高く、化膿性脊椎炎又は硬膜外膿瘍としての進行性の神経症状又は運動麻痺によるものであったと認めることはできない(証人A医師)。(中略)以上によれば、同日の時点において、原告に進行性の神経症状、運動麻痺又は膀胱障害があったと認めることはできない。
過失を争う場合、双方で前提事実の認識に争いがなく何らかの医療行為をすべき義務が争われる場合と、Aという事実を前提とすれば過失があるという主張とAという事実がないから過失もないという争われ方をすることがある。
本件では、MRI実施義務の前提として、「進行性の神経症状、運動麻痺又は膀胱障害」の有無が争われているので、分類するとすれば後者ということになるだろう。
過失を検討する際には、特に裁判で争点を正確に捉えるためには、過失の前提となる事実が争われているのか、事実に争いがなく評価が争われているのか、区別して整理する必要がある。
化膿性脊椎炎に対する治療の選択及びその実施時期については、本件当時、ガイドライン等統一された見解は示されておらず、医学文献の中には、運動麻痺があれば緊急手術を要する、脊髄障害が進行性の場合は緊急手術の適応であるなどといった、原告の主張に沿う記載をその一部に含むものが存在するが、これらの文献も、全体の記載からすると、運動麻痺又は進行性の脊髄障害(神経障害)があれば、他の初見又は臨床経過等に関わらず無条件で、直ちに手術を実施することを義務付けるものであるとまでは解されない。他の文献の内容をも併せ考えると、本件当時の医療水準としては、化膿性脊椎炎に対する手術の実施及びその時期は、麻痺の重篤性、神経症状の進行及び保存療法への抵抗性などから医師が判断するものであるとの限度で認めることができるにとどまるというべきである(証人A医師)。
(中略)
以上によれば、本件当時、原告が主張する医療水準、すなわち、原告が主張するような一定の場合に、化膿性脊椎炎の緊急手術又は硬膜外膿瘍の確定診断(ひいては緊急手術)を医師に義務付けるような医療水準が確立していたと認めることはできないから、原告の主張は、この観点からも採用することができない。
ざっくりとまとめると
- ガイドラインが存在しない ⇒ 統一された見解はない
- 文献の一部に記載 ⇒ 全体を読めば評価が変わる
- よって、医療水準は確立していない
このような判断からすると、裁判所が、ガイドラインの存在を重要視していることがわかる。
ガイドラインの存否、記載内容が、過失判断(医療水準の判断)において非常に重要な証拠と位置づけられているといえる。
また、患者側代理人としても、文献の一部を指摘した場合あっても、当然に文献の全体を読んだうえで証拠提出しているのであって、読み方・評価の仕方が代理人と裁判官との間でズレがあったということだろう。
このように「評価」の仕方で結論が変わることはありますが、裁判官がどのように評価するかは最後までわからないこともあり、裁判の見通しを考えるうえで予測が難しい部分です。