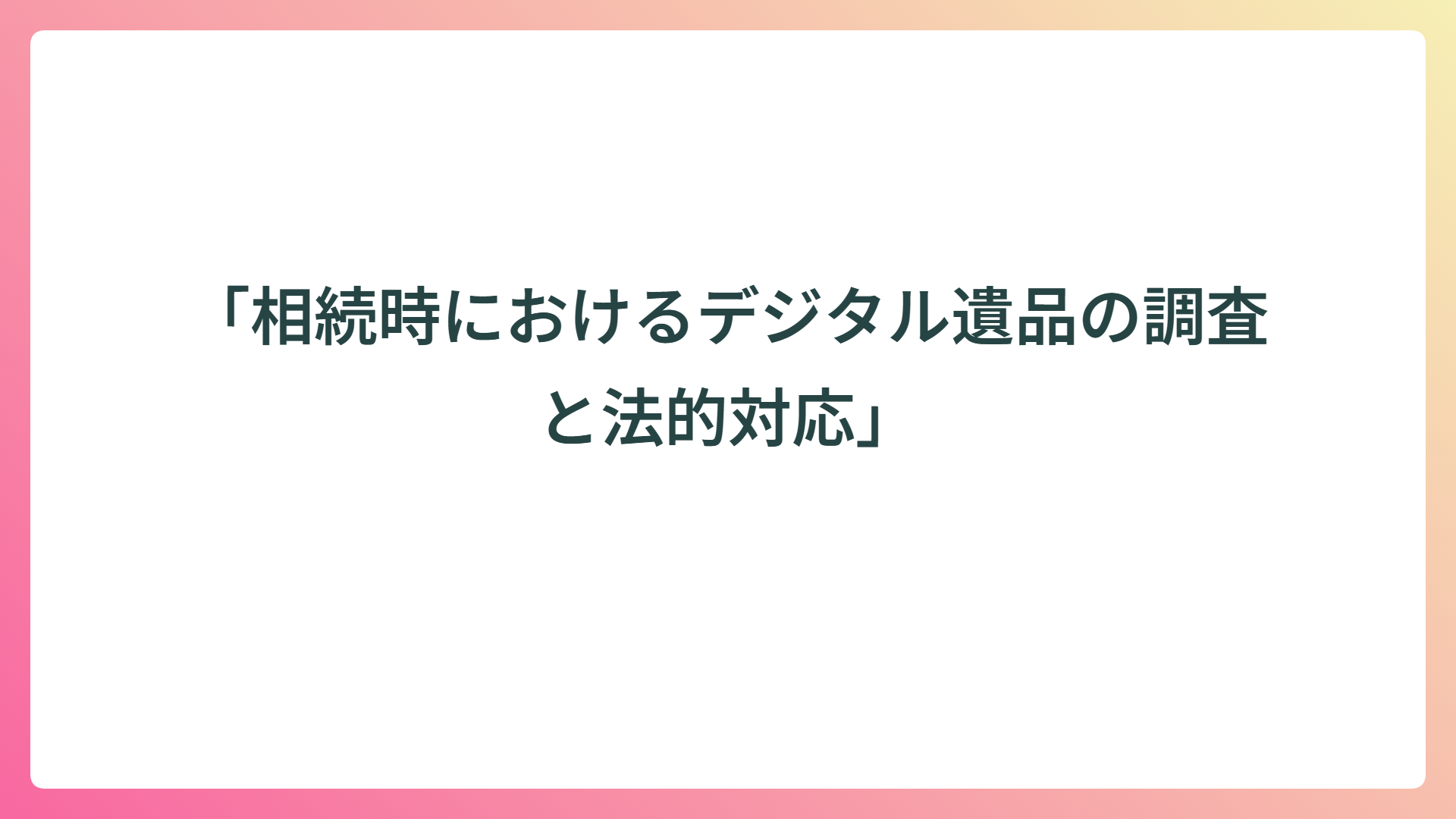kentaro
「相続時におけるデジタル遺品の調査と法的対応」(家庭の法と裁判 No.55/2025.4)
気になる部分の抜粋
- デジタル遺品は、その性質から、「オフラインのデジタル遺品」と「オンラインのデジタル遺品」の2種類に区分することができる。
- 現実問題として、デジタル機器のログインパスワードが分からず、デジタル機器内の調査を十分に行うことができない事例は多く、今後ますます増加するものと予想される。
- 相続の場面において、特定のオフラインのデジタル遺品の引継ぎを希望する場合には、相続人が引継ぎを希望するデジタルデータが補zンんサれているパソコンやスマホ等のデジタル機器自体の相続を要求する必要がある。
- オフラインのデジタル遺品には所有権を観念できず、他の相続人に対する「引渡し」を請求することは難しいため、遺産分割協議の対象にデジタル機器も含めて処理する等の対応が求められる。
- 一身専属性(中略)を有するケースが多く、相続の可否については、各契約内容において、一身専属性が認められるかどうか、利用規約等を確認する必要がある。
- 死亡時において、故人の友人知人に対して葬儀の連絡をするため、故人のFacebookアカウントから親族が本人に代わって訃報を伝えるケースがあるが、サービス提供者であるMeta社のポリシーに反するものとされており、推奨される行為ではない点について注意する必要がある。
- 故人が利用していたサブスクリプションサービスを特定できたとしても、サービス提供者と連絡がつかない、連絡がついたとしても、サービス提供者は任意の解約に応じない等のトラブルが報告されており、解約手続については一筋縄ではいかないおそれがある。
- 現状においては、できる限り、故人の利用していたサブスクリプションサービスを特定し、サービス提供者と粘り強く交渉を行うとともに、銀行口座の凍結やクレジットカードの退会手続により、決済を止めつつ、死後1年半程度、サービス提供者側からの連絡に備える方法が最善といえる。
【メモ】
・デジタル遺品もオンラインとオフラインを区別する
・分割方法においてオフラインデジタル遺品には所有権を観念できない
・サブスクリプションの解約は一筋縄ではいかない
ABOUT ME
大阪市で医療過誤事件(患者側)を中心に扱っています(全国対応)。
現在、訴訟6件(高裁1件、地裁5件)、示談交渉中・調査中の事件は10件以上を担当しています。