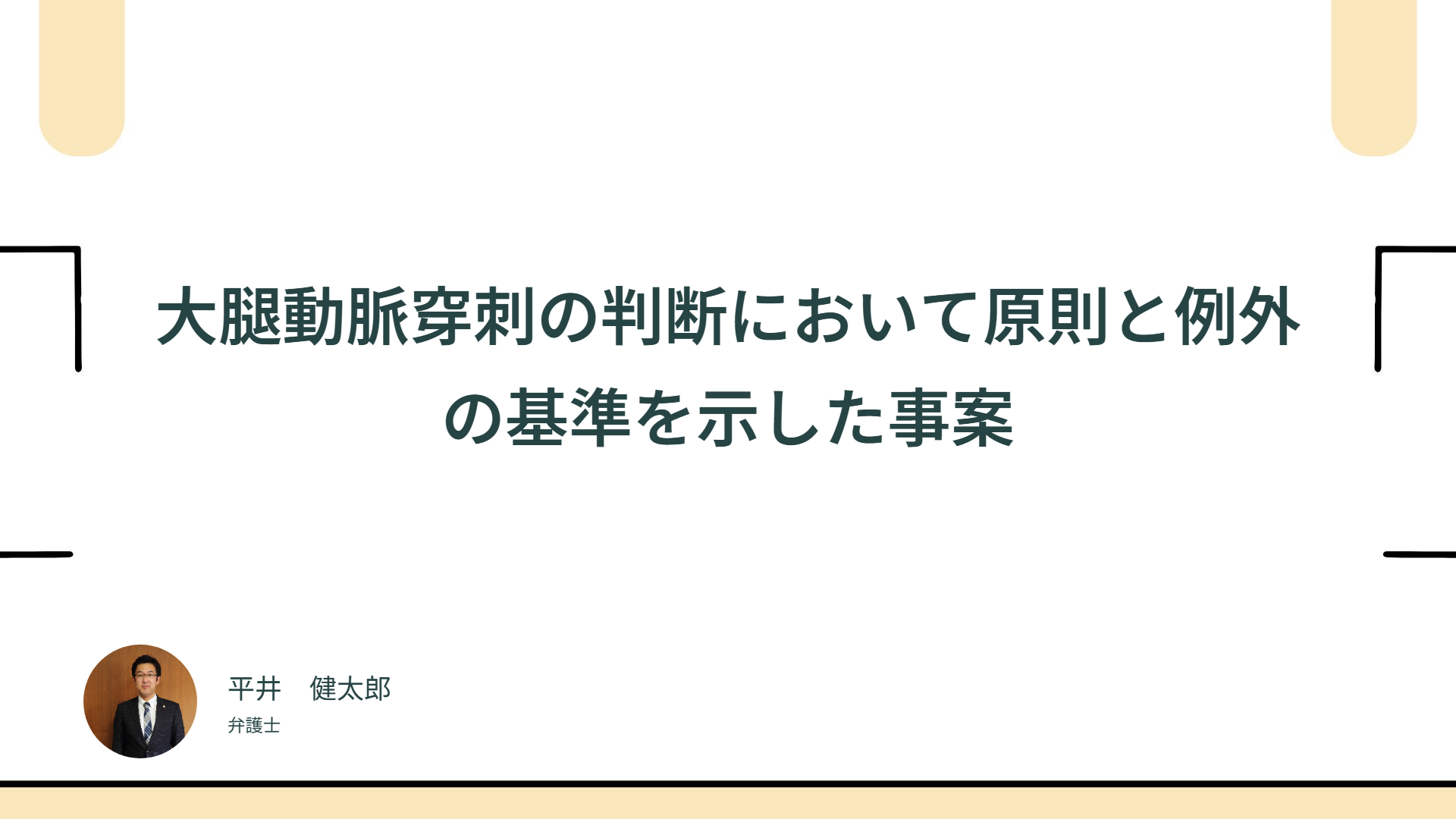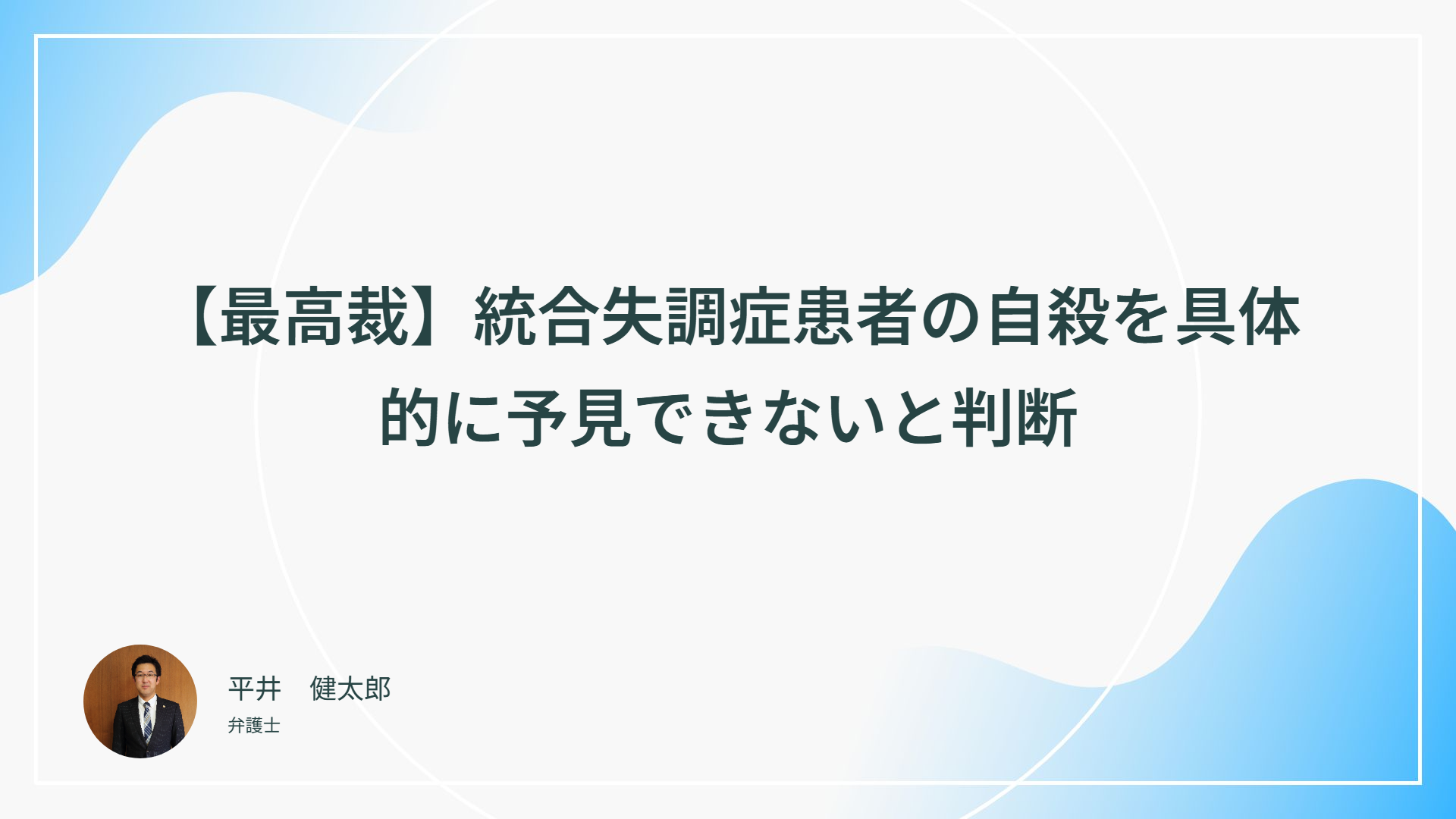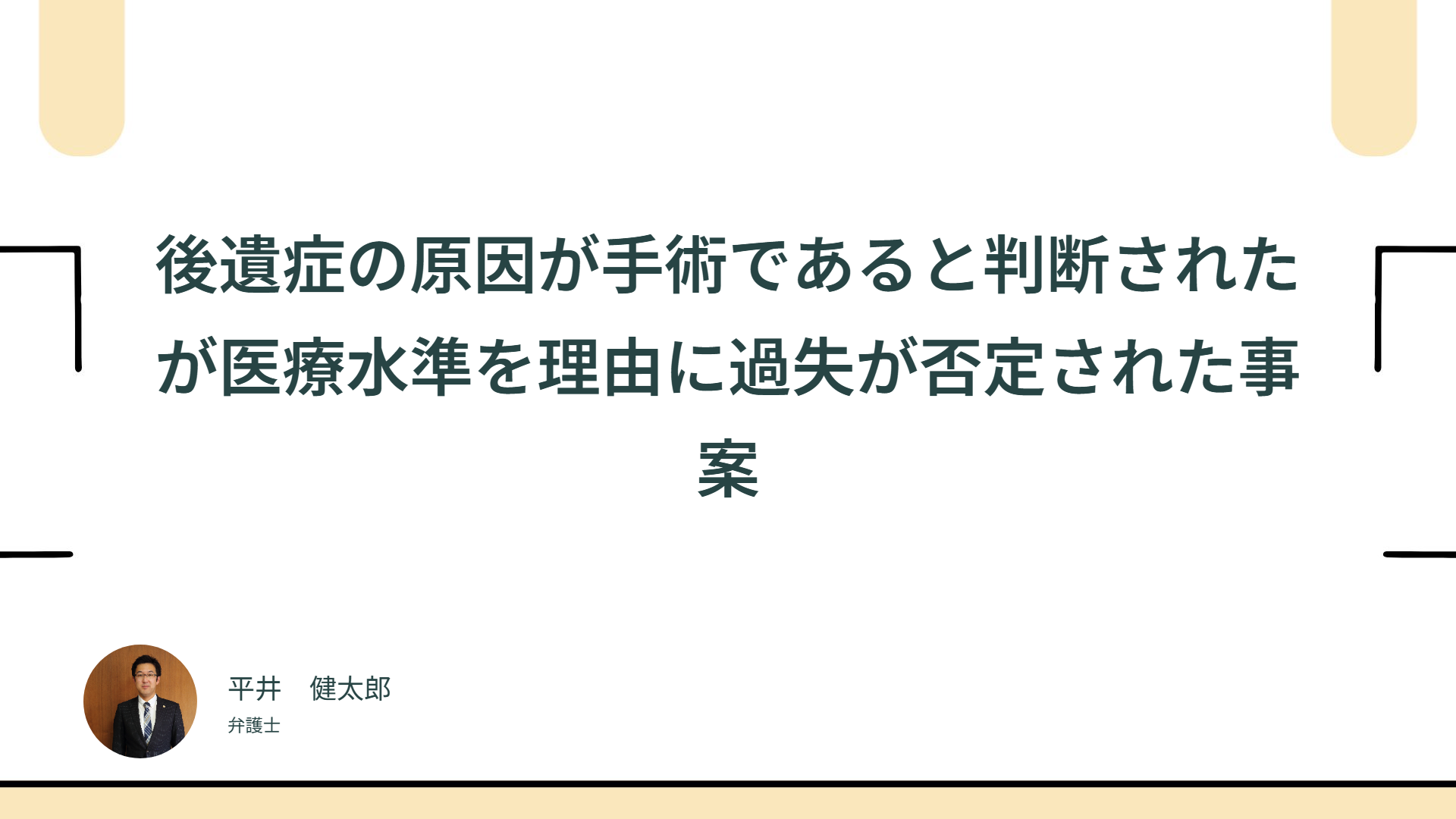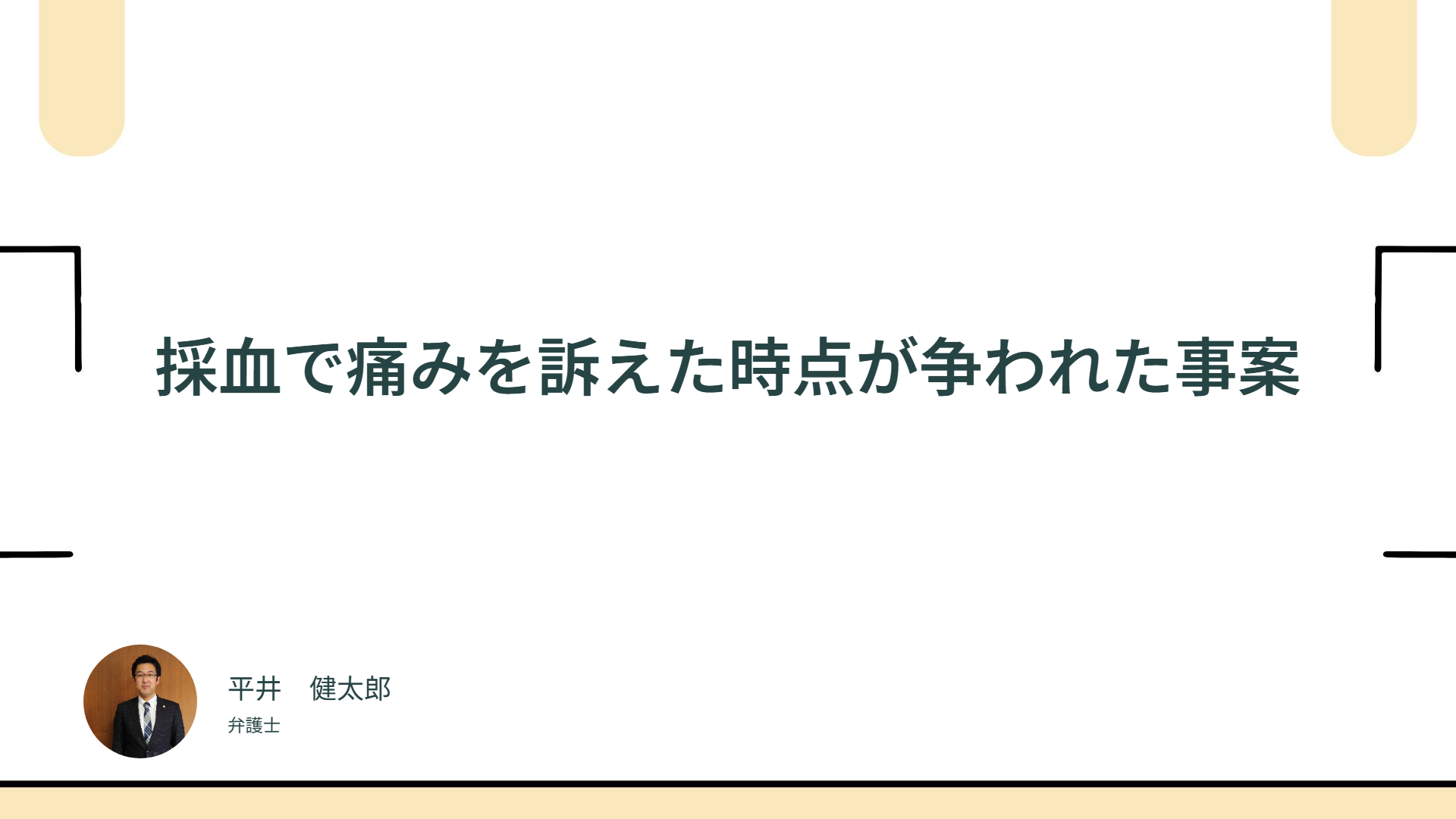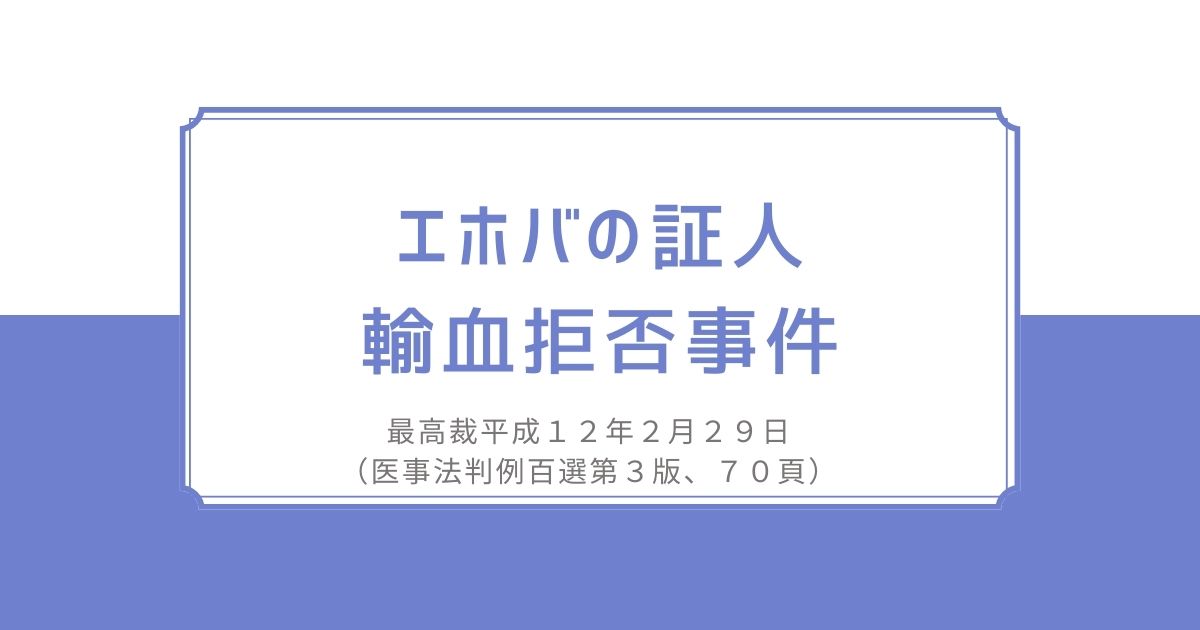診断の合理性とその診断では説明できない症状・状況があったか否かが問題となった事案
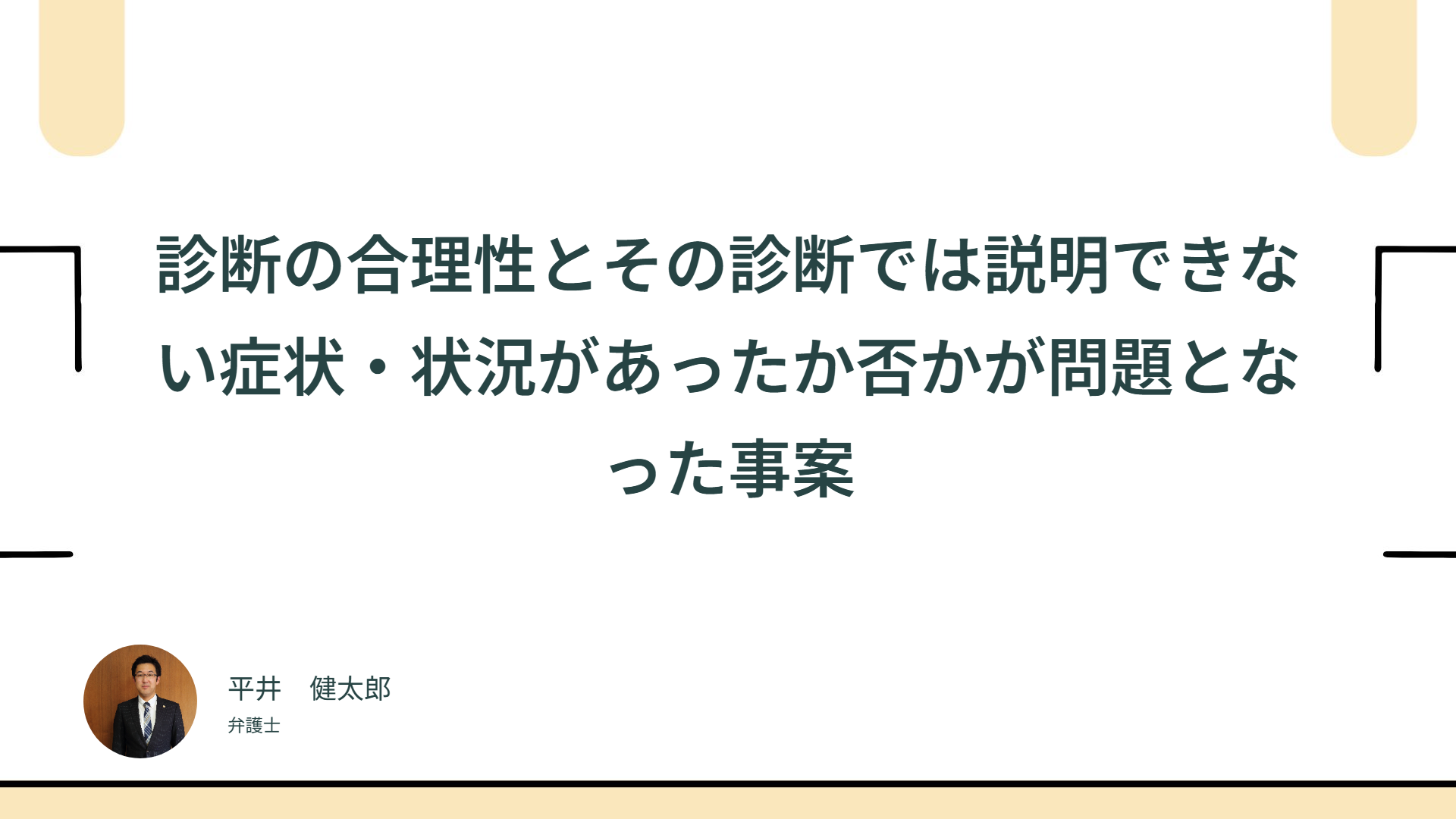
倦怠感・発熱で受診した小学6年生に対し胃腸風邪との診断をしたが、診療所受診中に心肺停止状態になり、転送先で亡くなったことについて、劇症型心筋炎に罹患している可能性を念頭に置いて診察すべきだったかが争われた事案
(大阪地裁平成30年3月20日判決、医療判例解説78号110頁)
【争点】
- 6月8日の診察時に心筋炎の可能性を念頭に置いた診療等をしなかった過失があるか
- 6月9日午前の診察時及びそれ以降に心筋炎の可能性を念頭に置いた診療等をしなかった過失があるか
- 過量のリプラス3号輸液の点滴投与をした過失があるか
- カシロンの点滴投与をした過失があるか
- 損害額
【判旨+メモ】
解剖医の所見について「死因説明書には,死因診断名として劇症型心筋炎と記載され,心筋炎の原因として,ウイルス性が疑われると記載されている。」ため、劇症型心筋炎が問題となっている。
6月8日の診察時における上記①~④の症状及び状況については,いずれも胃腸風邪等の特に重篤でない疾患によるものとみて説明が可能である一方,そのような疾患では説明することができない症状及び状況は見当たらない。そうすると,6月8日の診察時において,胃腸風邪と思われるという被告医師の診断は合理的といえる範囲内のものであり,被告医師が心筋炎の可能性に思い至るべきであったとはいえない。
したがって,6月8日の診察時に,被告医師が心筋炎の可能性を念頭に置いて診察及び検査をすべき注意義務を負っていたとはいえない。(中略)
6月9日午前の診察時において,夏風邪又はウイルス性胃腸炎が疑われるというB医師の診断は合理的といえる範囲のものであり,B医師が心筋炎の可能性に思い至るべきであったとはいえない。
(中略)
これらによれば,被告医師らがリプラス3号輸液の点滴投与や浣腸等の処置をしていた6月9日11時頃~18時頃の間,Aの症状が改善しない状態が続いたわけではなく,改善しているようにみられる時間帯もあったということができ,脱水症状を伴うウイルス性胃腸炎等により説明できない症状又は状況があったとはいえない。
そうすると,6月9日11時頃~18時頃の間,被告医師らが,脱水症状を伴う重いウイルス性胃腸炎の可能性が高いと考え,輸液や浣腸等をしていたという判断及び処置は合理的といえる範囲内のものであり,被告医師らが心筋炎に思い至るべきであったとはいえない。
判決の考え方は以下のように整理できる。
①医師の診断や処置が合理的な範囲内といえるか
②心筋炎の可能性に思い至るべきであったといえるか
(診断した疾患では説明することができない症状及び状況があるといえるか)
診断した内容の疾患では説明することができない症状及び状況の有無が結論に影響することになる。
また、意見書は提出されていたが採用されていない。
抽象的な意見にとどまり,被告医師らの立場に置かれた一般の医師において,具体的にAのどのような症状から心筋炎の可能性に思い至ることができたかを説明する部分がないから,上記記載は採用できない。
意見書では、上記のような記載が求められているという意味で参考になる。