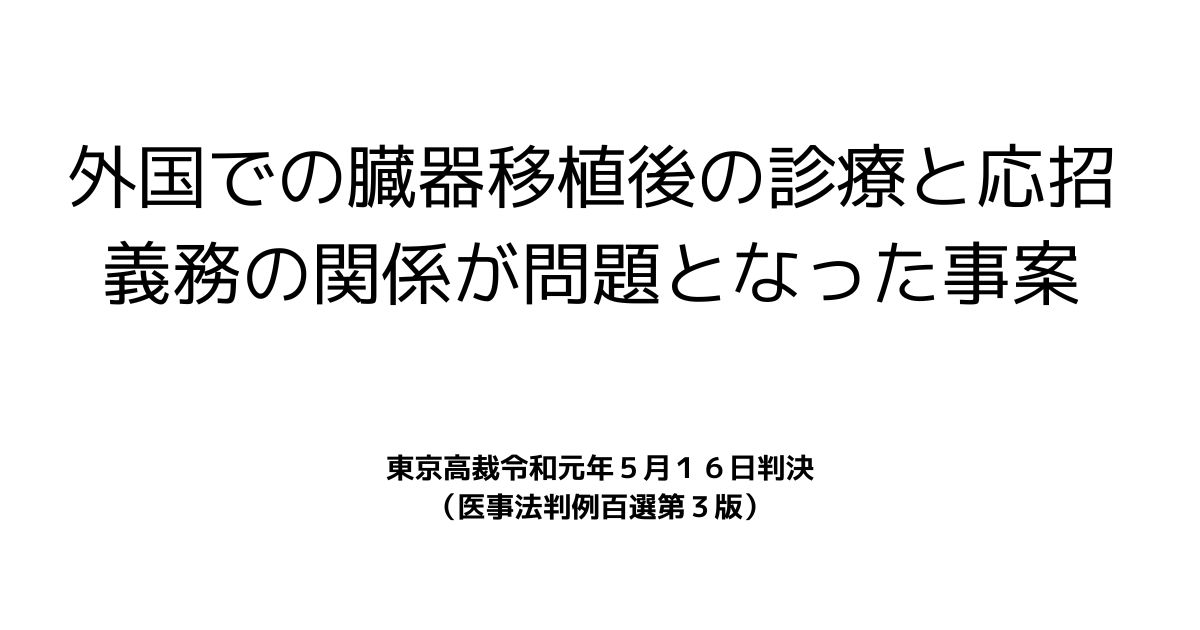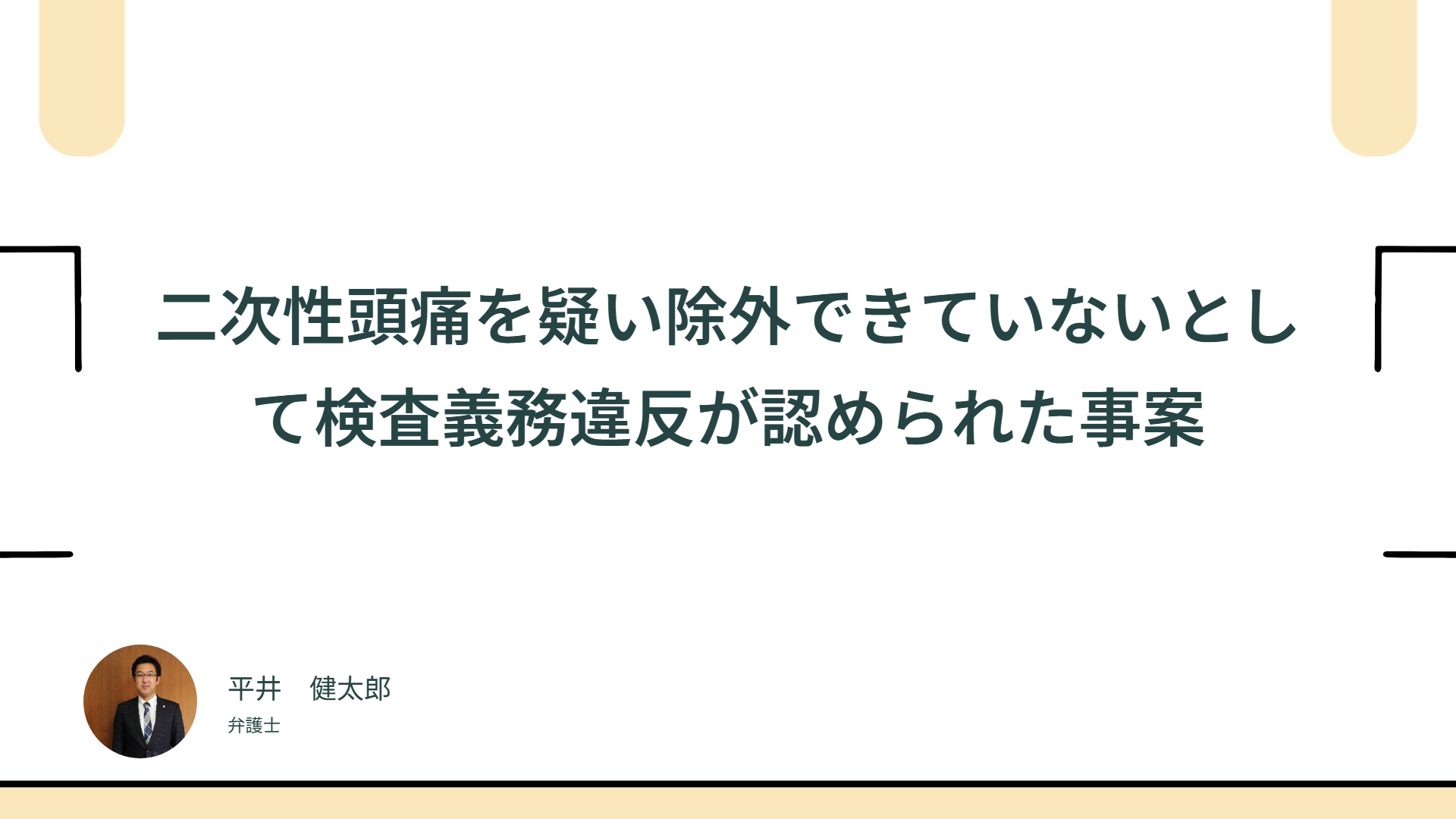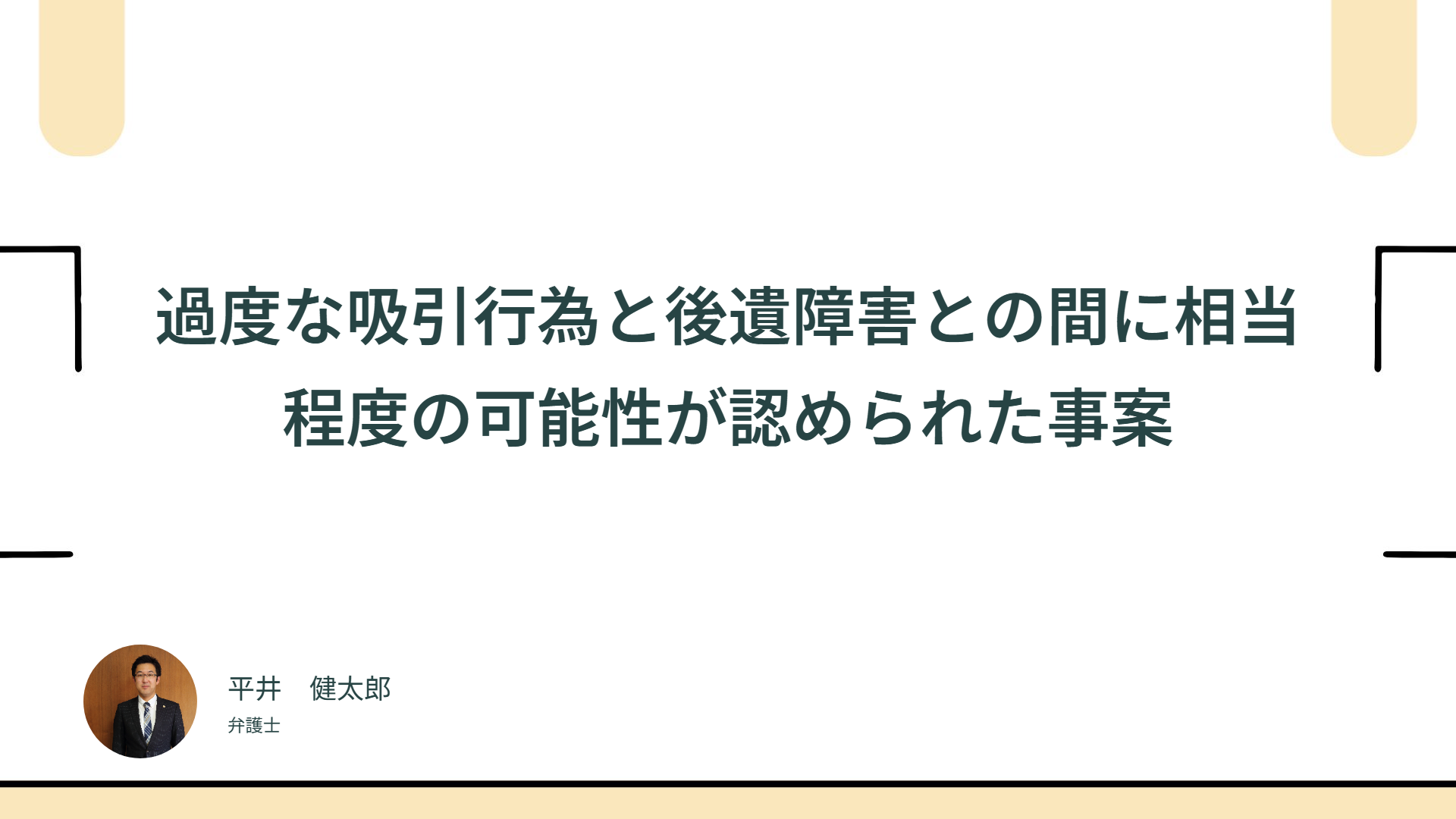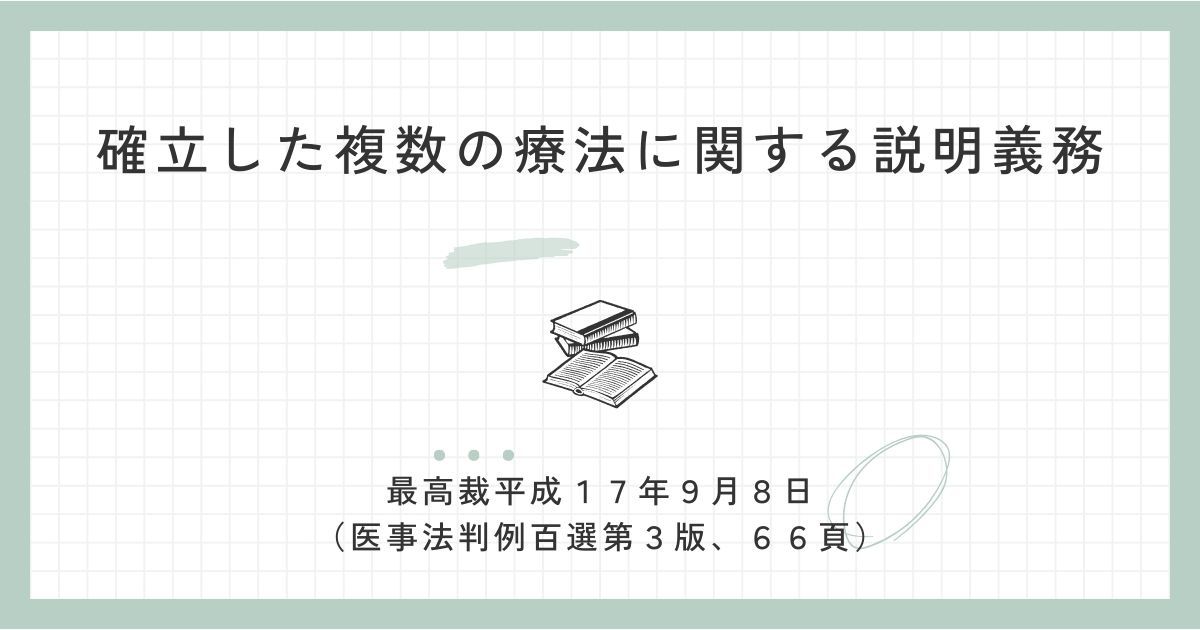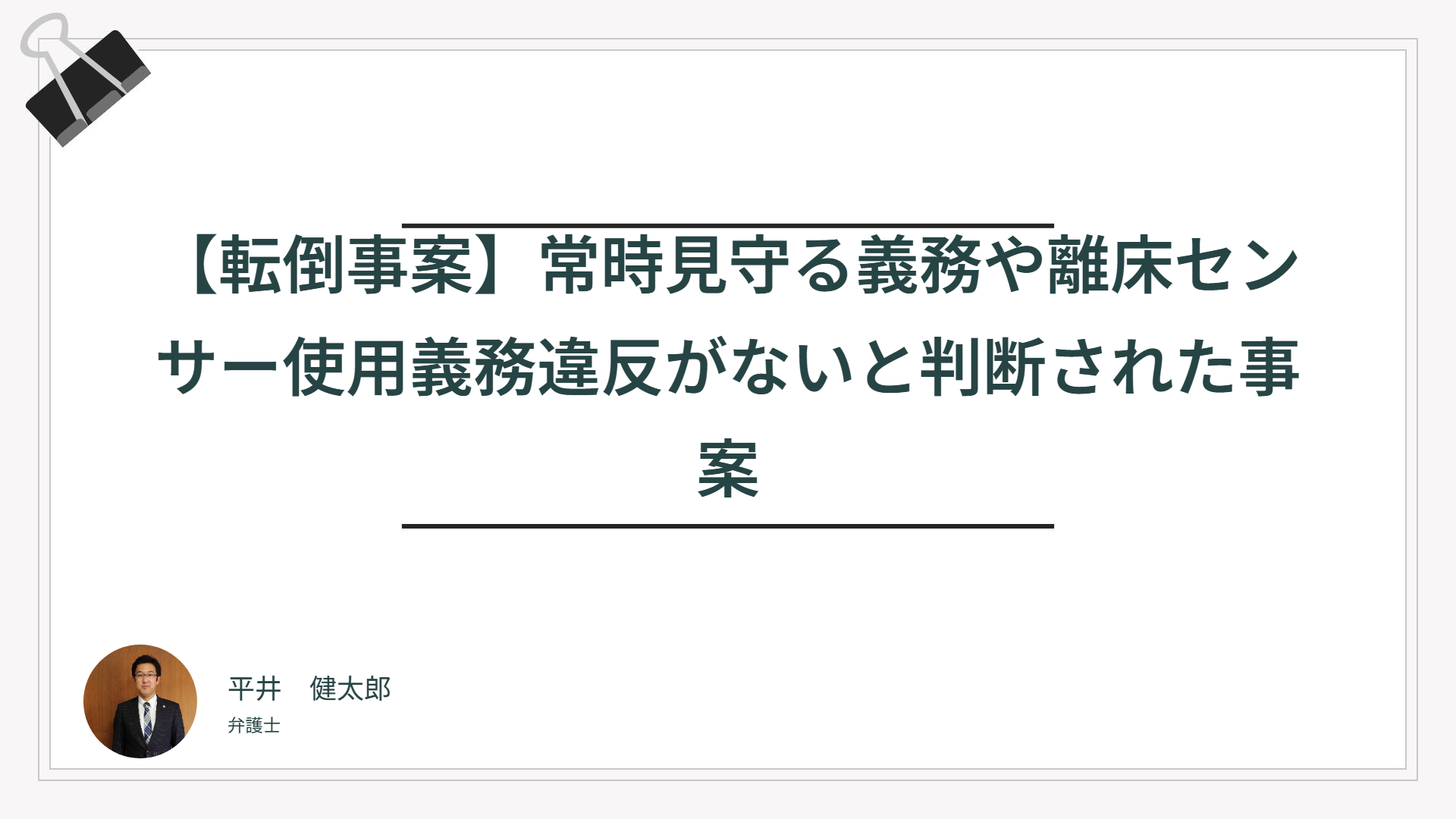説明義務違反と死亡との間の因果関係が認められた事案
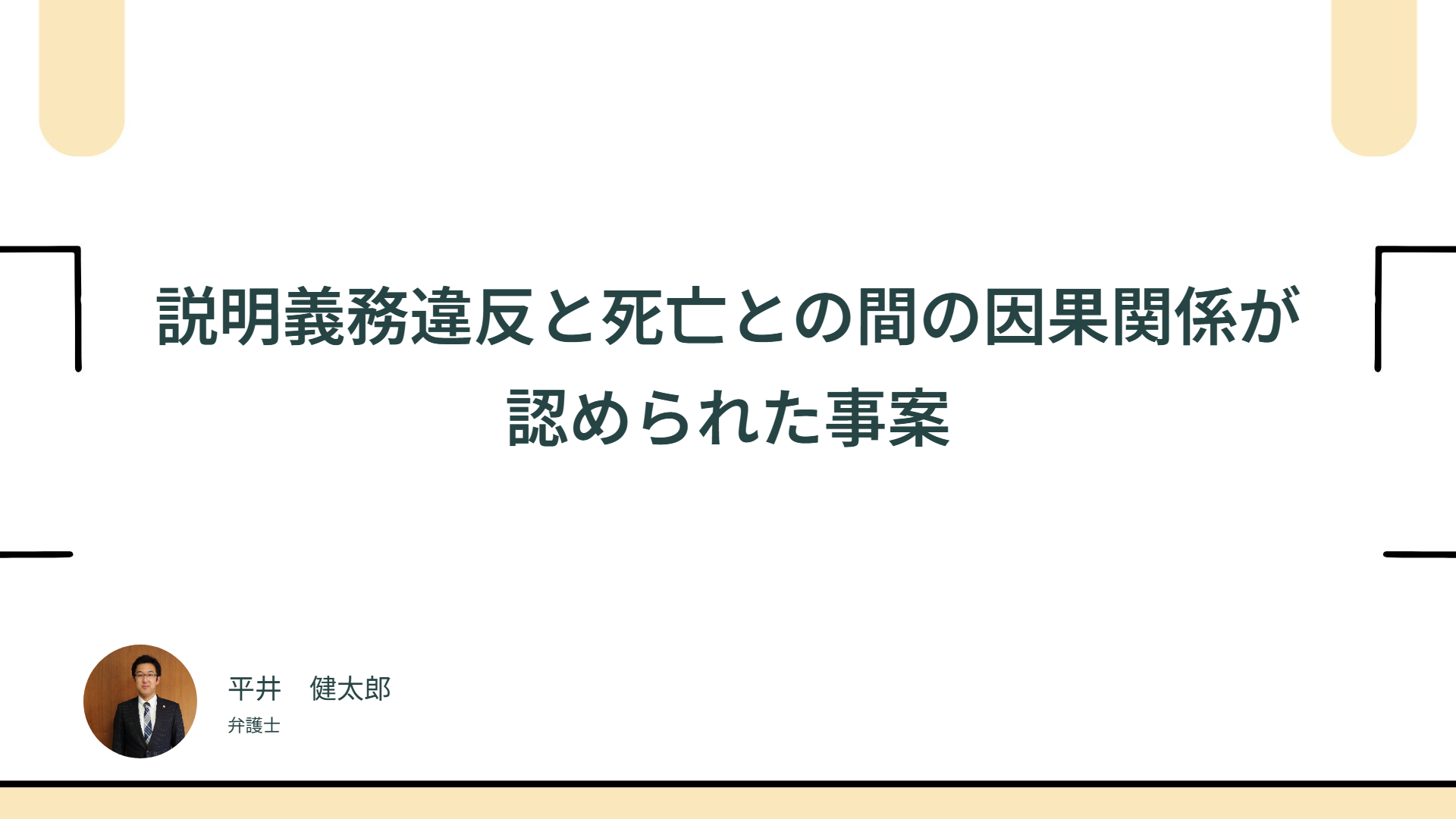
自己免疫性肝炎と診断されていた70代女性が、ERCP検査及び胆道鏡検査を受けた後、重症急性膵炎と診断され治療を受けたが死亡した事案
(東京地裁令和7年7月18日判決(控訴中)、医療判例解説118号2頁)
【争点】
- 亡花子が死亡するに至った機序
- 亡花子に胆道鏡検査の適応がなかったにもかかわらず、本件胆道鏡検査を実施した注意義務違反の有無
- 本件胆道鏡検査時に胆管径より大きいバルーンを使用すべきでなく、さらにバルーンで過拡張すべきでなかったにもかかわらず、これらを行った注意義務違反の有無
- 本件ERCP検査後の精査義務違反の有無
- 説明義務違反の有無
- 説明義務違反と結果との間の因果関係の有無
- 原告らの損害
【判旨+メモ】
まず、争点①の機序で、ERCP検査及び胆道鏡検査によって穿孔が生じたか否かが争われている。
結論としては以下のように判断されている。
したがって、原告らが主張する穿孔が生じた理由は穿孔が生じたことを認めるに足りるものではない上、穿孔を否定する事情も認められることからすれば、原告らが主張する機序を認めることはできない。
上記のとおり、機序において原告の主張が認められなかったため、機序と連動する過失である②③④は理由がないとされ、それぞれの過失の内容について詳しい判断はなされていない。
本件では、医療事故調査・支援センター報告書が証拠として提出されている。機序の主張においても、記載内容を根拠に原告は主張していた。
同報告書には「急性膵炎が急速に重症化した背景として、検査中の膵内胆管損傷が疑われた」との記載があったが、「穿孔が生じたと認めるのであれば穿孔が生じたと記載されるはずであり」などとして、穿孔を指すものであるとはいい難いと判断されている。
次に説明義務であるが、以下の義務があったとされている。
このような事情を踏まえれば、被告A医師は、遅くともERCP検査及び胆道鏡検査を実施する前までに、これらの検査のリスクが胃カメラと同程度のものであるとの亡花子の誤信を解くべくこれらの検査による死亡の危険性について説明を尽くす義務があったと認められる。
当該義務を導く前提に、被告A医師の供述の信用性が争われ、信用できないと判断されている。
この点については、録音データが存在しており、被告は録音が改ざんされたものであるなどと主張していたが、認められていない。
これらの事情を踏まえると、ERCP検査や胆道鏡検査が通常の検査と異なるリスクを有しており、ERCP検査後膵炎になる割合やこれが重症化すると死亡する可能性があることを説明したとする被告A医師本人供述は信用することができない。
そして、説明義務と結果との因果関係については以下のとおり判断している。
身体に負担のかかるような検査や治療は避ける方針を共有していたことを踏まえると、検査の緊急性、偶発症の発症確率、死亡の危険性等が適切に説明されていたとすれば、腫瘍マーカーの増大等があったこと(前提事実(2)のイ)、PSCに罹患している場合、通常人と比較して胆管がん等を効率に併発すること(前提事実(3)のア)を考慮しても、原告秋江をはじめとする家族で相談して今回の検査を見送っていた高度の蓋然性があるということができる。
上記の他に、日常生活レベルで支障がなかったこと、胆管がんや膵がんを疑う所見はなかったこと、PSCをと診断された場合の治療は肝移植のみとされていたこと、緊急性が高くなかったことなどが考慮されている。
説明義務違反と死亡との因果関係が認められた事案として参考になる。