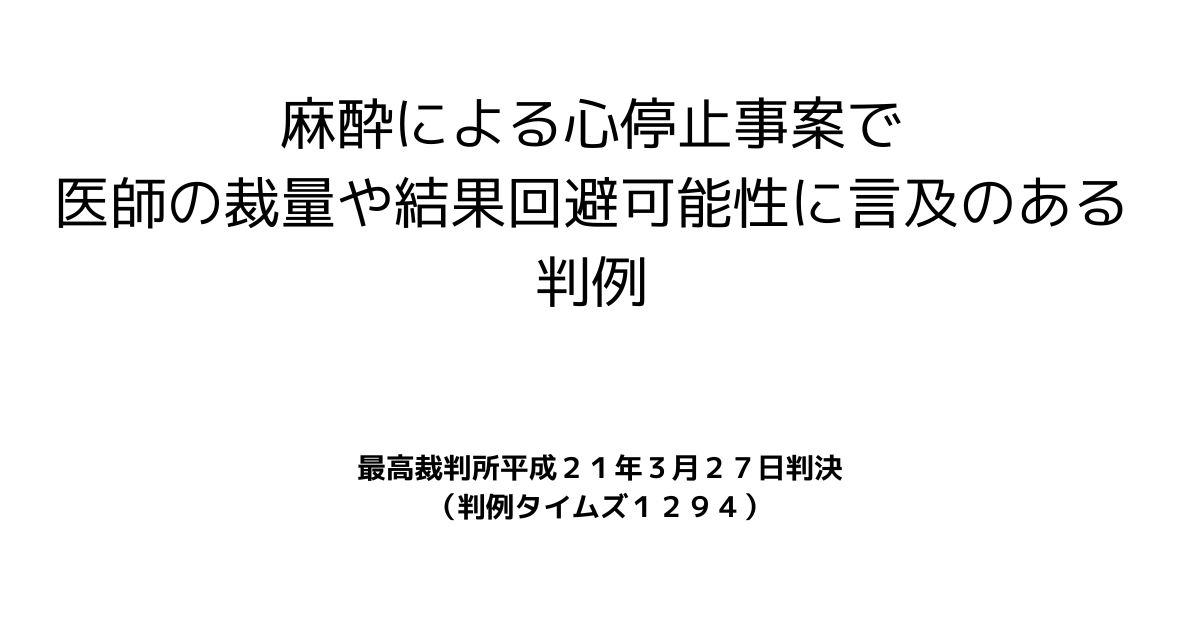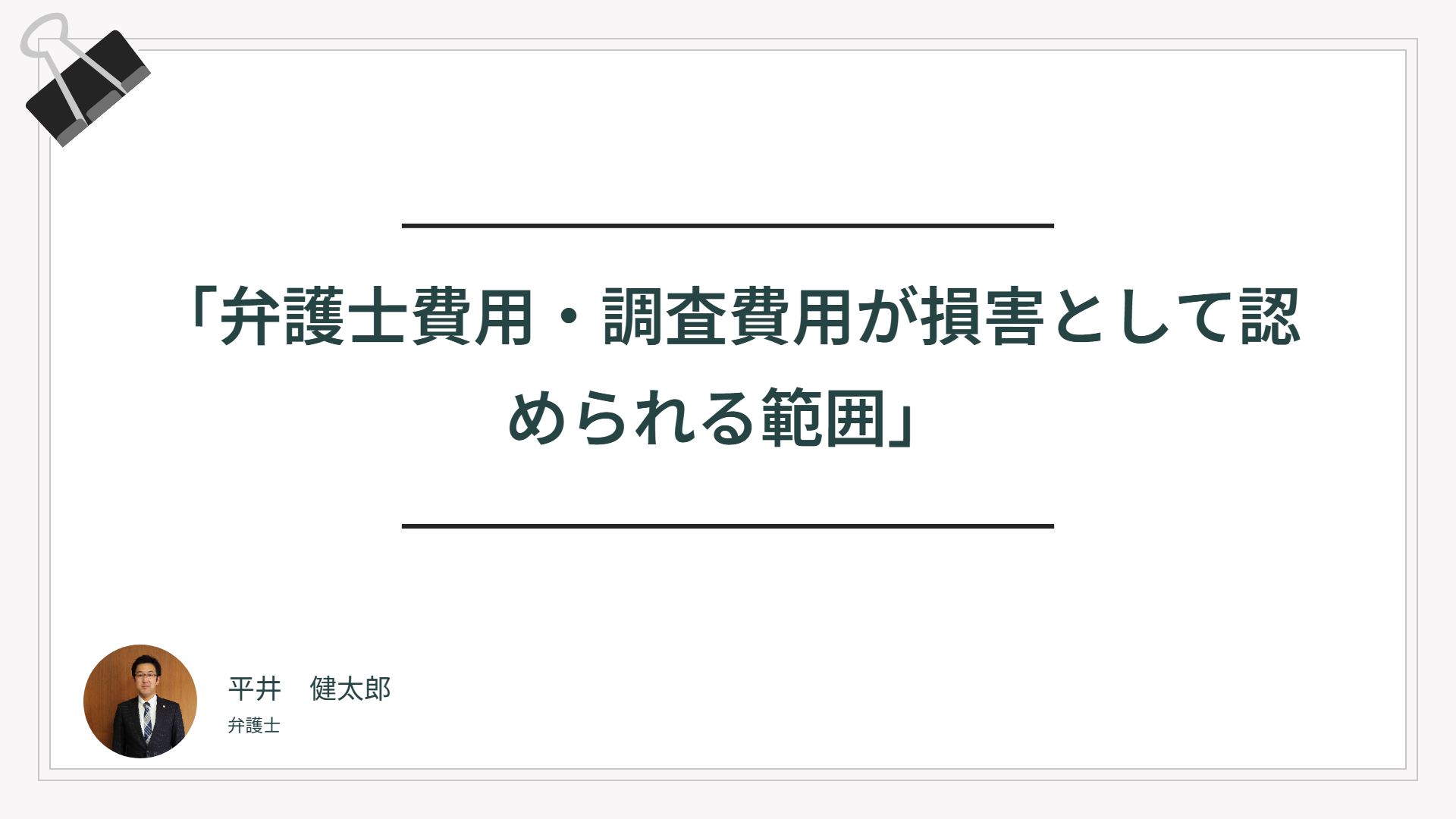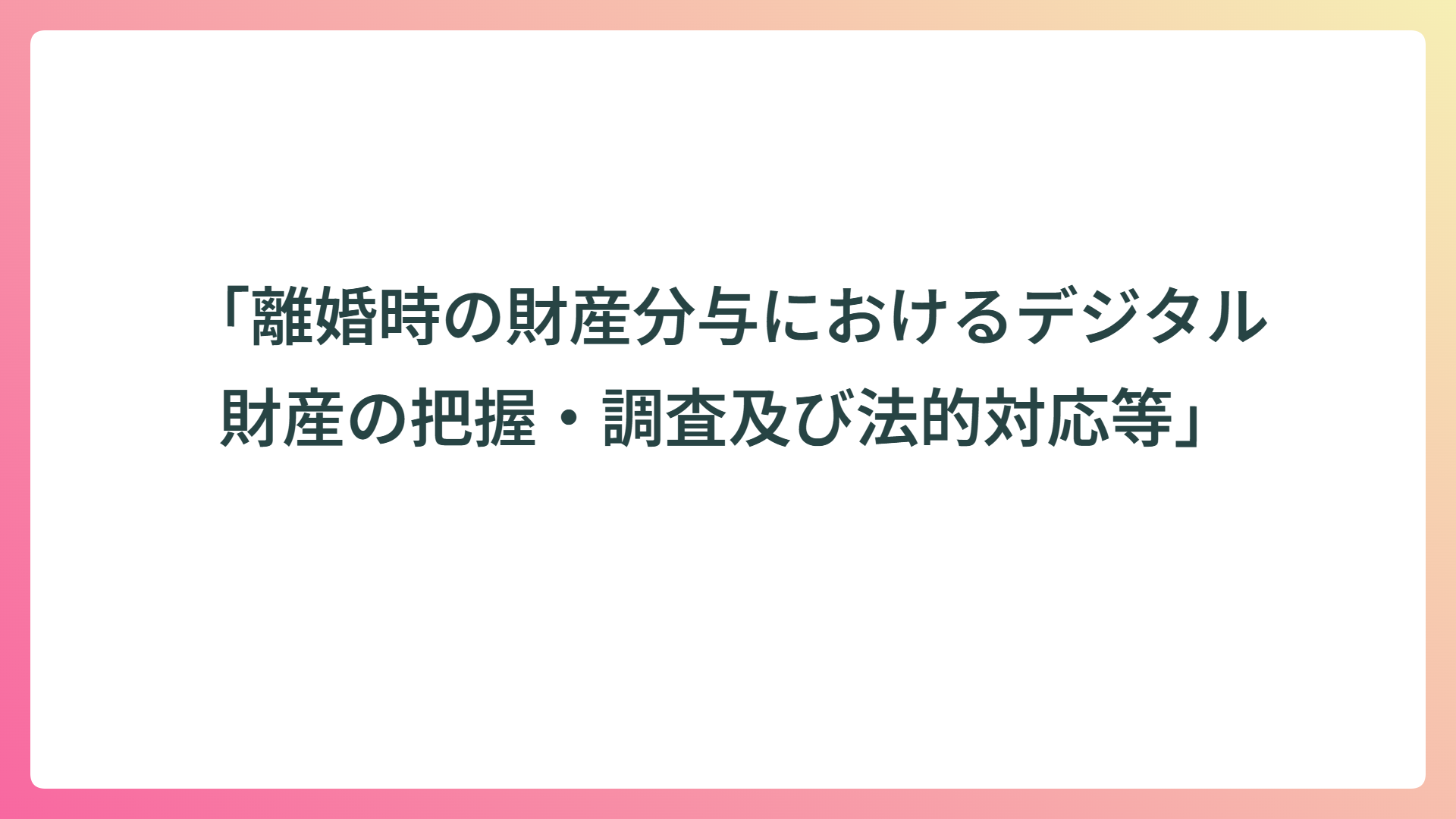「主張と証拠の早期提出と争点整理」(法律のひろばVol.78 No.2)
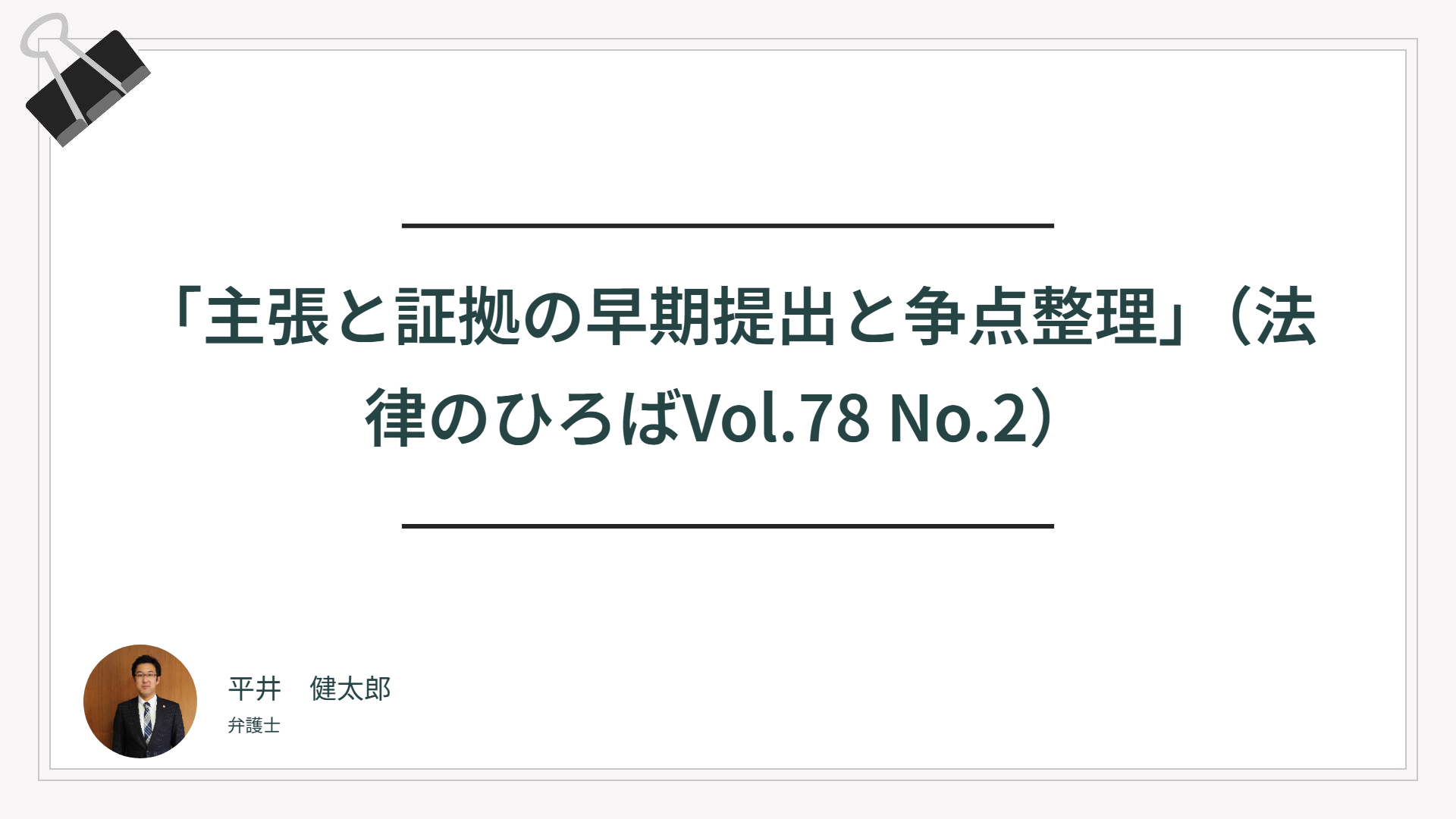
「主張と証拠の早期提出と争点整理」(法律のひろばVol.78 No.2)を読んで
その依頼者の権利が最大限認められる法律構成と事実を裁判所に提示し、これを裏付ける書証等について、制限を加えられることなく、訴状に添付して提出し、自らの主張の正当性を論証し、自ら提起する訴訟における土俵を有利に設定することができる。このように原告は、請求内容を根拠づけるのに必要十分な主張と証拠を可能な限り提出して裁判所に有利な心証を持って第1回口頭弁論期日に臨んでもらうことを期待できる。
その報告書中で、相手方準備書面が陳述されたという手続上の事項を記載するにとどまらず、次回に向けた準備内容を記載する欄を設けて、相手方準備書面の骨子を記載し、さらにこれに対する認否反論の大まかな方向性だけでも示しておく。
期限遵守に関しては、民事訴訟規則83条の2に裁判所書記官による当該準備書面の提出又は証拠の申出の促しの定めが設けられ(中略)民事訴訟法162条2項に、期限を遵守できなかった場合、当事者に理由を説明させる制度が創設されることとなった。この説明義務の実効性については、現行法においても、民事訴訟法167条とこれを準用する174条及び同178条に説明義務が定められ、この義務違反があったとしても、時機に遅れた攻撃防御方法として却下するといった運用はなされなかったことから、今般の改正を受けても甘い運用をしていると意味のない規定になってしまうという指摘がある。
間接事実及び補助事実については、主要事実を推認させる過程及び証拠の実質的証拠力にどれだけの影響力があるかも考慮要素となるから、①「存否」のほか、②「意味づけ」(主要事実、証拠との具体的関係性)と、③「重み付け」(主要事実の推認力又は証拠の証明力への影響)についての各当事者の見解を整理する。このうち、書証の裏付けのある主張とない主張を区分けし、書証のどの部分がその裏付けになるのかの対応関係を示す。
【雑感】
訴状の重要性を再認識した。
被告が提出する答弁書、双方の準備書面は先に提出された書面への反論など、ある程度範囲な決まってしまうが、訴状は誰からの干渉も枠の制約もなく、原告が書きたいこと、出したい証拠を提出することができる。
そういう意味では、訴状を出す側が有利のようにも思えるが、私が中心に取り扱っている医療事件で言えば、結果に至る機序の特定や過失の特定など、不十分な内容で提出してしまうと、最初の印象が悪くなり、原告に不利な印象を抱かせてしまうという危険もある。
やはり医療事件では、事前の調査が何より重要であり、その調査に基づいて訴状を作成し、患者側に有利な心証を抱いてもらえないとスタートラインに立てないと感じた。
間接事実にて関しては、「存否」「意味づけ」「重み付け」のうち何を起案しているかを常に意識しながら、主張を整理する必要がある。
これがごちゃ混ぜになってしまうと、読み手に分かりづらく、こちらに有利な評価をしてもらえないリスクが存在する。