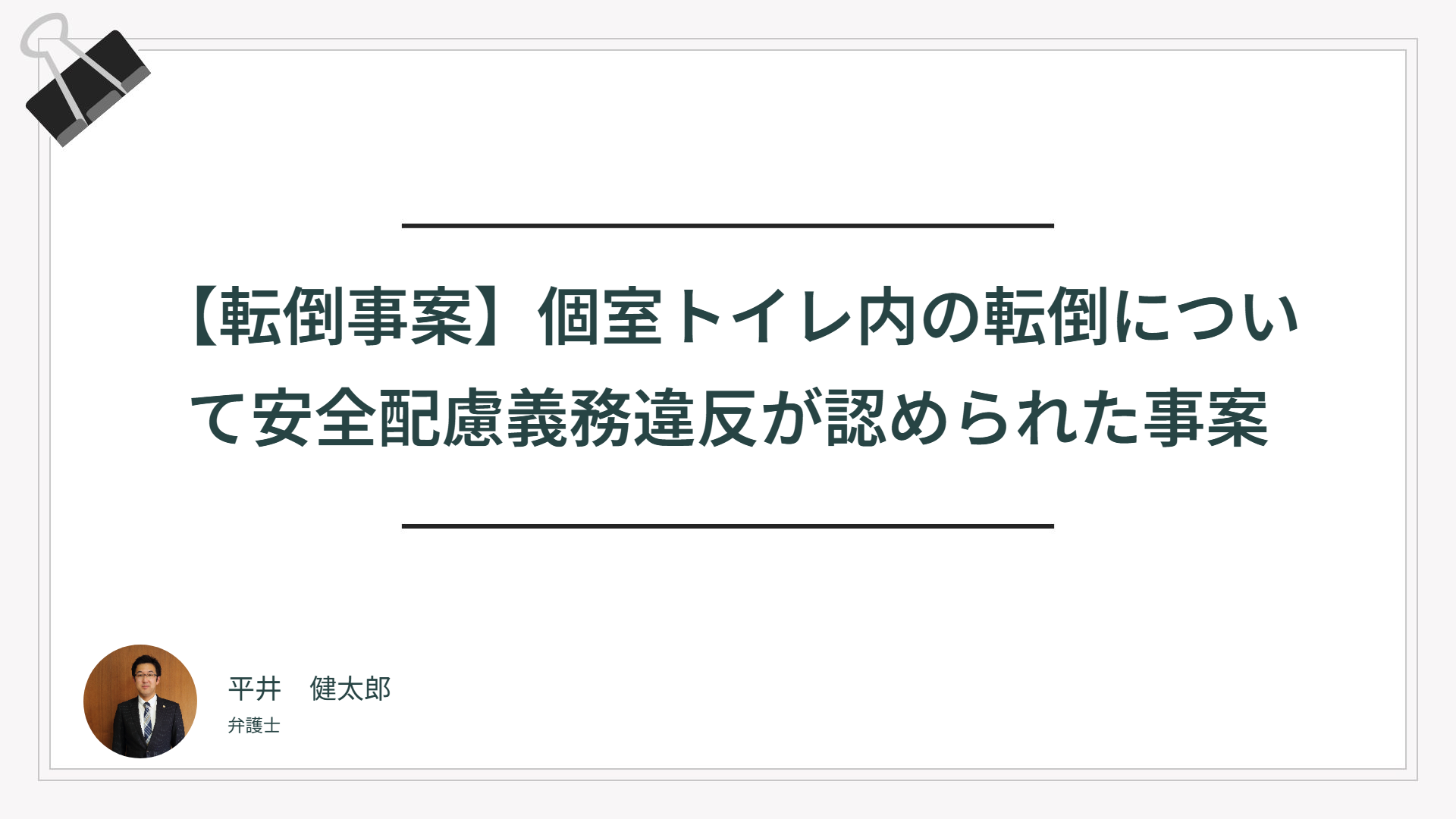「電子データ証拠調べの課題」(法律のひろばVol.78 No.2)
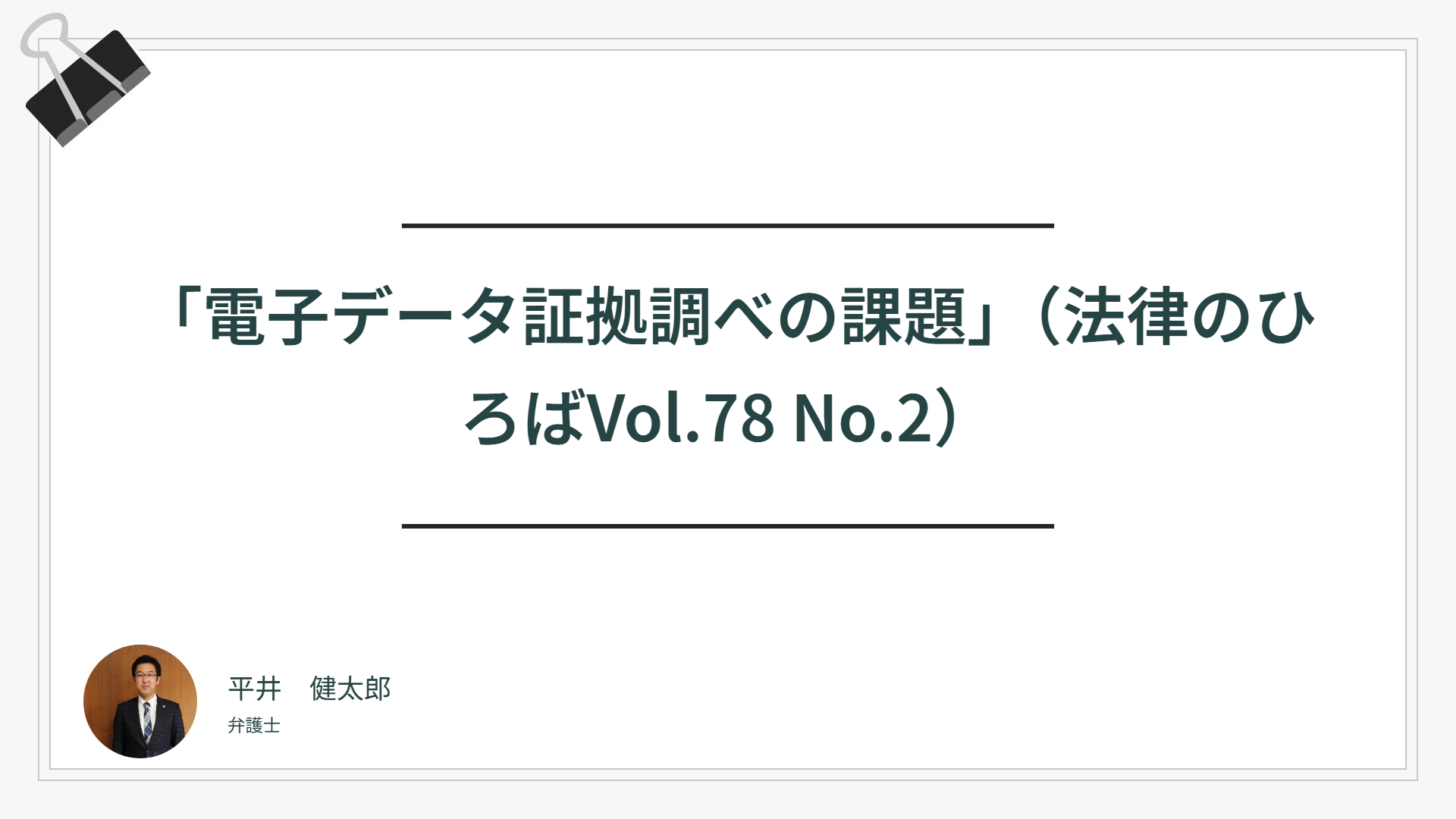
「電子データ証拠調べの課題」(法律のひろばVol.78 No.2)を読んだ備忘録
書証(調べ)の対象(になる適格)性の獲得のため、ないし、当事者の公平性や手続保障のため、一方当事者(代理人)が、多数ある医用画像の中から重要な画像を抽出して印刷し、これを準備書面に引用しながら説明を行うということをしなければならないこともあり得る。
故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったとき、10万円以下の過料に処され、実務では、軽々に文書の成立の真正を争うことはなされない。
紙の文書においては入力・記憶・出力が一体化しており、これらを分けることはできないが、電子データではこれらが分化しており、ハードウェアの構成に従って入力→記憶→出力という過程を経る。電子データは出力装置により出力されることによって(閲読可能性を獲得して)書証(調べ)の対象になるが、その前段階において、入力者は誰か、記憶は記憶装置に正確に保持されているかが問題になる。前者は、ほぼ文書の形式的証拠力(真正)に対応し、後者は、改ざんされていないこと(変造・改変がないこと)を意味する。そして、出力後は実質的証拠力に対応する。
デジタル署名については、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号/以下「電子署名法」という。)第3条に電子署名の真正な成立の推定規定がある。
医療事件をやっているとカルテだけでなく、画像データも見る必要があり、画像がDICOMと呼ばれる規格に従って作成されている。
病院からカルテ開示を受ければ、画像データのDiscにソフトウェアも含まれているため、自分のPCでも見ることは可能である。
しかし、上手く起動しなかったり、読み込みに時間がかかることもあるため、私は有料のソフトウェアを契約している。
本書では、画像データを読み込めない場合を想定して画像の引用を記述しており、それ自体は全くそのとおりである。
裁判所が画像データを読み込める場合に準備書面で画像引用しなくてよいかと言えばそうではなく、やはり原告が注目している画像は貼り付けて、印などを付けてポイントをわかりやすく伝える必要があると思い、実践している。
紙の文書と電子データの違いを普段あまり意識していなかったが、入力・記憶・出力の過程の違いや改ざんがどこに対応するかなど参考になった。