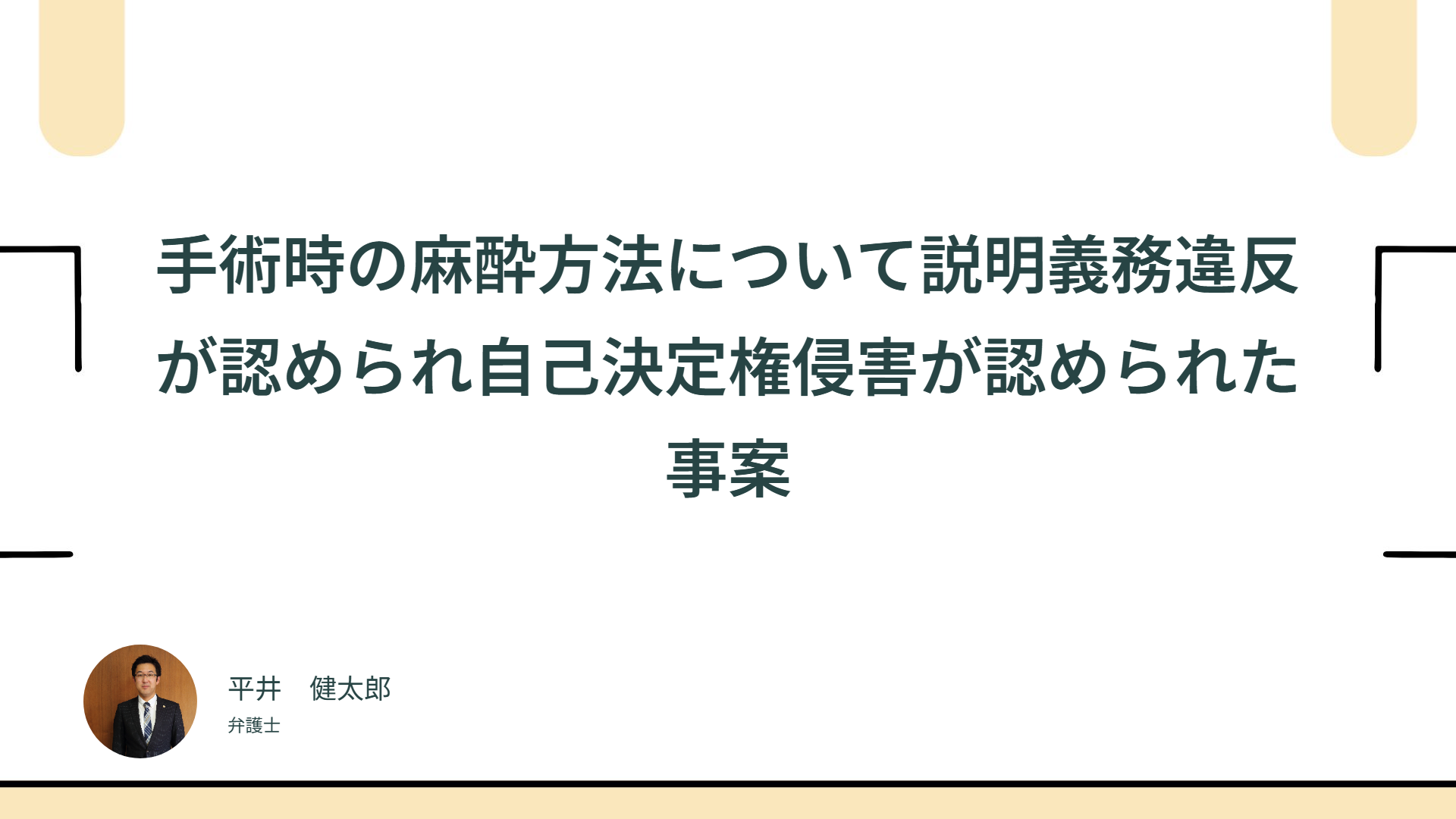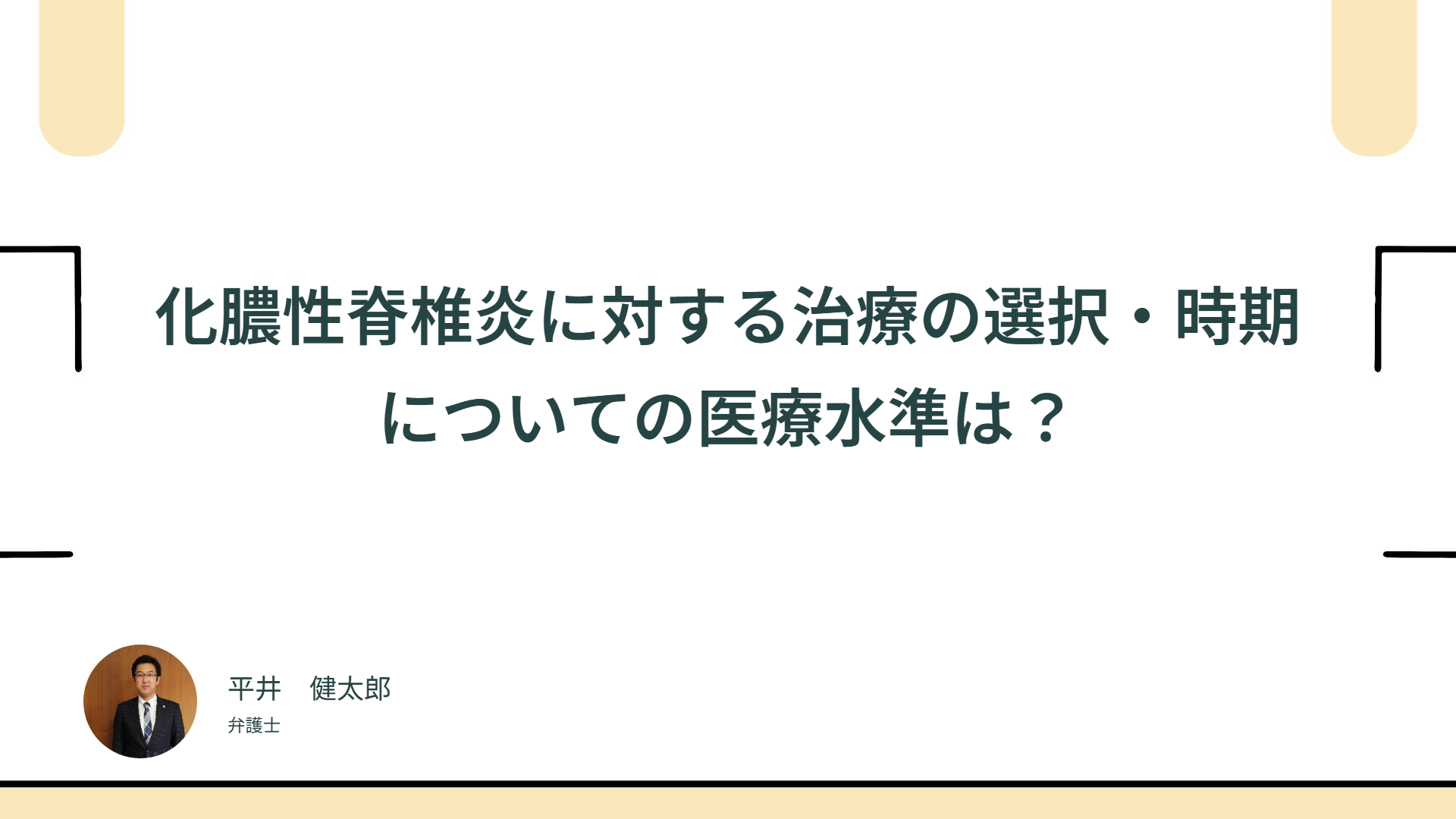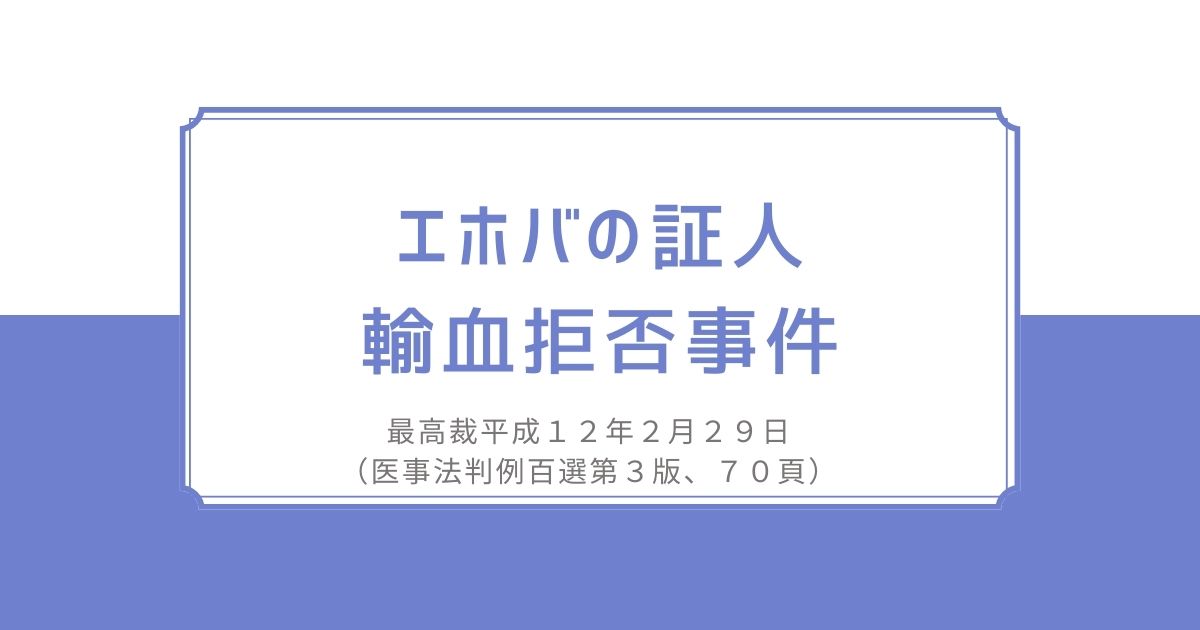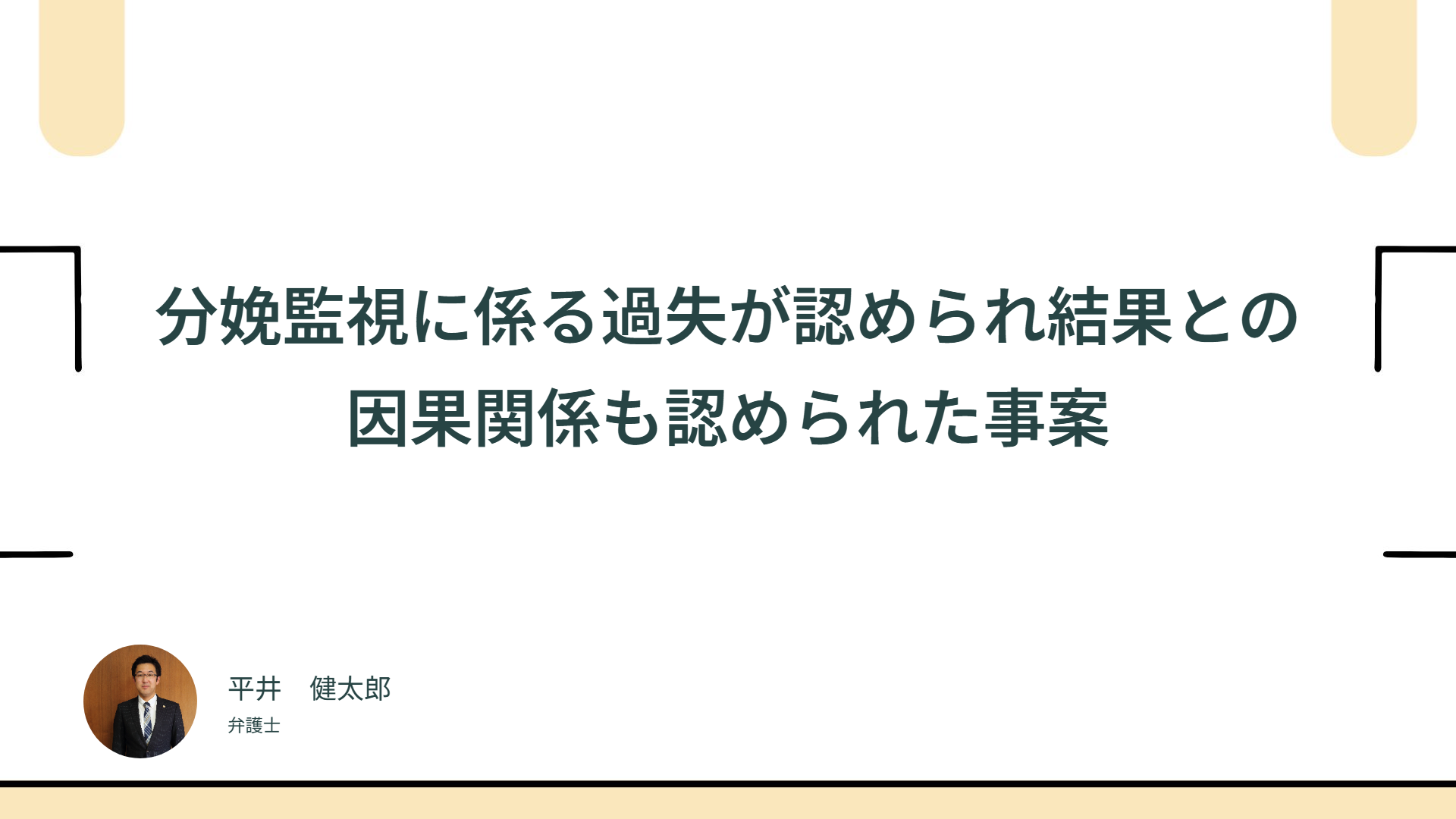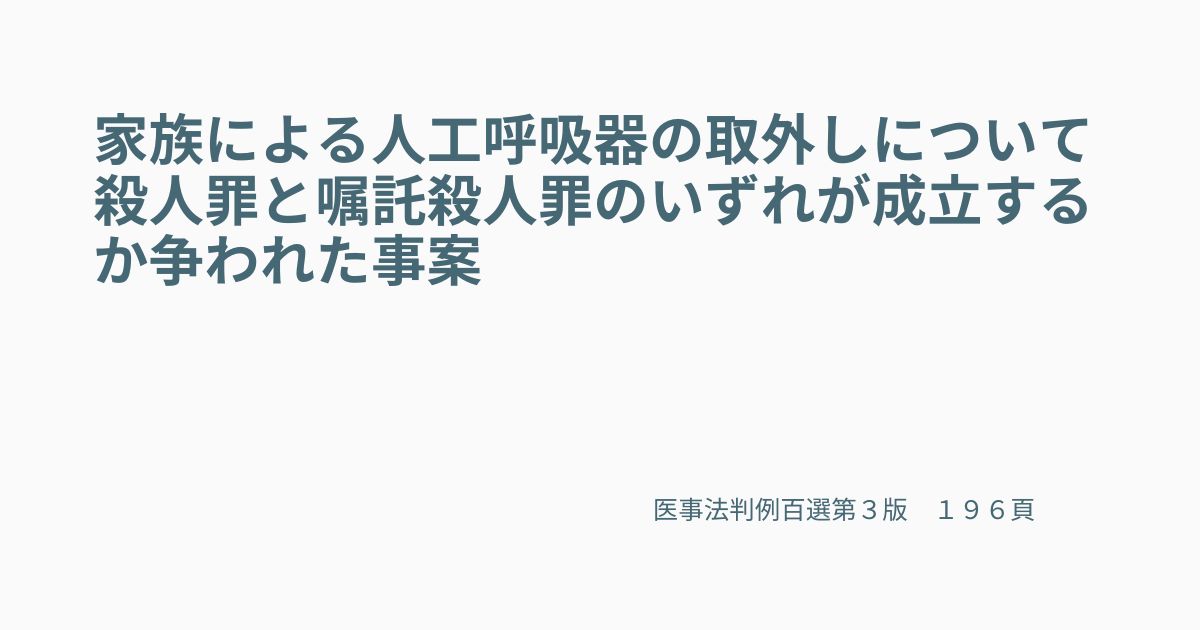【最高裁】統合失調症患者の自殺を具体的に予見できないと判断
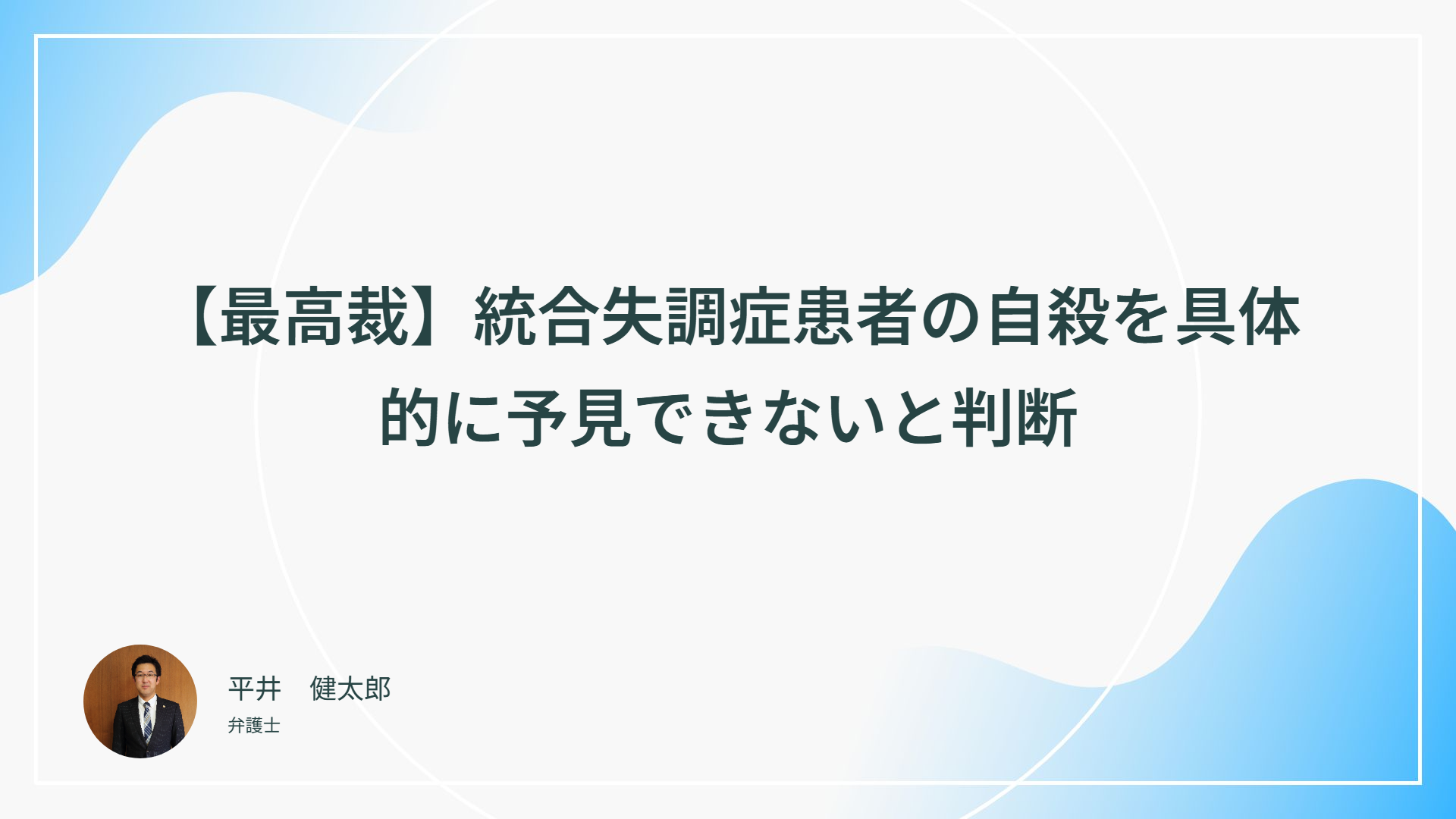
最高裁第三小法廷平成31年3月12日 判例タイムズ1465号56頁等
【概要】
統合失調症の患者が、中国の実家に帰省中に自殺したことについて、自殺を防止するために必要な措置を講ずべき義務を怠ったとして、損害賠償を求めた事案
【事実経過】
H10.1 統合失調症発症
H16.4~ 抗精神病薬等を処方
H22.3 幻聴が現れる
H22.8 自殺企図、医療保護入院
H22.10 幻聴の頻度が減り、希死念慮も現れなくなり退院
H22.11~H23.1 月1回の通院、服薬量の減量
H23.2 電子メールで中国実家に帰省を連絡
H23.4 実家に帰省
H23.4 漸次減量したが幻聴悪化、飛び降りたいという衝動
H23.5 幻聴悪化、希死念慮、医師に電子メール送信
H23.6 自殺
【判旨】
控訴審は
「本件患者が上記状況にあることを認識した上で抗精神病薬の服薬量の減量を治療方針としてその診療を継続しており、遅くとも本件電子メールの内容を知った平成23年5月▲日の時点において、本件患者の自殺の具体的な危険性を認識したのであるから、その自殺を防止するために必要な措置を講ずべき義務があり、これを怠った過失がある。」
と判断した。
これに対し、最高裁は
「抗精神病薬の服薬量の減量を治療方針として本件患者の診療を継続し、これにより本件患者の症状が悪化する可能性があることを認識していたことを考慮したとしても、被上告人X1からの本件電子メールの内容を認識したことをもって、本件患者の自殺を具体的に予見することができたとはいえない。したがって、上告人に、本件患者の自殺を防止するために必要な措置を講ずべき義務があったとはいえないというべきである。」
と判断した。
【メモ】
自殺を具体的に予見することができたといえるかどうかが判断の分かれ目であった。
最高裁も、症状悪化の可能性を認識していたことを考慮していることからすると、症状の悪化だけでは足りず、「具体的」に自殺を予見できなければならないと判断している。
具体的に予見できる事実関係が認められれば、医師の法的責任が認められる場合があるということも意味している。
他の件でも何らかの結果に対する予見可能性を検討するにあたっては、抽象的な予見ではなく、具体的に予見できることを事実に基づき主張する必要がある。