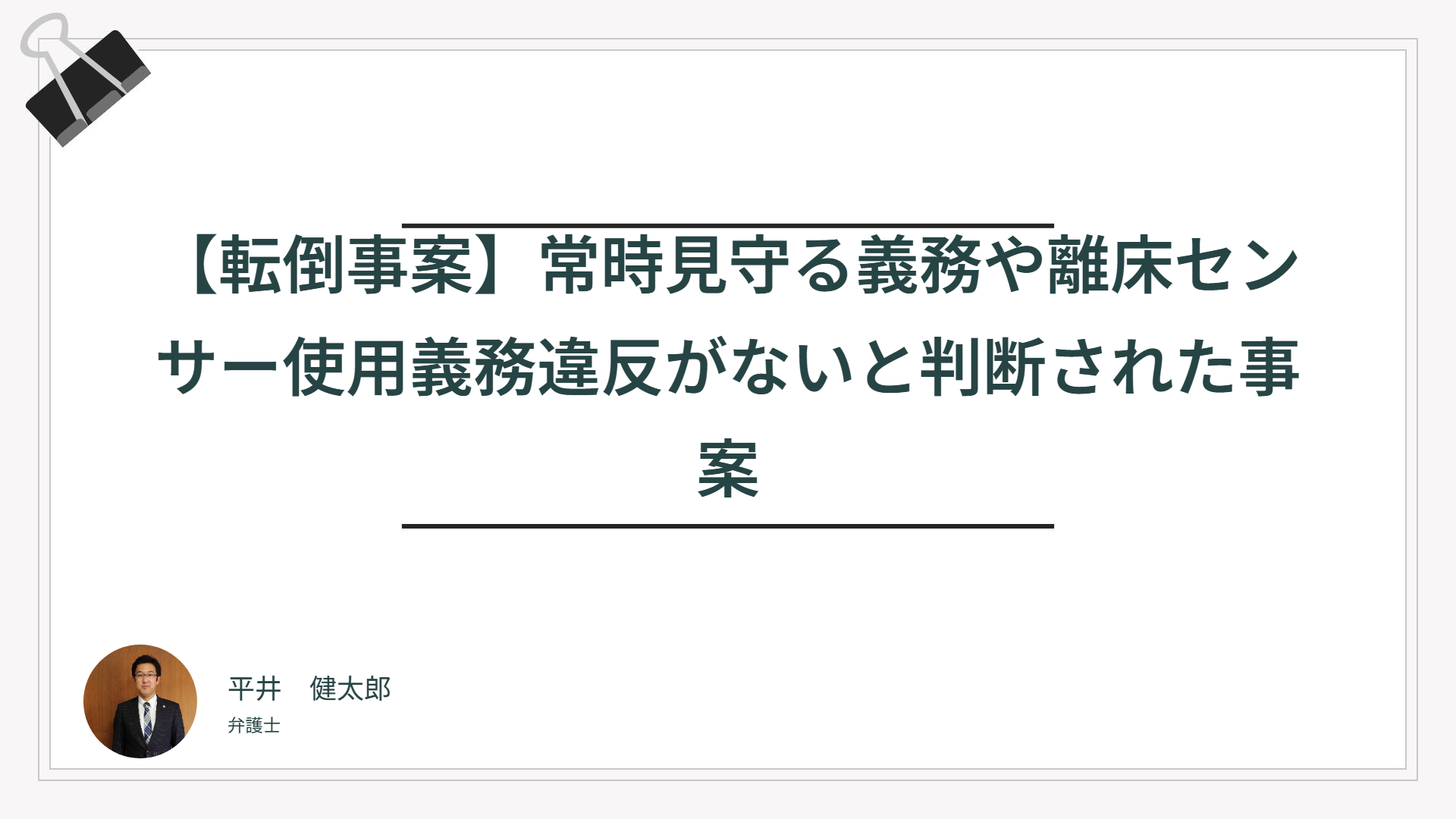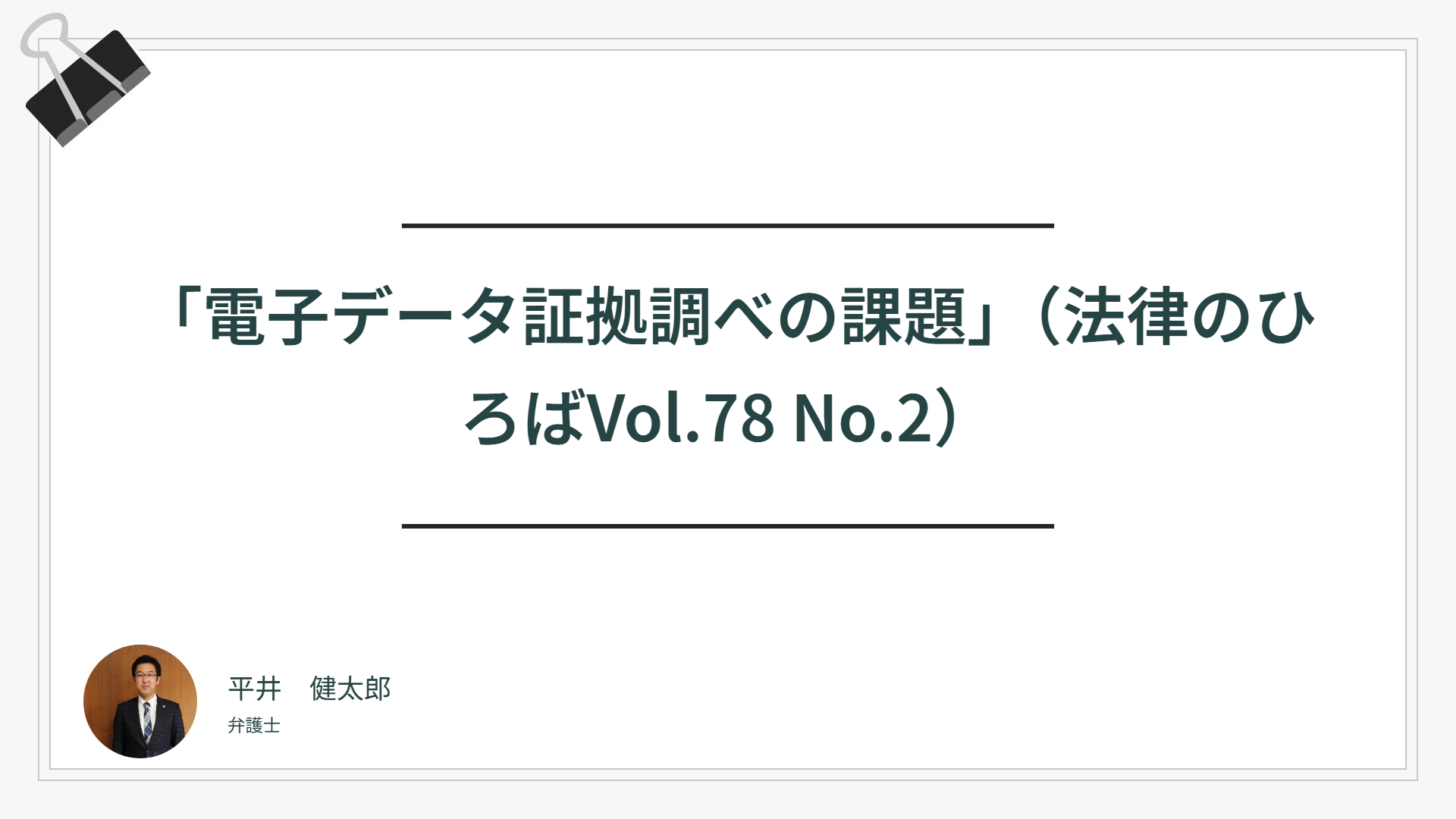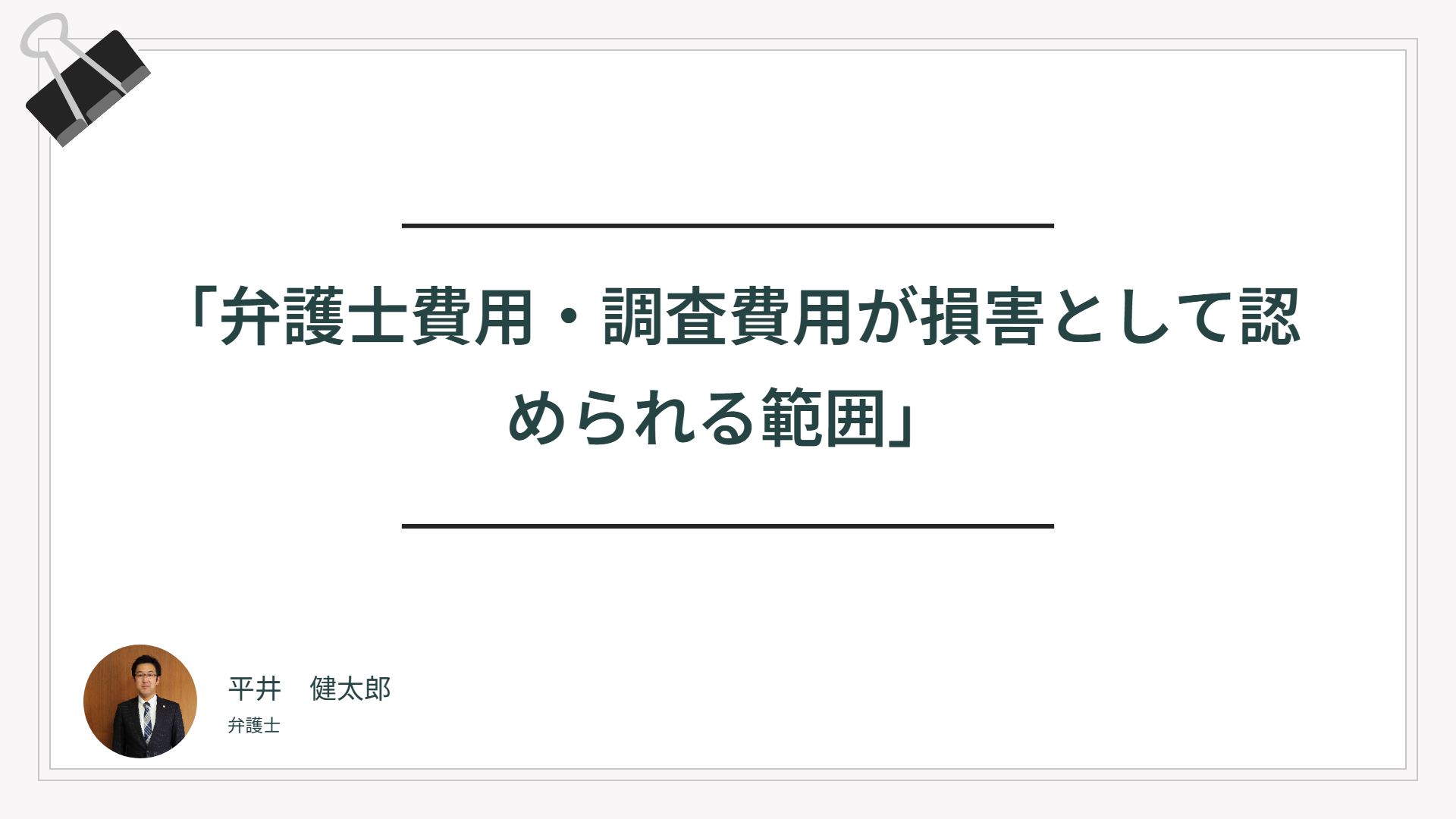在宅血液透析患者への入院指示が問題となった事案
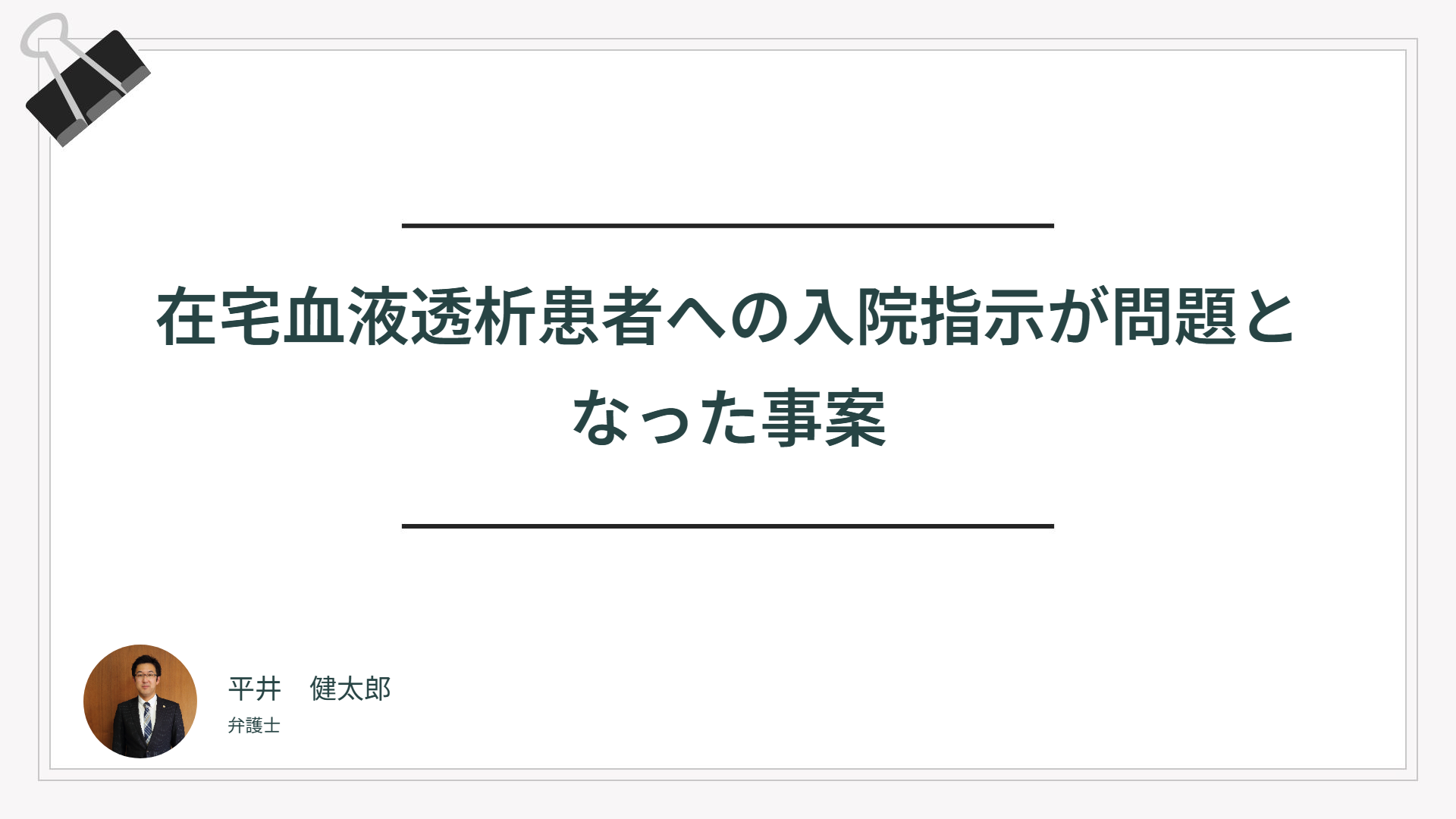
大阪地裁令和7年1月15日判決 医療判例解説vol.115
【概要】
患者に入院すべき指示義務違反があり、指示があれば心不全による致死性不整脈で亡くなることを回避できたと主張したのに対し、入院治療が必要な状況にあり入院を勧めたと判断された事案
【判旨】
「太郎が入院の相対適応があったこと自体については当事者間に争いがない。鑑定の結果においても、同日当時の太郎の状況を踏まえると、入院治療をすることが標準的で、その提案をしないことは標準的ではないとされている(鑑定書)。」
「診療契約を締結して患者を診察した医師として、入院治療が相当な状態にあると診断したのであれば、その旨を説明し、入院を勧めることが望ましいことは明らかといえる。」
「その記録内容は、診療時における被告医師と太郎の会話を逐語的に記録したものではなく、要点しか記載されていないこと・・・。これらの事情からすると、当該診療録には、次回以降の診察に用いる情報の要点だけが記載されていて、その余の問答の記載がされなかったにすぎないと考える余地があるといえるのであって、診療録に記載がない点を捉えて上記アの認定を覆すべき理由があるということはできないから、原告の上記主張及び上記意見書に係る意見を採用することはできない。」
「平成31年1月9日までに、入院治療が必要な状況にあることを説明し、入院を勧めた事実が認められ、その認定を左右させるに足りる証拠があるということはできない。」
「頻度に関する数値が低値であると言い切れないとしても、平成31年1月9日時点の被告医師において、かかる一般的な危険性を超えて太郎について突然死の危険があるとまで具体的に予見し得た合理的理由を認めるに足りる証拠はない。なお、原告が提出する上記意見書も、一般的な危険性を超えた、具体的な危険性の基礎づける事情についてまで明らかにしているとは認められない。」
【メモ】
過失については、入院を勧める注意義務の存否自体には争いはなく、具体的な義務違反行為=入院を勧めたのかどうかが争われている。
この点は、医学的知見に基づくというよりは、事実認定の問題であり、カルテや証言から、入院を勧めた事実が認められるかどうかが主に争われている。
診療記録に記載がない点については、「当該診療録には、次回以降の診察に用いる情報の要点だけが記載されていて、その余の問答の記載がされなかったにすぎないと考える余地があるといえる」と判断されており、患者側には厳しい判断にも思えるが、このような事実認定・評価がされるということを知っておく必要がある。
結果発生の予見可能性については、一般的な予見可能性と具体的な予見可能性を区別して認定判断しており、主張立証する際の注意点であるとともに、病院側からの主張に対し区別して反論すべきポイントであるといえる。