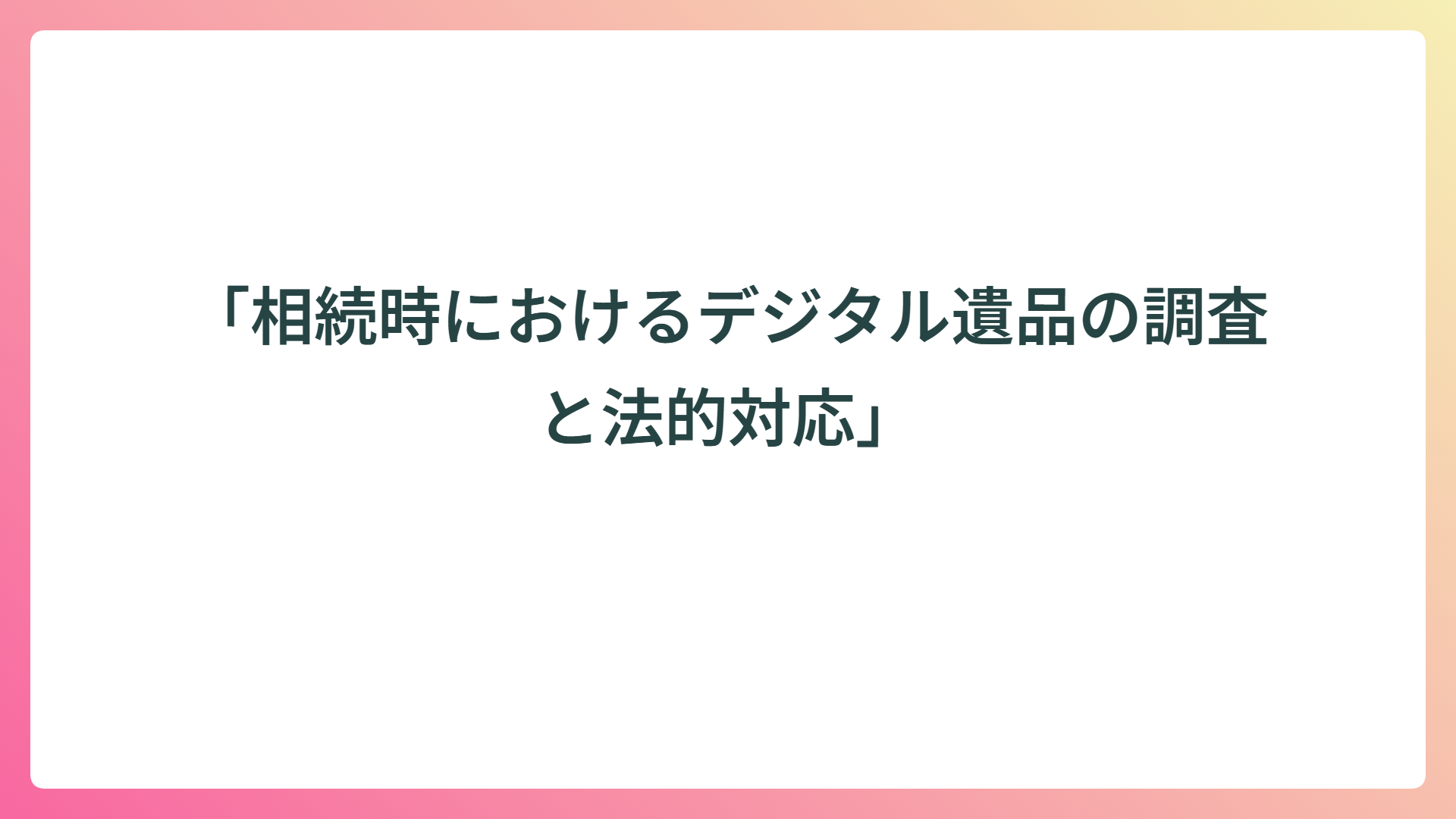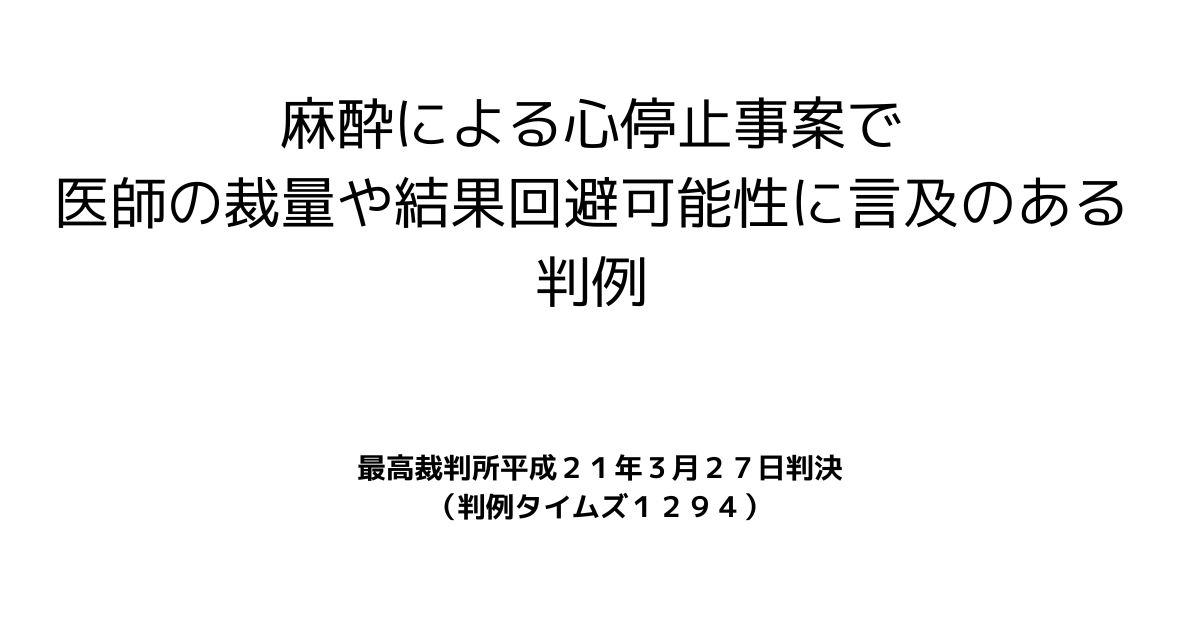重度知的障害者の逸失利益に関する裁判例
山口地裁令和5年12月20日 判例時報2617
【事案の概要】
施設利用中に施設を出て外のため池で溺死する事故が発生したことに対する損害賠償請求事件
【判旨】
①予見可能性
「本件空き部屋から本件掃き出し窓を通じて本件中庭に移動する可能性があることを予見し又は予見し得たというべきである。」
「更に、本件建物内を移動し、工事に係る作業等のために施錠されていない窓などから本件建物外に出ていくことを予見し又は予見し得たというべきである。」
「被告職員らは、Bが本件建物外に出た場合、その興味の赴くままに行動し、その結果、側溝等に転落したり、本件のようにため池に侵入したりする等の事故が発生する可能性があり、これによりその生命及び身体に危険が及ぶ可能性を十分に予見することができたというべきである。」
「上記の予見可能性を前提として、Bの生命及び身体に対して危険が及ぶのを防止するため、本件開口部からBが出られないように適切な措置を取るか、Bの行動について情報を共有し、Bの動静に十分注意すべき義務があったというべきであるところ、被告職員らには、Bの動静を注視し又は本件開口部から本件空き部屋に移動しないようにする措置を講ずることを怠った過失があるというべきである。」
「被告職員らは、Bが本件建物外において生命及び身体に危険が生じる行動をとることによって事故が発生する可能性を具体的に予見し得るのは上記アのとおりであって、この程度の予見可能性があれば具体的な結果回避措置を講ずることは可能であるから、それを超えて、更に具体的にBが本件ため池により溺死することまで予見する必要はない。」
②逸失利益
「障害を有していた現実に就労していない年少者であったので、将来得べかりし利益を喪失したことによる損害額の算定は困難であるが、証拠資料をもとに経験則とその良識を十分に活用して、損害の公平な分担という損害賠償制度の目的にかなうべく、具体的な事情に即応して蓋然性のある額を算出することとする。」
「Bが障害のない児童と比べて相当に後れを取っており、将来においてもその差の解消が困難であることを否定することはできないものの、Bが、将来の社会における職場環境の整備等と相まって、社会生活上の障害に折合いをつけ、得意な分野における能力を伸ばしていく可能性は十分にあるから、将来、障害者雇用が促進され、多様な働き方が認められた社会において、長年にわたるその就労可能機関のいずれかの時点では自身の長所を活かした稼働能力を発揮する蓋然性が認められる。」
「・・平均工賃額や、障害者雇用者の平均賃金額は、過去において実際に就労していた障害者の賃金の実態を示す統計資料ではあるものの、年少者であるBの将来における発達の可能性や障害者雇用促進の可能性を踏まえた上で逸失利益を算定するという観点からは参考にならないというべきであるから、これらを元にBの基礎収入を算定することは相当ではなく、基本的には、上記のような障害を有していたとしても年少者であるBの逸失利益を算定するには、全労働者の平均賃金を参考にすべきであると解するのが相当である。」
「知的障害については、身体的機能及び精神的機能の全てを司る脳に障害があり、発達障害も個々によって状態は様々であることから、周囲の支援等を含む総合的かつ個別具体的な支援が必要であって、潜在的な稼働能力が顕在化しても、直ちにその能力を最大限活用することが可能とも言い難い場合がある。そこで、これらの点を踏まえ、Bの基礎収入額については、就労可能期間の全体を通じて、全労働者の平均賃金(令和3年賃金センサス第1巻第1表、男女計、学歴計、全年齢の平均賃金489万3100円)の5割に相当する年収(244万6550円)とするのが相当である。」
【一言】
予見可能性については、段階を踏んで認定し、被告職員がどこまで具体的に予見すべきかについても認定している。
逸失利益については、工賃等を用いるのではなく全労働者の平均賃金を用いて判断し、結論として5割を判断している。